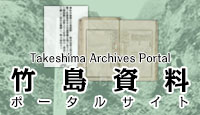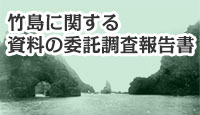本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
②竹島への渡海が幕府公認の下で行われたことがわかる資料
大谷家が幕府の役人に行った竹島渡海の説明 No.5 延宝九年酉ノ歳ニ御順見様御宿申上候覚(写)
1681年(延宝9年)5月13日
資料概要
三代目大谷九右衛門勝信の代、1681年(延宝9年)5月に幕府の巡検使(※1)が大谷家に宿泊した際、大谷九右衛門勝信が行った竹島渡海の説明(請書の控え)。
回答は五箇条からなり、最後の条に現在の竹島のことが記されている。すなわち、「厳有院様御代、竹嶋(※鬱陵島)の道筋に周回20町ほどの小島があり、草木も無い岩山で、二十四五年以前に阿倍四郎五郎様の仲介で拝領し渡海しております。この小島でもみちの魚(アシカのこと)の油を少々取っております。」とある。
「厳有院様」は徳川家綱(4代将軍:在位1651年-1680年)、「竹嶋之道筋ニ弐十町斗廻り申小嶋」は現在の竹島のことである。「廿四五年以前」は、1681年の24年以前は1658年に当たり、竹島への渡海について阿倍四郎五郎が老中の内意を得た時期No.4-1
No.4-2
と符合する。大谷、村川両家が、竹島へも幕府公認の下で渡海しアシカ漁を行っていたことを裏付けている。
※1 江戸幕府の臨時職名。幕領、私領を巡視してその政情・民情を復命させるために派遣した役人。五代将軍綱吉の頃から将軍の代替りごとに特派された。じゅんけんつかい。(『精選版 日本国語大辞典』より)
内容見本
竹嶋之様子御尋被成候ニ付此一通書申候(※4)
取持を以竹嶋拝領仕其上親共より御
目見江迠被為 仰付難有奉存候御事
所務仕申候御事
可有御座由、海上之儀ニ御座候ヘハ慥ニハ知レ不申候
御事
申小嶋御座候、草木茂無御座岩山ニ而御座候
廿四五年以前阿部四郎五郎様(※3)御取持を以拝領船
渡海仕候、此小嶋ニ而茂ミち之魚之油少宛所務
仕候、右之小嶋江隠岐国嶋後福浦より海上六十里
余茂御座候御事
※2 大猷院(だいゆういん)は三代将軍徳川家光のこと。在位1623年-1651年。
※3 阿部四郎五郎(正継)。第一条の阿部四郎五郎(正之)の長男。
※4 この2行は、文書の袖に書かれた注記。
読み下し
竹嶋の様子御尋ね成られ候につき此の一通書き申し候
五月十三日
現代語訳
※5 巡検使。 ※1へ
| 作成年月日 | 1681年(延宝9年)5月13日 |
|---|---|
| 編著者 | 大谷九右衛門勝信 |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | (大谷家文書1-19) |
| 機関コード | |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 島根県竹島資料室 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室に問い合わせを行う |