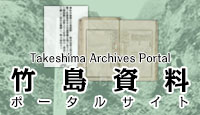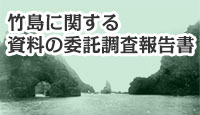本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
②竹島への渡海が幕府公認の下で行われたことがわかる資料
竹島への渡海に関する文書(1) No.4-1 阿倍権八郎から大谷九右衛門勝実に宛てた書簡
1660年(万治3年)9月4日
資料概要
阿倍(部)正継(四郎五郎)(※1)が亡くなった後、正継の養子であった阿倍権八郎(正重)が大谷九右衛門(二代目大谷九右衛門勝実:図参照)に宛てた1660年(万治3年)9月4日付の手紙。
大谷家、村川家が、鬱陵島への渡海を続けるうち、その道筋にある竹島(当時は松島と呼ばれていた)への渡海に村川家が積極的に取り組んでいたが、阿倍家の裁定により大谷家と交代で行うこととなった。それを背景に、阿倍はこの書状で、以下の内容を大谷に伝えた。
・来年(1661年(寛文元年))、鬱陵島への渡海と、初めて竹島にも渡海することについて、村川市兵衛と相談されたとおりとする。
・詳しくは家来の亀山庄左衛門から話すはずである。
この記述のとおり、翌9月5日付けで、亀山庄左衛門が、大谷九右衛門に竹島への渡海について先年四郎五郎が老中から了解を得たことなどを伝える書簡を送っているNo.4-2
。
※1 阿倍家は代々、四郎五郎を名乗っていた。大谷、村川両家に竹島渡海免許を斡旋したのが阿倍四郎五郎正之。正之の長男が阿倍四郎五郎正継で1660年3月16日に亡くなった。正継は、存生中に末弟の権八郎(正重)を養子に迎えた。
内容見本
尚々亡父四郎五郎
我等へ両通之紙面
令披見得其意候、
遠路御飛札過分之至候、
近日村川市兵衛可被致当着候間
其節可申述候、已上
過八日之御飛札到来、
殊下緒壱具贈給
過分之至候、其元相替
儀無之無事之旨令
祝着候、亡父四郎五郎方へ
預御音札令承知候、去
三月相果、我等共々悲
嘆申事候、来年御手前
舟竹嶋へ渡海、松嶋へも
初而舟可被指越之旨
村川市兵衛と被致相談
尤ニ候、委細者家来
亀山庄左衛門方より可申
達候間、不能詳候、
恐々謹言
阿倍権八郎
九月四日 政重(花押)
大屋九右衛門様
御返事
読み下し
尚々(なおなお)
亡父四郎五郎
我等へ両通の紙面
披見せしめ、その意を得候
遠路御飛(ごひ)札過分の至りに候、
近日村川市兵衛到着致さるべく候間
其節申し述ぶべく候、已上
過ぎる八日の御飛(おひ)札到来、
殊に下緒壱具贈り給い
過分の至りに候、其元相替る
儀これなく無事の旨
祝着せしめ候、亡父四郎五郎方へ
御音札に預かり承知せしめ候
去る三月相果て、我等共々悲しみ
嘆き申す事候、来年御手前
舟竹嶋へ渡海、松嶋へも
初めて舟差し越されるべき旨
村川市兵衛と相談致され
尤もに候、委細は家来
亀山庄左衛門方より申し
達すべく候間、詳しく能(あた)わず候
恐々謹言
阿倍権八郎
九月四日 政重(花押)
大屋九右衛門様
御返事
現代語訳
去る八日に出された急々の御手紙が到着し、その時、共に下緒(※)一つお贈り下さって御礼の申しようもありません。貴方様にはお変わりもなくお過ごしのご様子でお喜びいたします。
亡くなりました四郎五郎への手紙も受け取り承知いたしました。去る三月に父は亡くなりまして、私たち家族は悲しみ嘆いております。
来年、貴方様の船が竹島へ渡海、松嶋へも初めて船を向かわせることは、村川市兵衛と相談されたとおりでよろしいと存じます。詳しくは家来の亀山庄左衛門から伝える予定につき、詳しくは申し上げません。恐々謹言
阿倍権八郎
九月四日 政重(花押)
(追伸)
またまた、申し添えます。
亡父四郎五郎と我ら宛二通の手紙を読ませていただき、御主意を承知いたしました。遠い所から、急々の御手紙を頂き、大変ありがたく御礼申し上げます。
近い内に村川市兵衛がこの地へ来られるそうですから、その時にお話ししようと思います。以上
大屋九右衛門様
御返事
※下緒 (さげお)とは、日本刀の鞘に装着して用いる紐のこと。
| 作成年月日 | 1660年(万治3年)9月4日 |
|---|---|
| 編著者 | 阿倍権八郎政重 |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | (大谷家文書2-35) |
| 機関コード | |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 島根県竹島資料室 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室に問い合わせを行う |