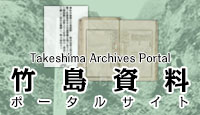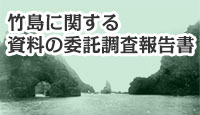本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
②竹島への渡海が幕府公認の下で行われたことがわかる資料
竹島への渡海に関する文書(2) No.4-2 亀山庄左衛門から大谷九右衛門勝実に宛てた書簡
1660年(万治3年)9月5日
資料概要
阿倍(部)権八郎正重の家来である、亀山庄左衛門から大谷九右衛門(勝実)に宛てた書簡で、竹島への渡海について、先年、先代の阿倍四郎五郎正継が老中の内意を得ており、村川市兵衛と大谷九右衛門が年番を決めて渡海するという証文も渡しているので、村川と相談の上、証文の通り実行するように伝えている。(経緯についてNo.4-1参照)
内容見本
猶以村川市兵衛殿近日
御当地へ御参府可被成由
被仰越候、左候ハヽ渡海之
儀様子直段ニ可承候、市兵衛
被帰候時分委細可申入候、
先年相渡し候證文ニ具
可有御座候間、今以其通ニ
舟御渡し可被成候、御仕合能
可有之と存事候、追而御
吉左右可承候、已上
八月八日之御飛札拝見、先以
貴様御無事之由目出珍重
存候、然者四郎五郎儀去三月
上旬より煩出し、同月十六日ニ
相果被申候、各様も久々之
御知人ニ候間、可為御迷惑と察
入候、跡職之儀ハ存生之内
末之弟権八郎致養子、公儀
相済候間可安御心候、病中ニも
御老中様各御見廻被成
色々御懇被遊外実難
有四郎五郎被存候、権八郎
儀今以四郎五郎同前ニ
御老中様御懇御座候間可安
御心候、御用之儀も御座候ハヽ
四郎五郎同前ニ可被仰越候、
少も如在申間敷候、将又来
年より竹嶋之内松嶋へ貴様
舟御渡し之筈ニ御座候旨
先年四郎五郎御老中様へ
得御内意申候、渡海之番
年相定市兵衛殿貴様へ
證文相渡し置候間、村川殿と
御相談候而其證文次第ニ
可被成候、市兵衛殿も貴様も
其證文之通少も御違背者
有之間敷儀と存候、猶
期後音之時候、恐惶謹言
亀山庄左衛門
九月五日 ■■(花押)
大屋九右衛門様
読み下し
猶(なお)以村川市兵衛殿近日
御当地へ御参府ならるべき由、
仰せ越され候、左候はば渡海の
儀様子直段に承るべく候、市兵衛
帰られ候時分、委細申し入るべく候、
先年相渡し候證文に具(つぶさに)
御座有るべく候間、今以其通に
舟御渡しならるべく候、御仕合能(よく)
これあるべしと存じ候、追而御
吉左右承るべく候、已上
八月八日の御飛札拝見、先以
貴様御無事の由、目出珍重に
存候、しからば、四郎五郎儀去三月
上旬より煩出し、同月十六日に
相果申され候、各様も久々の
御知人に候間、御迷惑たるべしと察
入候、跡職(しき)の儀は存生の内
末の弟権八郎養子に致し、公儀
相済候間御心安かるべく候、病中にも
御老中様各御見廻なられ
色々御懇(ねんごろ)あそばされ外実
難有(ありがたく)四郎五郎存ぜられ候、権八郎
儀今以四郎五郎同前に
御老中様御懇に御座候間、
御心安かるべく候、御用の儀も御座候はば
四郎五郎同前に仰せ越さるべく候、
少も如在申すまじく候、将又(はたまた)
来年より竹嶋の内松嶋へ貴様
舟御渡しの筈に御座候旨、
先年四郎五郎御老中様へ
御内意を得申し候、渡海の番
年相定め市兵衛殿貴様へ
證文相渡し置き候間、村川殿と
御相談候て其證文次第に
成らるべく候、市兵衛殿も貴様も
其證文の通り少も御違背(ごいはい)は
これあるまじき儀と存じ候、猶
後音の時を期し候、恐惶謹言
亀山庄左衛門
九月五日 ■■(花押)
大屋九右衛門様
現代語訳
八月八日のお手紙拝読しました。
先ず、貴方様がお元気でおられるとのこと目出度く存じます。
一方、こちらの(安倍)四郎五郎が去る三月初旬に病になり、同月の十六日に亡くなりました。皆様も長い間の御知り合いですから、
戸惑っていらっしゃることとお察しいたします。
(阿倍家の)跡継ぎについては、(四郎五郎が)存命中に末弟権八郎を養子にし、すでに、公儀に養子縁組を届け出て承認されていますのでご安心ください。
(四郎五郎の)病気のあいだには御老中様が各々お見舞いくださり色々ご親切にしてくださり誠にありがたいことだと四郎五郎も喜んでおりました。
権八郎は、四郎五郎同様に御老中様と親しくしておりますからご安心ください。
御用があれば、今までの四郎五郎のときと同じく申し出てください。
少しも躊躇されることはありません。
さて、又、来年から竹島の内松島へ貴方様の船が渡海されるはずとのことについて、先年、四郎五郎が御老中様から御内意を得ました。渡海の年番を定め、市兵衛殿と貴方様へ証文を渡してあるので、村川(市兵衛)殿と相談の上、その證文のとおりにしてください。
市兵衛殿も貴方様もその證文通り、少しも背く事は無いと思っております。
それではまた後の機会まで。恐々謹言
亀山庄左衛門
九月五日 ■■(花押)
(追伸)
猶添えて書き加えます。
村川市兵衛殿が近日中に江戸へ来られるとの知らせがありました。
来られたなら、その時に渡海の件、
様子を直接聞くことが出来るでしょう。
市兵衛殿が(米子へ)帰られたらくわしく(江戸での事を)話されるでしょう。
先年、お渡しした證文に詳細に書かれていますので、
今もそのとおりに渡海なされるように。
うまくいくと存じます。
良い話をお聞き出来る事でしょう。以上
大屋九右衛門様
| 作成年月日 | 1660年(万治3年)9月5日 |
|---|---|
| 編著者 | 亀山庄左衛門 |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | (大谷家文書2-34) |
| 機関コード | |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 島根県竹島資料室 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室に問い合わせを行う |