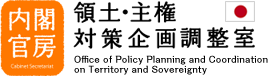本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
総合的論点
コラム 尖閣諸島、竹島、国際裁判
中谷 和弘 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
1. はじめに
本小論においては、国際法の観点から次のような高度に仮定的な問いへの簡潔な回答を行う。即ち、尖閣諸島と竹島の領有権問題がもし国際司法裁判所(ICJ)で争われて本案まで進んだとしたら、良識的な裁判官はどのような判断を示すことが期待されるかということである。
2. 尖閣諸島問題における本案の要点
尖閣諸島に関しては、国際裁判の管轄権の根拠も領土紛争も存在しないため、この問題がICJで本案段階に進むことは極めて仮定的な話である1 。そう指摘した上で、尖閣諸島問題の本案の要点は、オーソドックスな国際法の解釈・適用に従うと、次の通りである。
1895年1月、日本政府は尖閣諸島を、それまで無主地であったのみならず他国の支配が及んでいなかったことを確認の上、閣議決定の発出により沖縄県に編入した。 PCIJ「東部グリーンランド事件」判決(1933年)で示された通り、領有主権の要求には、「主権者として行動する意図及び意思」並びに「当該権原の現実の行使又は表示」という二つの要素の存在を立証しなければならない2。 無人島である尖閣諸島に対する日本の占有は、同諸島に対する実効的、継続的かつ平穏な領有主権を行使するもので、これら2つの要件を充足している。
1895年の編入の際に日本は近隣諸国に対する通告を行っていないが、特別の条約の定めがないかぎり他国への通告が一般国際法上の要件とまではいえない。「クリッパートン島事件」仲裁判決(1931年)では「フランスの占有の適法性もやはり、他国への通告を行わなかったために問題視されてきた。しかし、上述のベルリン議定書第34条に規定されたこの通告義務は本件には適用されないということに留意すべきである。同議定書に対して何等かの方法で公知を付与することで十分であり、フランスは上に示したような方法でその行為を公表することにより、この公知性を生じさせたと考えるべきである」3と述べている。この閣議決定は、日清戦争とは無関係に、かつ、1895年4月の下関条約の締結以前になされたものであり、同条約で日本に割譲された台湾及びその附属島嶼に尖閣諸島は含まれない。
中国政府は尖閣諸島が無主地ではなかったことを説得的に証明していない。「パルマス島事件」仲裁判決(1928年)4において指摘されたように、国際法では単に島を発見することは未成熟の権原にすぎない。また、地図は限定的な証拠価値しか有さない。ICJ「ブルキナファソ・マリ国境紛争事件」判決(1986年)は、「地図それ自体は事案毎に正確性が異なる情報を構成するにすぎない。 地図それ自体は、また単なるその存在のみによっては、領域的権原を構成するものではない、即ち、領域的権利を確立する目的で固有の法的効力を国際法上付与される文書たりえない」5と述べている。
中国側は、日本が1895年に閣議決定により尖閣諸島を沖縄県に編入してから1970年頃までの約75年もの間、日本に対して抗議を行うことも、尖閣諸島に対する自らの領有権を主張することもなかった。中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を突如始めたのは、1968年秋に国連アジア極東経済委員会(ECAFE)が東シナ海に石油埋蔵の可能性があることを指摘してからである。 4分の3世紀にもわたる長期間の沈黙は、国際法上、黙認(acquiescence)を構成する。ICJ「プレア・ビヘア寺院事件」判決(1962年)6が指摘するように、「抗議をなすべきであり、かつ可能な場合に、沈黙をした者は黙認をした者とみなされる」(Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset)。 さらに、1920年5月に中華民国駐長崎領事が、遭難した中国漁民を助けた日本人に宛てた感謝状の中で「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と記載した事実や、1953年1月8日の人民日報において「尖閣諸島は琉球諸島に含まれる」旨の記事が掲載された事実は、尖閣諸島が日本領であることを中国側が「自認」したことを明確に示している。 これらのことから、中国が尖閣諸島について自らの権原を主張することは、国際法上の根拠を欠くと同時に禁反言(estoppel)の法理に反し、認められるものではない。
註1
もし中国が尖閣諸島問題をICJに付託したければ、まずICJの強制的な管轄権を受け入れた(日本は1958年以来そうしている)上で、日本を提訴することによりそれが可能になる。その場合でも、日本は先決的抗弁において尖閣諸島に関する領土紛争は存在しないと主張するかもしれない。この抗弁が先決的に判断されるか本案に併合されて審理されるかはICJの裁量に属する。
註2
PCIJ Ser.A/B, No. 53, pp. 45-46.
註3
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 1110.
註4
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 846.
註5
ICJ Reports 1986, p. 582.
註6
ICJ Reports 1962, p. 23.
3. 竹島問題における本案の要点
竹島については、日本は1954年9月、1962年3月、2012年8月の3回にわたり韓国に対して、領有権問題のICJへの付託を提案したが、韓国はこれを拒否した。竹島問題が本案に進んだ場合の要点は、オーソドックスな国際法の解釈・適用に従うと、次の通りである。
日本政府の立場は、日本は古くから竹島の存在を認識し、遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立したというものである。1905年1月28日の閣議決定により、日本は竹島を領有する意思を再確認し、島根県に編入した。この閣議決定は、1905年11月の日韓保護条約及び1910年8月の日韓併合条約の締結とは無関係になされたものである。さらに日本はその後も竹島でのアシカの捕獲を許可制にして、これを第二次世界大戦によって1941年に中止されるまで続けるなど、主権者として実効的支配を続け、十分な期間にわたる継続的かつ平穏な主権の表示を行ってきた。「当該領域に対する国家の機能の継続的かつ平穏な表示は領域主権の構成要素であるとの原則」を指摘した「パルマス島事件」仲裁判決(1928年)7の基準に従えば、竹島に対する日本の主権は国際法上、確立されたといえる。
1951年9月のサンフランスシコ平和条約第2条(a) において、「日本は韓国の独立を承認し、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とした。しかし、同項において日本が放棄した「朝鮮」に竹島は含まれない。 サンフランシスコ平和条約が署名される1か月前の1951年8月10日、米国のディーン・ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補は梁裕燦(Yang Yu Chan)韓国駐米大使に対して、「ドク島または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、 1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとはみられない」と明確に回答したのである 8。サンフランシスコ平和条約の中心的な締約国であった米国の条約解釈は大きな証拠価値を有する。
さらに、万が一放棄の範囲について疑いがあるとしても、国際法上、放棄は推定されず、放棄者に有利な狭い意味において解釈されなければならない。「Campbell 事件」仲裁判決では「放棄は決して推定されないことはすべての国家の法で認められている。 放棄は権利、能力又は期待さえもの遺棄を構成するため、常に狭義の解釈に服することになる」 9旨を指摘している。 また、Eric Suyは1962年に論文の中で「放棄の効果は権利の消滅であるため、その意図は狭義に解釈されるべきで、疑義が生じる場合、放棄者に有利な意味で解釈されるべきである」10と述べている。 「インド・パキスタン西部国境(Rann of Kutch)事件」仲裁判決(1968 年)におけるLagergren仲裁裁判長意見も同様の考えに基づくものと思われる11。
したがって、サンフランシスコ平和条約の下で日本が放棄した「朝鮮」地域に竹島が含まれていないことは明らかである。
竹島に関する紛争の決定的期日については、1952年1月に、韓国が国際法に違反して、いわゆる李承晩ラインを一方的に公海上に定めた時点とするのが合理的である。1954年8月には韓国の警備隊の隊員が竹島に駐留していることが確認されている。] 国際法上、島に対する侵攻や違法な占領の継続から法的権原は生じない(不法から権利は生じない(Ex injuria non oritur jus))のである。
註7
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 840
註8
「平成28年度 内閣官房委託調査
竹島に関する資料調査報告書」
註9
RIAA, vol. II, p. 1156.
註10
Eric Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public (LGDJ, 1962), p. 185.
註11
RIAA, vol. XVII, p. 565.
同意見では、「この点に関するいかなる不確実性もパキスタンにとって有利に解決されるべきである。なぜなら、Kutch地区からの請求は、その形式ゆえに及び他の行為によって支持されていないゆえに、請求当事国に不利に狭義に解釈されなければならならず、英国当局によって発せられた声明も同様に理解されなければならず、広義に解釈されてはならない」と指摘する。