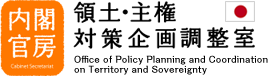本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
他国の主張分析
コラム
尖閣の海と島は前近代において
どう利用されてきたのか
平野 聡 (東京大学法学部教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
1. 明清と台湾
石垣島の北に浮かぶ尖閣諸島は19世紀まで、琉球と中国のあいだの大海原を往来する人々にとって、航路標識として頼るべき島でした。水先案内人をはじめ、海を行く人々は、尖閣諸島が見えて来ると航海が半ばに達したことを思いつつ、那覇あるいは中国の福州を目指したのです。
もっとも、言語が異なれば、同じ地理的存在を異なる固有名詞で呼ぶことは珍しくありません。そこで、中国の歴代王朝とされる明や清の史書では、今日の尖閣の島々を指して釣魚嶼・赤尾嶼・黄尾嶼(それぞれ魚釣島・久場島・大正島)と呼んでいました。倭寇を強く意識した海域の防衛論や、琉球に派遣された皇帝の使節(冊封使)が執筆した報告書に付された地図には、たしかにこれらの島々が描かれています。
しかし明や清は、尖閣をはじめ大陸から遠く離れた島々に対して、必ずしも支配の実績を挙げていたわけではありません。そもそも、台湾に対する支配ですら、比較的新しい時代の話です。かつて鶏籠嶼と呼ばれた台湾は、明代後期にあたる17世紀まで、今日台湾で原住民と呼ばれるオーストロネシア語族の人々(フィリピン・マレーシア・インドネシアと文化的に連続)が暮らす大地でした。 今日の台湾で多数を占めている華語を話す人々(漢人)が、大陸から台湾に渡って暮らし始めたのは、今から約400年前、17世紀前後からの話です。17世紀半ばには、台湾の西部がオランダに占領され、さらに17世紀後半の約20年間、明の滅亡ののちも明への忠誠を誓い続けた鄭氏が台湾に逃れて支配していました。 今日の中国が正統と見なしている王朝がようやく台湾の西部を支配するようになったのは、清の康煕年間、17世紀末以後のことです。
その後、台湾東部のうち、最も北にある宜蘭県については、18世紀以後次第に清の勢力が及びました。しかし、台湾を南北に貫く山脈に距てられた現在の花蓮県と台東県については、険しい海と山に距てられ、19世紀後半になっても清の支配は及びませんでした。 台湾東部ですら、中国の正統な王朝は関与しなかった以上、台湾から遠く離れた海上に浮かぶ航路標識の島としての尖閣諸島については、その存在が航海をする人々に知られていても、実際に清が支配するという状況にはなかったのです。
2. 倭寇と前近代の海域防衛
このような中、尖閣諸島を取り巻く海域において最も活躍していたのは、琉球の船乗りであり、日本人を中心とした海賊集団である倭寇でした。
倭寇に対し、明・清がどのような対応をとろうとしていたのかをみれば、先にみた台湾支配の実態と相まって、明・清の海域への態度を理解することができます。
例えば『籌海図編』や『武備志』といった、明代に著された兵法書をひもとけば、倭寇の襲来に見舞われた浙江省や福建省の当局者にとって、海の防衛は大陸の沿岸で行うのが常識でした。とりわけ、倭寇との対戦は、大陸の都市に面した湾口に倭寇を引き入れ、陸に設けた要塞を活かして迎え撃つという戦法をとっていました。 逆に、遠洋に軍艦を出して倭寇を取り締まるという発想は、波の荒さ、海の広大さゆえの海上警備の非効率、突然現れる浅瀬の岩礁に乗り上げる危険性、といった理由で排除されていました。そこで、こういった兵法書を見てみると、中国大陸の沿岸部については、倭寇を迎え撃つ都合上、非常に詳細な地理情報が記されていますが、大陸から遠く離れた島については、極めて曖昧・漠然とした位置関係のまま列挙されているに過ぎなかったのです。
官や兵が出向いて管理することを想定しない、絶海の彼方の曖昧な空間にある島。それが、前近代の明・清からみた「釣魚嶼」すなわち尖閣諸島の姿でした。
したがって、明は琉球に国王としての称号を付与(冊封)するための使者を送ろうとしても、不案内な航海であることに加えて、準備のために福州の人々が消耗することに悩まされていました。とりわけ、琉球の王が長命で、代替わりの間隔が開くと、前回の冊封使の経験が福州側に受け継がれておらず、苦労することの繰り返しでした。 だからこそ、冊封使が福州と那覇とのあいだを往復する際には、水先案内人(看針通事)以下の主要な乗組員は、ふだん貿易のために尖閣の海域を自由に行き来している琉球人に頼ることが一般的でした。
3. 曖昧な境界線
明や清は尖閣諸島を管理しようとする発想を持たなかった以上、尖閣諸島を取り巻く境界の意識も極めて曖昧でした。そのような中、「境界」をめぐる記述は、冊封使が琉球人の水先案内人や乗組員との間で交わしたやりとりにおいて現れます。
中国が尖閣問題をめぐって2019年9月に発表した「釣魚島白書」は、那覇に向かう冊封使が残した記録、すなわち「冊封琉球使録」の中に出て来る文言から、前近代の段階で尖閣諸島と琉球の間に明確な境界線があったとしています。 例えば、陳侃『使琉球録』(1534年)には、古米島(久米島)が見えてくると琉球側の乗組員が「戻ってきた」と喜んだという記載があり、謝傑『琉球録撮要補遺』(1579年)及び夏子陽・王士楨『使琉球録』(1606年)には「黒水溝」「黒水・蒼水」という潮目が現れるという記載があることから、中国と琉球の「中外の境界」が前近代の時点ではっきり意識されていたとしています。 そのうえで同「白書」は、「釣魚島、赤尾嶼は中国に属し、久米島は琉球に属し、境界線は赤尾嶼と久米島の間の黒水溝(現・沖縄トラフ)にあるとはっきり記している」としています。
しかし、そもそも人の住まない航路標識の島に「帰って来た」感情を懐く人はいないでしょう。また、そもそも潮目は全く現れなかったり、いくつも現れたりもするものです。1800年に琉球に向かった清の使者・李鼎元は『使琉球記』を記した中で、潮目が現れなかったことから「そもそも黒溝など存在しない」と言い切っています。 このように曖昧な地理認識や自然現象をもって、「国境線がそこにあった」ということは出来ませんし、それを海底の地形である沖縄トラフと同じものとして扱うことも出来ません。
4. 領域・領海・境界を明示する近代
西洋では近世以後、土地と国民を有効に支配して責任を持つ主権国家が生まれ、主権国家どうしの関係をどう律するかを示した国際法がつくられました。そして19世紀半ば以後、西洋を中心とした近代の国際関係がアジア太平洋地域を覆い尽くす中で、日本・清も国際法を次第に採用するようになりました。 海洋についても国際法のもと、陸地のまわりの領海と、それ以外の公海に分けてとらえられるようになりました。
すると、それまでは誰が管理するのか曖昧なままでも良かったあらゆる島が、果たしてどの国に属するのか、そして海域のどこを領海とし、あるいは中間線を引くのかが問題とされるようになりました。もちろん、複数の国々が互いに「自分の土地だ」と主張し合っている場所について、そのうちの一国が一方的に境界線を引けば、必ず国際紛争が起こります。 しかし、長年誰も管理も主張もしていなかった土地について、そこにゆかりの深い国が、誰からの反対も受けず平和裏に管理を始めるとき、国際法はその国に土地と領海の支配権、すなわち主権を認めています。 尖閣諸島は、琉球あらため沖縄県の人々が海域を利用するうえで縁の深い土地であったために、明治政府が1895年に、正式に日本の領土としました。
以来、第二次大戦後の一時期において、尖閣諸島を含む沖縄県の施政権は琉球列島米国民政府のもとにありましたが、1972年に沖縄県が日本政府の統治のもとに復帰したことで、尖閣諸島も今日まで一貫して日本政府が管理しています。