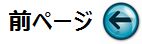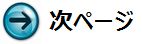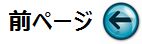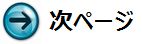懇談会が注目する3つの視点(3つの軸)
III パブリック(公共)に参加し、国とともに支えよう(公共を「他人ごと」から「自分ごと」へ。)
|
【問題意識】
パブリックは誰のものか。パブリックというと、日本では「国が提供するもの」という意識が強い。しかし、欧米では「私たちのもの」と意識される。
そうした中、日本においても、社会起業家などが社会課題に取り組み、家族でない者同士が助け合い補完し合うシェア社会が広がり、また価値を共有したコミュニティやアソシエーションの力に期待が寄せられ始めている。
ITを活用したパブリックへの参加機会の拡大も意識される中、私たちの知恵や経験や労働力をパブリックの形成にあてる社会を実現できるか。
パブリックを「他人ごと」としてではなく、「自分ごと」として捉え、参加していくことが求められる。
- 問題意識を共有し、社会課題の解決に参加しよう 第7回
-
行政が何でもやる時代は終わり。ニーズの多様性・細分化の中で、公では対応しきれない面も。 第5回
-
税を通じて官が政策サービスを提供する形から、企業や市民が連携し て、パブリックを提供する時代になっていく。 三浦
- 社会貢献意識の高まりは、国家への依存心を変えるか? 第2回
- 要望陳情型をやめて、公共的な事業への「参加」を促そう。 山崎
- 何のための参加か?そのためには、問題意識をより多くの人と共有する必要がある。
- クラウドファンディングの活用。 米良
- パートタイムで人材を流動化。
- 人の目を気にせず、自分をもっと表現しよう。 諏訪
- サイレントマジョリティの意見をいかに「見える化」するか?彼らに意思決定をうまくしてもらうための仕組みが必要。
- 家族の枠を超えた支え合い。それをどう支え、加速させていくかを考えよう。
-
おひとりさま社会のセーフティネットとしてのシェアハウスの広がり。お互いができることをして、できないことは支えてもらう支え合いの輪「シェア社会」 三浦
-
独身者や共働きの増加で、「血縁」の文化が少しずつ成り立たなくなっていく。今後は「知縁(知人や学びの縁)」や「地縁(土地や地元の縁)」の時代に変わっていく。 牛窪
- 金銭で示されない社会的関係の活用、重要性。
- コミュニティに人が参加するというのはどういう現象なのか?異文化異世代とのコミュニケーションがカギ。危機感もきっかけ。若い人が地域に入ると集落は変わる。 第2回
- コミュニティ↓(地域共同体)とコミュニティ↑(アソシエーション) 第10回
- 「バーチャルゆるつながり」の先に社会起業や多様性、農業イノベーションもある。winwinシニア(シニア同士、シニアと社会の相互扶助)。 牛窪
- 限界集落は限界じゃない、同居ばかりが家族じゃない、実際には農村は豊かな社会。「生活の営み」としての農業。優秀な人でないと暮らせない「農村」暮らしの魅力。少子高齢化と農村コミュニティの活用可能性。 第3回 徳野
- 地域社会の要請と自分たちがやりたいと思っていることを、上手に重ねていこう 第10回
-
社会を変える第一歩の踏み出し方
-
参加型社会は人々が地域社会に貢献する社会だが、それが楽しいものでなければ長続きしないのが実情。地域に貢献しつつ、楽しいことであり、どんどん続けて発展させていきたくなるようなプログラムとは?
- 社会が求めている公共と、住民が自発的に楽しくやりたい公共のすれ違いをどう重ねるか。デザインをどう活用するか?
- 情報量が多過ぎる社会だからこそ、「手ざわり」感ある機会を提供して、地域の人と人とを「つなぐ」良質な「分権型商社」のような存在が求められる。 山崎
- システムやデザインをうまく工夫して社会課題の解決を推し進めよう。 第7回
-
参加型社会における行政の役割は、税を投じるのとは違ったことになるはず。 山崎
-
「非営利」、「慈善」に限らない「社会的起業」は、社会課題の解決のためのシステム設計を行う起業家。
- 「営利」、「非営利」で線を引くべきでない。きちんと経済が回るデザインなしに社会貢献への支援はできない。社会課題解決への多様な主体の参加、営利・非営利のうまい使い分けが重要。
- デモとは違う、新しい「社会運動」としての社会起業。
- コミュニティ継続計画作りを通じたコミュニティ醸成。 第4回
- 日本農業最大の魅力は、豊かな消費者の存在。これからの暮らし方の選択次第で、農業は変わる。 第3回
|
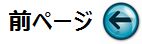 |
|
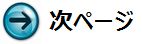 |