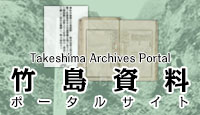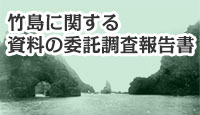本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
③将軍への拝謁、産品献上等に関する資料
大谷九右衛門勝実による将軍への拝謁の記録 No.6 竹島渡海由来記抜書控
作成年代不詳
資料概要
竹嶋渡海由來記抜書控は、大谷家が渡海の経緯を後年まとめた記録(※1)で、二代目の九右衛門勝実が御目見(将軍への拝謁)と献上を行ったことについて書かれている。御目見は、1671年(寛文11年)をはじめ何度も行われたが、記録が焼失しているものもあると記載されている。村川家が御目見を行ったことについても言及されている。
また、1671年の御目見の際、幕府の役人に産品を献上した際の相手方、内容について記録がある。文中に「竹嶋」とあるのは鬱陵島のこと。
※1 大谷文子氏は、大谷九右衛門勝意が文政の頃に書き写したものと考えられるとする。No.1
内容見本
二代目 九右衛門勝實
勝實幼名惣助於江府九右衛門と改号及老年隠居シ瀬兵衛と改此惣助若年之時父勝宗為名代江府江詰前記如ク首尾能 御目見仕其後数度 御目見仕則参府度毎記録有之処焼失尤
寛文十一年亥五月廿八日
御目見仕并ニ延宝七年未七月参府其翌八月
御目見仕右両度分献上之品并ニ御役人様勤門控左之通書顕
猶延宝九年酉七月村川市兵衛参府之節御達書ニも顕然たり
寛文十一年亥五月廿八日
御目見仕砌御勤門左之通
御公方様江獻上箱肴 但例之通竹嶋鮑五百貝一折
酒井雅楽守(ママ)様
同 河内守様
阿倍豊後守様
稲葉美濃守様
久世大和守様
土屋但馬守様
板倉内膳守(ママ)様
右御七人様江竹嶋鮑五百貝入一折宛
(略)
現代語訳
二代九右衛門勝實
勝實は幼名を惣助という。江戸で九右衛門を襲名、老いては隠居し瀬兵衛と改名した。この惣助は若い時に父勝宗の名代として江戸に滞在し、前記のように首尾よく御目見をこなし、その後も数回御目見にあずかっており、参府のたびの記録もあったが、焼失してしまった。ただし、寛文十一年(1671年)亥の五月二十八日の御目見および延宝七年(1679年)未の七月参府し翌八月に行われた御目見(※2)、この両度分の献上品と御役人様方へ差し上げた品の控えは、次に書き表すとおりである。なお、延宝九年酉の七月村川市兵衛が参府した時、頂いた御達書によってもはっきりとしていることである。
寛文十一年亥の五月二十八日御目見の時に差し上げた品々は左の通りである
御公方様へ献上箱肴 但し 例の通り竹嶋鮑五百貝一折
酒井雅楽守(頭)様
同 河内守様
阿倍(部)豊後守様
稲葉美濃守様
久世大和守様
土屋但馬守様
板倉内膳守(正)様
右御七人様へ竹嶋鮑五百貝入一折宛
(以下略)
※2 延宝七年(1679年)の参府、御目見ついては、実際には三代目の勝信が代理で行った。
| 作成年月日 | 作成年代不詳 |
|---|---|
| 編著者 | - |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | -(大谷家文書1-3) |
| 機関コード | |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 島根県竹島資料室 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室に問い合わせを行う |