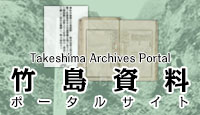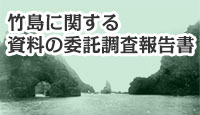本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
①大谷家、村川家の鬱陵島、竹島渡海について伝える資料
鬱陵島渡海の経緯を伝える大谷家の文書 No.1 竹島(鬱陵島)渡海由来記抜書控
作成年代不詳*
資料概要
鬱陵島渡海の経緯を書き記した大谷家資料。
大屋(谷)甚吉が越後の帰り、鬱陵島に漂着した際現地を調査し、鬱陵島は朝鮮国から4、50里離れたところにあり、人家はなく、島には商売になる産物品々があることが分かり、渡海することを考えたという話が出てくる。
内容見本
一 於米府大谷家初宅元祖勝宗と号す、会見郡尾高御城主
杦原氏断絶頃者永禄年中米子灘江引越住居、尓時勝宗
甥甚吉越後国より乗船帰帆之砌、与風竹嶋江漂流、甚吉全く
嶋巡り越方等熟思ス、朝鮮国相隔事四五拾里、人家更無之土産
所務之品有之姿、弥渡海之勝手相考、(略)
現代語訳
米子において大谷家が初めに屋敷をかまえた時の元祖は勝宗という。会見郡尾高城主杉原氏が断絶し、米子へ引っ越し屋敷をかまえ住居とした頃は永禄年中であった。ある時、勝宗の甥の甚吉が越後国から船で帰帆しようとしたその節、ふと鬱陵島へ漂流してしまった。甚吉は着岸した鬱陵島をくまなく巡り、色々と熟考した。鬱陵島は朝鮮国から四、五十里隔てられ、そのうえ人家は全くなく、島には商売になる産物品々がある状況から今後渡海することを考えた。
※ 作成年代不詳であるが、大谷文子氏は、大谷九右衛門勝意が文政の頃に書き写したものと考えられるとする。
参考資料: 大谷文子『大谷家古文書』(1984), p.109
| 作成年月日 | - |
|---|---|
| 編著者 | 大谷九右衛門 |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | -(大谷家文書1-3) |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 無 |
| 所蔵機関 | 島根県竹島資料室 |
| 利用方法 | 島根県竹島資料室に問い合わせを行う |