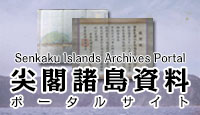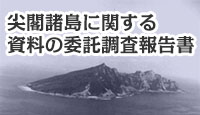本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで
資料集
vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)
①尖閣諸島の所轄
沖縄県の郡編成に関する勅令 No.3 明治29年勅令13号
1896年(明治29年)3月5日
資料概要
沖縄県を島尻、中頭、国頭、宮古、八重山の5郡に画し、各郡に行政上属する地域を定める勅令(1896年(明治29年)3月5日付)。内務省令第2号(※1)によって、同年4月1日に施行された。
1880年(明治13年)以降、沖縄県は那覇、首里、島尻、中頭、国頭、伊平屋、久米島、宮古、八重山の9つの地方に分けられており、各地方に地方役所が設置され、現在の市町村に相当する「間切」が各地方役所の監督下に置かれていた。
この勅令第13号によって、島尻、中頭、国頭、宮古、八重山に郡制が、勅令第19号(※2)によって那覇、首里に区制が敷かれたことで、沖縄県は、2区5郡制となった。2区5郡制以降、各間切は郡役所の監督下に置かれることとなった。
この勅令には、尖閣諸島について明記されていないが、この勅令が公布された直後の『沖縄県統計書』No.4をみても、八重山郡の所属となっていることから、行政上、尖閣諸島が八重山郡に所属することが確定したと考えられる。
なお、1885年(明治18年)の沖縄県による調査以降、尖閣諸島の沖縄県所轄への編入に至る過程では、八重山島役所から所轄編入の伺いが沖縄県に出されており(1889年(明治22年)12月)、また沖縄県は、尖閣諸島を八重山島警察署の仮所轄に編入している(1891年12月)。このように、1885年の沖縄県による調査以降、尖閣諸島は一貫して八重山島の付属島嶼として扱われた。
※1 「内務省令第2号」『官報』(第3806号)1896年3月10日
(国立国会図書館所蔵:デジタルコレクションで閲覧可能)
※2 「沖縄県区制・御名御璽原本・明治二十九年・勅令第十九号」
1896年3月5日公布、同年4月1日施行
(国立公文書館所蔵:デジタルアーカイブで閲覧可能)
内容見本
朕沖縄県ノ郡編制ニ関スル件ヲ裁可シ
茲ニ之ヲ公布セシム
(御名御璽)
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣侯爵伊藤博文
内務大臣芳川顕正
勅令第十三号
第一条 那覇首里両区ノ区域ヲ除ク外
沖縄県ヲ画シテ左ノ五郡トス
島尻郡 島尻各間切久米島慶良間諸
島渡名喜島粟国島伊平屋諸
島鳥島及大東島
中頭郡 中頭各間切
国頭郡 国頭各間切及伊江島
宮古郡 宮古諸島
八重山郡 八重山諸島
第二条 郡ノ境界若クハ名称ヲ変更ス
ルコトヲ要スルトキハ内務大臣之ヲ定ム
附則
第三条 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
| 作成年月日 | 1896(明治29年)年3月5日 |
|---|---|
| 編著者 | 内閣 |
| 発行者 | 内閣 |
| 収録誌 | - |
| 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 国立公文書館 |
| 利用方法 | 国立公文書館で利用手続きを行う (デジタルアーカイブで閲覧する) |