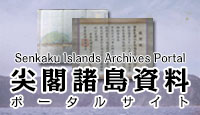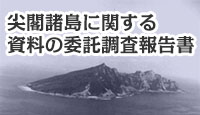本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
南シナ海・東シナ海
コラム 海洋境界画定と国際裁判
河野 真理子 (早稲田大学法学学術院教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
はじめに
日本は、1996年に海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea)に加入し、この条約の下での海域の制度に関して、領海(TS, territorial sea)及び排他的経済水域(EEZ, exclusive economic zone)並びに大陸棚(CS , continental shelf)に関する立法措置をとった1 。また、大陸棚限界委員会(CLCS, Commission on the Limits of the Continental Shelf)の2012年の勧告を受け、200海里を超える大陸棚を日本の大陸棚とする政令の措置がとられた2 。日本の周辺の海域では、北方領土と竹島についての領土主権に関する紛争が解決されておらず、日本の固有の領土たる尖閣諸島については中国と台湾が主権を主張していることもあり、海洋境界についての問題が解決されていない海域が存在する。本稿では、海洋境界画定(MD, maritime delimitation)に関する紛争の解決について国際裁判所が果たしてきた役割を検討することとする。
1. 海洋境界画定(MD)の意味
UNCLOSは、沿岸国がTSに対する主権(第2条)、及びEEZ(第55条、EEZ)並びにCS(第76条)に対する主権的権利及び排他的な管轄権を有するとし、沿岸国の海域に対する権原(entitlement)が認めている。TSの幅員は12海里(第3条)、EEZの幅員は200海里(第57条)と規定されている。沿岸国のEEZに対する主権的権利及び排他的な管轄権は水塊部分だけでなく、海底及びその下にも(第56条)に及ぶ。CSは、200海里という距離と「領土の自然の延長」という2つの要素によって定義されており(第76条1項)、CSについては一定の制限の下で200海里を超える海域への延長が可能であり(同条2~6項)、沿岸国は200海里を超えるCSの限界に関する情報をCLCSに提出し、その勧告後定める国内法により、200海里を超える部分に自国のCSの限界を設定できる(同条7、8項)。
MDとは1つの海域に対して複数の国の権原が重複する場合にその境界を決定することを意味する。UNCLOSの下での沿岸国の権原の大幅な拡大により、向かい合っているか、隣接する複数の国の権原が重複する海域が生ずる場合が多くなった3 。TSのMDに関する第15条は、関係国の特段の合意がない場合、中間線を越えての領海の拡張が認められないとし、距離への明文の言及がある。EEZのMDについては第74条、CSのMDについては第83条で実質的に同じ内容の規定が置かれている。これらについては、当事国の合意による解決が尊重される(1項)ものの、合理的な期間内に紛争が解決されない場合、第15部の紛争解決制度による解決がなされる(2項)。また、同条4項でMDに関する関係国間の効力ある合意の尊重も規定されている。第74条と第83条は、起草過程でMDの基準や方式に関して各国間の合意が得られなかったため、明文の規定ではなく、「衡平な解決の達成」という文言が置かれているのみである。
註1
領海、及び接続水域に関する法律(平成8年法73)、及び排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法74)。
註2
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条第2号の海域を定める政令(2014年)により四国海盆海域、その一部を改正する政令(2024年)により小笠原海台海域を日本の大陸棚とした。なお、小笠原海台海域の一部と南硫黄島海域については米国と協議中(内閣府「大陸棚」、https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/tairikudana/tairikudana.html)。
註3
V. Lowe and A. Sander, The Law of the Sea, Fourth Ed. (2022), pp. 300-302, and Y. Tanaka, International Law of the Sea, Fourth ed. (2023), p. 258.
2. MDに関する紛争と国際裁判
(1) UNCLOS第15部の紛争解決制度
(ⅰ) 第15部の紛争解決制度の利用の要件
UNCLOSの紛争解決制度では、第15部第2節の拘束力を持つ決定を伴う義務的国際裁判制度が重要な特色である。第286条はこの制度への紛争付託の3つの要件を規定している。第1に、UNCLOSの解釈又は適用に関する紛争が存在すること、第2に、第1節に両当事者の選択する紛争解決手続により紛争が解決されなかったこと、第3に、第3節に規定される制限及び適用除外が適用され紛争にあたらないことである4 。
第287条1項の下、条約当事国は、(a)国際海洋法裁判所(ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea)、(b)国際司法裁判所(ICJ, International Court of Justice)、(c)附属書VIIの下で組織される仲裁裁判所、(d)附属書VIIIの下で組織される特別仲裁裁判所の1つ以上を選択する宣言ができる。紛争の両当事国の選択が一致する場合は、特段の合意がない限り、その裁判手続にのみ紛争が付託される。紛争当事国の宣言が有効でない場合、紛争の当事国が選択している裁判所が一致しない場合、又はいずれか若しくは両方の紛争当事国が宣言をしていない場合は、附属書VIIの下で組織される仲裁裁判所が義務的管轄権を有する(第287条3、4、5項) 5 。
(ⅱ) UNCLOSの解釈又は適用に関する紛争の存在(第1の要件)
「条約の解釈又は適用に関する紛争」とは、条約の特定の規定の解釈又は適用について当事国間で事実又は法について意見の相違があることである。MDそれ自体に関する紛争は、第15条、第74条、又は第83条の解釈又は適用に関する具体的な紛争であり、第286条の第1の要件を満たしうる。ただし、MDに関する紛争は背景に領土紛争がある混合紛争(mixed dispute)である場合が少なくない。混合紛争に対する管轄権の判断では、領域紛争と海洋紛争を切り離すアプローチ(南シナ海事件6 )と、真の紛争主題がUNCLOSの解釈又は適用に関するものであり、付随してマイナーな領域紛争が存在する場合であれば管轄権の行使が排除されないとする立場(チャゴス海洋保護区事件7 及びケルチ海峡等事件8 )がみられる9 。
(ⅲ) 当事者が選択する紛争解決手段による紛争解決の尊重(第2の要件)
第286条の第2の要件では、紛争当事国が選択する紛争解決手段の選択の自由の尊重が保障されている(第281条、第282条)。また、第2節の義務的裁判手続への紛争の付託前に、紛争当事国間での紛争解決手段に関する意見の交換が必要である(第283条)10 。みなみまぐろ事件では、第281条の末文について、紛争当事国間の条約にUNCLOSの義務的裁判手続の排除に関する明文の規定がなくとも、関連規定によりその意図が認められれば、これが排除されるとの趣旨であると判断された11 が、南シナ海事件では、UNCLOSの義務的裁判手続を排除する旨の明文の規定がなければ、これは排除されないとの判断が示された12 。学説は南シナ海事件の判断の立場を支持するものが多数説である13 。
(ⅳ) 制限及び選択的適用除外の対象ではないこと(第3の要件)
第3の要件は、第3節の下での制限(第297条)及び選択的適用除外(第298条)の対象となる紛争にあたらないことである。UNCLOSでは条約の一体性の確保のため、留保及び除外が認められていない(第309条)ことから、第2節の義務的紛争解決手続のゆえにこの条約の締約国とならない国がありうることへの懸念があり、第3節が設けられた。第297条はすべての締約国に、第298条はこの規定に基づく宣言を行った締約国にのみ適用される。MDに関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争は選択的適用除外の対象の1つで、これを除外する宣言を行う場合、附属書V第2部の義務的調停を受け入れることになる(第298条1項(a)(i))14 。
(2) UNCLOS第15部の紛争解決制度とICJ
UNCLOSの発効後、ICJは、規程第36条に基づく管轄権と、第15部第2節の義務的裁判制度の選択肢の1つとしての管轄権という2つの機能を持つことになった。規程第36条2項に基づく強制管轄受諾宣言をしている国家間の紛争の場合、原告は2つの義務的裁判制度のいずれかを選択できる。日本は2015年の強制管轄受諾宣言で、「海洋生物資源の調査、保存、管理又は開発について、これらから生ずる、これらに関する又はこれらに関係のある紛争」に関する留保を追加し、この紛争についてUNCLOS第15部の義務的紛争解決手続への付託に限定するとの意思を示した。なお、規程第36条に基づく紛争付託の場合、ICJは領土紛争とMDに関する紛争の両方について管轄権を有し、UNCLOS第15部第2節に基づく義務的裁判制度における混合紛争の問題は生じない15 。
註4
T. Treves, “Article 286,” in A. Proelss (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary (2017), pp. 1844-1849, N. Klein, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea (2005), pp. 31-52.
註5
T. Treves, “Article 287,” in Proelss, supra note 4, pp. 1849-1857.
註6
South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award of 2015, para. 157, 170, and 204.
註7
Chagos Marine Protected Area (Mauritius v. United Kingdom), Award of 18 March 2015, paras. 220-221.
註8
Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russia) Award of 21 February 2020, paras. 157-161.
註9
田中嘉文「仲裁-チャゴス諸島海洋保護区事件」森川幸一他編『国際法判例百選』第3版(2021年)、181頁、T. Treves, supra note 4, pp. 1847-1848, B. Oxman, “Courts and Tribunals: The ICJ, ITLOS, and Arbitral Tribunals,” in D. Rothwell et al. (eds.), The Oxford Handbook of the Law of the Sea (2016), p. 400, K. Kittichaisaree, The International Tribunal for the Law of the Sea (2021), pp. 94-99。
註10
A. Serdy, “Article 281,” “Article 282,” and “Article 283,” in Proelss, supra note 4, pp. 1820-1838.
註11
Southern Bluefin Tuna Arbitration (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), 4 August 2000, para. 57.
註12
South China Sea, supra note 6, para. 223.
註13
T. Treves, supra note 4, pp. 1848-1849.
註14
Ibid., pp. 1848, Oxman, supra note 9, pp. 403-408, A. Serdy, “Article 297,” and “Article 298,” in Proelss, supra note 4, pp. 1906-1932, Klein, supra note 4, pp. 125-315(特に、海洋境界画定又は歴史的権原については、pp. 228-279)。
註15
ICJが領土紛争とMDに関する紛争についての判断を示した先例は以下の通り、Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Judgment of 11 September 1992, I. C. J. Reports 1992, p. 351, Land and Maritime Boundary between A and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2002, p. 303, Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment, I. C. J. Reports 2007, p. 659, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I. C. J. Reports 2012, p. 624, and Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 139.なお、エルサルバドル/ホンジュラス事件では、MDではなく問題の海域の法的事情(legal situation of the maritime spaces)についての判断が要請された(El Salvador/Honduras, in this note, pp. 586-609, paras. 381-420, and pp. 616-617, para. 432 (1))。
3. 国際裁判所の先例を通じたMDに関する国際法規則の発展及び明確化
MDに関する多くの国際裁判の先例から、特にEEZとCSのMDにおいて、UNCLOS第74条1項と第83条1項の下での「衡平な解決の達成」のための国際法規則や方式に関して一定の定式化がみられるようになっている。
(1) 初期のMDに関する紛争
CSのMDに関連する最初の先例であるICJの北海大陸棚事件の1969年判決は、ジュネーヴ大陸棚条約第6条が慣習国際法となっていないこと16 や、CSのMDの際の方式や考慮要因の詳細な議論17 等についての判断を示し、UNCLOS第74条と第83条の起草過程の議論に大きな影響を与えた。また、「陸は海を支配する」18 との判断はその後の国際裁判で常に引用されている19 。
チュニジア/リビア事件とリビア/マルタ事件では、UNCLOSの起草及び採択と同時期にCSのMDに関する紛争がICJに付託された20 。特に後者でICJは、UNCLOSの採択後の1985年に判決が出され、UNCLOSの規定への言及がなされた。ICJは、UNCLOSのEEZの制度が慣習国際法となっていることを認め、本件でICJは、CSのMDのみが要請されていることを確認しつつも、EEZとCSいう2つの異なるが相互に関連する2つの制度における権原の共通要素としての距離がより重要な意味を持つとした。また、距離に基づくEEZの制度が慣習国際法上のものとなっていることも認めている21 。
(2) 単一海洋境界線(SMB, single maritime boundary)
UNCLOSに基づくMDに関する国際裁判の先例では、SMBに関する判断が要請される事例が増加したことも、距離という基準の重要性が増した別の要因である。UNCLOSではEEZ(第5部)とCS(第6部)は別の制度であり、理論的には個別のMDが可能である。しかし、EEZとCSの境界線が異なることは海域の利用の観点から実際的ではない。紛争当事国がSMBの決定を国際裁判所に要請する事例が増えるとともに、EEZとCSに共通する要素としての「距離」の重要性が増したと考えられる22 。
SMBに関する初期の事例では、両当事者の合意によりSMBの決定が要請された23 。ヤン・マイエン事件ではCSと漁業水域という2つの水域のMDにつき、SMBによるか否かで当事国の見解が異なったため24 、ICJはこれらのMDを個別に検討したが、最終的にその線が一致した25 。なお、ICJはこの文脈で、リビア/マルタ事件でEEZとCSの共通要素としての距離が重視されたことに言及している26。
カタール対バーレーン事件でICJは、両紛争当事国がSMBによるMDを要請しているとし、TS、EEZ、CSのSMBを判断した。本件では地理的特性のため、ICJは南部のTSと、北部のEEZとCSのMDを区別して判断した。ICJは、SMBは多数国間条約の規定によって求められているものではなく、国家慣行から生じる者であり、単一のMB制度を確保したいという当事国の希望によるものであると指摘している27。
これ以降、一方的付託の事例で、原告のEEZとCSに共通するSMBの決定の要請に被告が反対しない事例が増加した28 。なお、TSのMDが含まれる事例では、TSのMDとEEZとCSのMDとを区別した検討がなされている29 。国際裁判所は、第15条に基づくTSのMDと第74条と第83条に基づくEEZとCSのMDの違いを考慮していると考えられる30 。
(3) MDの方法
MDの方法は多様とされる31 が、国際裁判の先例では、海岸の一般的方向から境界を画定するアングル・バイセクター方式(A/B方式)と、暫定的な等距離線又は中間線を関連事情により調整する方式(E/RC方式)のいずれかが選択されている32 。初期の事例では、ギニア/ギニア・ビサウ間の海洋境界画定事件とメイン湾事件でA/B方式が採用された33 が、その後は、海岸線が特定できないという特殊な事情のゆえにICJがA/B方式を採用したニカラグア対ホンジュラス事件34 以外のすべての先例で、「衡平な結果の達成」のための方式としてE/RC方式が採用されている35 。一方の当事者がA/B方式の採用を主張した事例でも、そのような主張は認められなかった36 。
註16
North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 45, para. 81.
註17
Ibid., pp. 46-53, paras. 83-100.
註18
Ibid., p. 51, para. 96.
註19
例えば、ICJがMDの方式を定式化したMaritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I. C. J. Reports 2009, p. 89, paras. 77。
註20
Continental Shelf (Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, 1. C. J. Reports 1982, p. 18, and Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I. C. J. Reports 1985, p. 3.
註21
Ibid., p. 33, para. 33-34.
註22
M. Kawano, “International Courts and Tribunals and the Development of the Rules and Methods Concerning Maritime Delimitation,” The Journal of International Law and Diplomacy, Vol. 112, No. 3 (2013), pp. 9-13.
註23
Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau Sentence du 14 février 1985, Reports of International Arbitral Awards, Vol. 19, p. 166, para. 42, and Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française Décision du 10 juin 1992, Reports of International Arbitral Awards, Vol. 21, p. 1152, para. 1.
註24
Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I. C. J. Reports 1993, pp. 56-58, paras. 41-44.
註25
Ibid., pp. 59-77, paras. 49-87.
註26
Ibid., p. 59, para. 46.
註27
Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, 1. C. J. Reports 2001, pp. 91-94, para. 168-177, particularly para. 173.
註28
Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 440-441, para. 286.コスタリカ対ニカラグア事件では、ICJは、TSの境界とEEZ及びCSのSMBを区別した(Costa Rica v. Nicaragua), supra note 15, p. 171, para. 79. UNCLOS第15部の手続の下での仲裁の事例として、Barbados/Trinidad and Tobago, Award of the Arbitral Tribunal, 11 April 2006, pp. 71-72, paras. 234-335 and Guyana/Suriname, Award of the Arbitral Tribunal, 17 September 2007, p. 108, para. 334がある。
註29
Nicaragua v. Honduras, supra note 15, pp. 738-745, paras. 262-282, Black Sea, supra note 19, p. 70, para. 17, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar, Judgment, 14 March 2012, paras. 177-181, Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (The People’s Republic of Bangladesh and The Republic of India), Award, 7 July 2014, paras 178-181.ニカラグア対コロンビア事件では、ニカラグアは請求訴状段階ではSMBの判断を要請したが、抗弁書でこれを修正し、最終申立ではコロンビアの島に基づく権原戸ニカラグアのCSとEEZの境界画定についての判断を要請するとした(Nicaragua v. Colombia, supra note 15, pp. 670-671, paras. 133-136)。
註30
Nicaragua v. Honduras, supra note 15, pp. 742-745, paras. 277-282, Bangladesh v. Myanmar supra note 29, para. 150, and Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Judgment, I. C. J. Reports 2021, pp. 248-249, para. 120.クラインの著書でも、TSのMDとEEZ及びCSのMDは区別した記述となっている(Klein, supra note 4, pp. 241-248)。
註31
北海大陸棚事件の判決でICJは、E/RC方式が実務的であることを認めつつ、他にも多様な方式があり、E/RC方式のみが国際法の規則によって求められているわけではないと指摘した(North Sea Continental Shelf, supra note 16, p. 23, para. 23, p. 34, paras. 51-52, pp. 35-36, para. 55, p. 45-46, para. 82, p. 47, para. 85, and p. 49, para. 90)。
註32
サンピエール・ミケロン事件で仲裁裁判所は、衡平な解決の重要性を強調し、関連する海域の地理的特性を詳細に検討する立場をとった(St. Pierre and Miquelon, supra note 23, pp. 1169-1171, paras. 66-74)。
註33
Guinea/Guinea-Bissau, supra note 23, pp. 181-194, paras. 86-125.
註34
Nicaragua v. Honduras, supra note 15, pp. 242-244, paras. 277-280, and pp. 745-749, paras. 283-298.
註35
第4章第2節を参照。
註36
Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 238-240, Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 340-346, and Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte D’Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte D’Ivoire), Judgment, 23 September 2017, paras. 289-325.