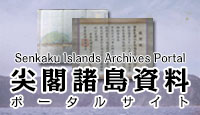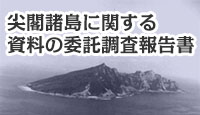本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
南シナ海・東シナ海
4. 国際裁判所の先例を通じたMDに関する国際法の発展
(1) MDに関する合意
UNCLOS第74条1項と第83条1項では当事国間の合意による解決の尊重が規定されている。そのような合意の存在は国際裁判の先例の一部でも論点となった。カメルーン対ナイジェリア事件、ルーマニア対ウクライナ事件、ペルー対チリ事件でICJは、海岸から一定の距離までのMDにつき当事国間の合意の存在を認めた37。他方、ニカラグア対ホンジュラス事件、バングラデシュ対ミャンマー事件、及びガーナ/コートジボアール事件では合意の存在は認められなかった38。
(2) E/RC方式における3段階の検討
「衡平な結果の達成」のためにE/RE方式が採用された先例の蓄積は、この方式の用い方に一定の定式化をもたらした。特に黒海事件のICJ判決は大きな役割を果たした。本件でICJは、先例を総括し、E/RC方式が一般的なMDの手法であるとしたうえで、この方式では、第1段階の暫定的な等距離線又は中間線の決定、第2段階の関連事情の検討に基づく暫定的な等距離線又は中間線の調整、第3段階の衡平な結果の達成の検証という3段階の検討が必要であると述べた39。なお、E/RC方式では、第1段階に先立ち、等距離線又は中間線の決定の基礎となり、関連事情の考慮の際にも検討の対象とされうる各当事国の海岸線と、MDの対象となる海域が特定される40。
第2段階で考慮されるべき関連事情としては、両当事国の海岸線の長さの違い41及び海岸の地形や沿岸国の海洋へのアクセスの阻害効果(cut-off effect)等のような地理的要因42が重視される傾向がある。紛争当事国が、関連事情として、資源の賦存の位置、資源の利用やパトロール等の沿岸国の権限の行使の内容等をあげた先例は多いが、その主張が認められた先例は多くない43。ガーナ/コートジボアール事件で、ITLOSの特別裁判部は、石油コンセッション及び石油に関連する活動が暫定的な海洋境界線を調整する関連事情戸して認められにくいということについて国際裁判所の先例は一貫した立場を示してきていると指摘している44。
註37
Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 441-442, para. 287-289, Black Sea, supra note 19, pp. 82-89, paras. 55-76, and Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, pp. 57-58, paras. 149-151.
註38
Nicaragua v. Honduras, supra note 15, p 737, para. 258, Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 98 and 118, and Ghana/Côte D’Ivoire, supra note 37, para. 228..
註39
Black Sea, supra note 19, pp. 101-103, paras. 115-122.その後の以下の事例では黒海事件への明文の言及がある: Nicaragua v. Colombia, supra note 15, pp. 695-696, paras. 190-193, Peru v. Chile, supra note 38, p. 65, para. 180, Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 336-346, Ghana/Côte D’Ivoire, supra note 37, paras. 360, Costa Rica v. Nicaragua, supra note 15, pp. 190-203, paras. 135-166 and pp. 176-224, paras. 208-204, and Delimitation of teh Maritime Boundary between Mauritius and Maldives in the Indian Ocean (Mauritius/Maldives), Judgment, 28 April 2023, paras. 95-98。
註40
Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 443-444, para. 291, Black Sea, supra note 19, p. 93, para. 88, pp. 96-98, paras. 98-105, and pp. 99-100, paras. 110-114, Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 185-205, Nicaragua v. Colombia, supra note 15, pp. 675-686, paras. 143-166, Somalia v. Kenya, supra note 30, pp. 252-257, paras. 132-141, Costa Rica v. Nicaragua, supra note 15, pp. 181-187, paras. 108-122 and pp. 210-214, paras. 179-185, Ghana/Côte D’Ivoire, supra note 37, paras. 361-386, and Mauritius/Maldives, supra note 40, paras. 108-111.
註41
Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 446-447, para. 301, Black Sea, supra note 19, pp. 116-118, paras. 163-168, and Nicaragua v. Colombia, supra note 15, p. 702, paras. 209-211.
註42
Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 442-443, para. 291, Black Sea, supra note 19, pp. 119-120, paras. 174-178, pp. 122-123, paras. 185-188, and p. 127, para. 201, Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 290-297, 316-319, 322, and, Nicaragua v. Colombia, supra note 15, pp. 703-704, paras. 214-216, Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 399-421, and 437, Somalia v. Kenya, supra note 30, pp. 264-270, paras. 161-174, Costa Rica v. Nicaragua, supra note 15, pp. 196-198, paras. 153-158, and pp. 218-221, paras. 192-201, Ghana/Côte D’Ivoire, supra note 37, paras. 421-426 and paras. 434-436, and Mauritius/Maldives, supra note 40, paras. 243-247.
註43
2000年以降の国際裁判の先例では沿岸国の活動が関連事情として考慮された先例は少ない。ニカラグア対コロンビア事件でICJは、両当事者の活動(漁業活動の規制、科学的探査活動及び海軍によるパトロール)、安全保障と法執行に関する配慮、及び天然資源への衡平なアクセスについての主張のうち、安全保障と法執行に関する配慮のみに留意するとした(Nicaragua v. Colombia, supra note 15, pp. 704-706, paras. 217-223)。これ以外の事例では、石油資源や漁業等は関連事情として認められていない(Cameroon v. Nigeria, supra note 15, pp. 442-443, para. 291, and pp. 447-448, para. 304, Qatar v. Bahrain, supra note 27, 109-110, paras. 222-223, pp. 112-113, paras. 236, and pp. 114-115, paras. 247-249, Black Sea, supra note 19, p. 125-126, para 197-198, and p. 128, para. 204, Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 422-424, Ghana/ Côte D’Ivoire, supra note 37, paras. 450-455, and paras. 467-479, and Somalia v. Kenya, supra note 30, pp. 262- 264, paras. 154-160)。
註44
Ibid., para. 476.
5. 200海里を超えるCSのMD
(1) UNCLOS第76条に基づくCSの延長の制度
UNCLOS第76条の下で200海里を超えるCSの限界についての情報がCLCSに提出される際、他国が異なる見解を申し立てる場合がある。このような場合、科学者によって構成されるCLCSはUNCLOSの解釈や適用に関する問題を判断する権限を有しておらず、勧告が先送りされることになる。例えば、日本のCSの限界についての情報の提出に関しては、中国と韓国がそれぞれの立場に関する口上書を提出したため、2012年のCLCSの勧告では、関係する海域についての勧告が先送りされた45。
(2) 国際裁判における200海里を超えるCSのMD
200海里を超えるCSについても複数の沿岸国の権原が重複する場合、MDが必要である。ICJは200海里を超えるCSのMDの要請を受けた事例ではこの要請には積極的には応えておらず46、ITLOSのバングラデシュ対ミャンマー事件が200海里を超えるCSのMDの最初の事例となった。本件はCLCSの勧告の前の判決であったが、ITLOSは権原の決定と大陸棚の限界の決定は異なるとし、200海里を超えるCSについて複数の国の権原が重複する場合、MDについての判断が可能であり、本件では200海里を超えるCSに対する沿岸国の権原の問題は主として法的な性質であると判断した上で、両当事国の権原の存在とその重複を認めた47。そしてMDについて、E/RC方式による判断を示した48。
バングラデシュ対インド事件でもE/RC方式による判断が示された49。ソマリア対ケニア事件とガーナ/コートジボアール事件では、ICJとITLOSの特別裁判部はそれぞれ、200海里を超える大陸棚の境界線について、EEZとCSのSMBの延長線であると判断するとともに、その限界はCLCSの勧告によるものとした50。200海里を超えるCSのMDについても国際裁判所は距離という基準を重視し、E/RC方式を採用する傾向がある。
モーリシャス/モルディブ事件では、モーリシャスが200海里を超えるCSのMDについての判断をITLOSの特別裁判部に要請した。本件の判決の以下の2つの点についての判断は特に注目される。第1に、モルディブの200海里を超える大陸棚に対する権原とモーリシャスの200海里以内の大陸棚に対する権原との重複に関するMDの扱いである。特別裁判部は、200海里以内のEEZとCSのMDに関する判断により、一方の国の200海里を超えるCSと他方の国の200海里以内のCSの権原との重複の問題は訴訟目的を欠く(moot)ものとなると判断した51。なお、200海里を超える大陸棚の境界画定に関するニカラグア対コロンビア事件でICJは、慣習国際法上、国家は200海里を超えるCSに対する権原を他国の200海里内のEEZに対して主張することができないと判断した52。
第2に、本件では特別裁判部は両国の200海里を超えるCSに対する権原のうち、モーリシャスの権原に「重大な不確実性(significant uncertainty)」があるため、MDを判断する立場にないと判断した53。特別裁判部は、「重大な不確実性」という基準は、200海里を超えるCS に対する権原に関し、特別裁判部の判決とその後のCLCSの勧告の内容が異なる危険性を最小限にするために適用されると述べた54。また、200海里を超えるCSのMDに関する判断によって他の沿岸国の権利が影響を受ける場合、国際裁判所は判断を差し控えなければならないこと、及び、「重大な不確実性」という基準の適用は人類共通の財産である深海底における国際共同体の利益のためでもあり、本件のように深海底に関する国際共同体の利益が影響を受ける危険性がある場合には、注意すること(exercise of caution)が必要であるとの指摘もなされた55。
200海里を超えるCSのMDに関する先例の主要な論点から、CLCSが勧告を出す前の段階では国際裁判所が判断をすることには限界があるということができるだろう。
(3) グレー海域
バングラデシュ対ミャンマー事件では、200海里を超えるCSの境界の判断において、バングラデシュの200海里を超える大陸棚の一部がミャンマーのEEZと重複する海域をグレー海域とし、この部分の海域のMDは両国がUNCLOSの関連規定に従って相互にdue regardを払って権利を行使し、義務を果たすべきであり、合意に解決や協力のための取極を設けることも可能であるとした56。バングラデシュ対インド事件でも同様の判断が示された57。200海里を超える海域の限界に関する判断が示されなかったソマリア対ケニア事件でも、これが決まればグレー海域が生じる可能性があることが指摘されている58。
註45
Commission on the Limits of the Continental Shelf, Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission Made by Japan on 12 November 2008, 19 April 2012.
註46
Kawano, supra note 22, p. 24.
註47
Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 397-449.
註48
Ibid., paras. 461-462.
註49
Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 456-497.
註50
Somalia v. Kenya, supra note 30, pp. 276-277, paras. 194-196, and Ghana/Côte D’Ivoire, supra note 37, para. 527.
註51
Mauritius/Maldives, supra note 40, paras 274-275.
註52
Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), Judgment 13 July 2023, paras. 69-79.
註53
Mauritius/Maldives, supra note 40, paras. 434-451 and para. 466(4).
註54
Ibid., para. 433.
註55
Ibid., paras. 452- 453.
註56
Bangladesh v. Myanmar, supra note 29, paras. 463-464, and 471-476.
註57
Bangladesh v. India, supra note 29, paras. 503-508.
註58
Somalia v. Kenya, supra note 30, para. 197.
おわりに
海洋境界画定に関する紛争が国際裁判に付託された事例を検討した結果、UNCLOSの採択以降、TS,EEZ,CSの海洋境界画定については、SMBという実際的な手法が求められる場合が多く、よほどの例外的な事情がない限りは、200海里を超えるCSのMDも含め、E/RC方式によるMDの手法が定着してきていると考えられる。また、海岸線の長さや形状といった地理的な要素が関連事情として考慮される事例が多く、資源の利用に係る経済活動や法執行活動のような要素が考慮された事例は多いとはいえない。こうした地理的な要素は裁判所の判断により客観性をもたらすと考えられる。両当事者に衡平な結果を国際法に基づいて判断するという機能を期待される国際裁判所は、関連事情においても客観的に判断できる要素を重視してきているといってよいだろう。