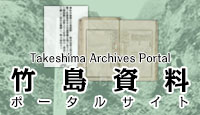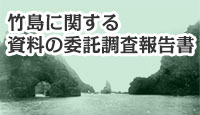本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
資料集
vol.3 江戸期の竹島の利用
①大谷家、村川家の鬱陵島、竹島渡海について伝える資料
幕府が大谷家、村川家の鬱陵島への渡海を許可する通達 No.2 竹島(鬱陵島)渡海御免の達書(写)
1618年(元和4年)5月16日
資料概要
江戸幕府が、鳥取藩主に対して、大谷家、村川家の鬱陵島への渡海許可を通達した奉書(※1)である。
米子で廻船業を営んでいた大谷甚吉は、1617年(元和3年)、越後から帰帆の途中に遭難し、鬱陵島に漂着した。大谷は、鬱陵島が無人島で、森林資源や海産物が豊富なことを確認し、竹島への渡航を決意する(→No.1)。そして、同じく米子の町人である村川市兵衛とともに、その頃国替えの監使として米子にあった旗本阿倍(部)四郎五郎に竹島渡海を注進した。
阿倍四郎五郎は、大谷、村川を伴って江戸に戻り幕府に取り次いだ。幕府は、両家の鬱陵島への渡航に異議がなく、それを許可することを伝える奉書を鳥取藩主(松平新太郎)に送った。
大谷、村川両家は、この奉書の写しを所持し(※2)、毎年交互に鬱陵島に渡海し事業を営んだ。
なお、この頃、鬱陵島は「竹島」と呼ばれており、奉書には「竹島」への渡海を許可するとある。
※1 奉書は将軍家の命を老中が奉じて連署で下達する文書であり、一般には書状様式である。つまり折紙であるが将軍家の命を大名に伝える場合に用いる。(『日本古文書学講座』6近世編Ⅰ pp.101-102)
※2 1637年(寛永14年)に村川家の船が、1666年(寛文6)年には大谷家の船が朝鮮に漂着した。両方とも許可証の写しを所持していたことが、対馬藩宗家の記録や鳥取藩の記録に残っている。
内容見本
從伯耆國米子竹嶋江
先年舟相渡之由候、
然者如其今度致渡
海度候段、米子町人
村川市兵衛大屋甚吉
申上候付而達 上聞候
之處、不可有異議候
旨被 仰出候之間、
被得其意渡海之儀
可被仰付候、恐々謹言
永井信濃守
五月十六日 尚政 在判
井上主計頭
正就 同
土井大炊頭
利勝 在判
酒井雅楽頭
忠世 同
松平新太郎殿
人々御中
現代語訳
伯耆国米子から竹嶋へ先年船を渡したとのこと。そうであればそのように、このたび渡海いたしたいと米子の町人村川市兵衛大屋甚吉が申し上げていることにつき上様にお諮りしたところ、異議無い旨仰せ出でられたので、御意向に沿い[両名に渡海を]仰せ付けられるように。恐々謹言
| 作成年月日 | 1618年(元和4年)5月16日 ※1625年の説もある |
|---|---|
| 編著者 | - |
| 発行者 | - |
| 収録誌 | - | 言語 | 日本語 |
| 媒体種別 | 紙 |
| 公開有無 | 有 |
| 所蔵機関 | 米子市立山陰歴史館 |
| 利用方法 | 米子市立山陰歴史館で利用手続きを行う |