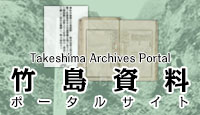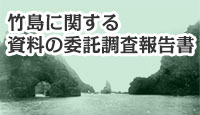本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
3.駐日ニュージーランド大使館作成の文書
1954年5月3日、巡視船5隻が警戒する中で、隠岐の久見漁業組合員は島根県漁業取締船「島風」に乗船して竹島で採介藻を行い、漁業権を行使した。同月27日には「島根丸」が、同月30日には鳥取県水産試験場試験船「だいせん」が竹島に接近した。これらに刺激されたのか、同年6月11日に韓国政府は海洋警察隊を竹島に急派し、9月2日には警察の常駐を決定した16。同年8月27日、日本政府は竹島での灯台設置に抗議した。同年には、8月23日に巡視船への銃撃事件、11月21日にも巡視船への砲撃事件がおきている。この年、日本政府は2月10日に、韓国政府は9月25日に竹島領有根拠を記した見解を相手に送付した。前年の一回目と同様、二回目の見解交換も日本政府の主張に韓国政府が反駁する形で行われた。また、同年9月25日に日本政府は竹島問題の国際司法裁判所への付託を提起し、韓国政府は同年10月28日にそれを拒否した。
1955年も日韓間の緊張は続いた。1953年9月に深刻化した東シナ海での韓国の日本漁船拿捕は収まらなかった。前年1954年の7月から、李承晩ライン侵犯を口実に拿捕した日本漁船の船員を、韓国政府は漁業資源保護法が定めた刑期を終えても帰国を許さなくなっていた。日本人船員たちは貧弱な食事と不自由な生活に苦しみながら、釜山の外国人収容所で抑留生活に耐えた。日本政府は交渉による諸懸案の解決を求めたが、同年8月17日に韓国政府は韓国人の日本往来の禁止、対日貿易の全面停止を発表した。同年11月17日には韓国連合参謀本部は日本漁船への砲撃声明を発表した。日本の漁業関係者はこの声明に抗議して各地で集会を行い、政府に対策を求めた。
ニュージーランド(以下「NZ」と略記)の国立公文書館に1955年10月31日という手書きの日付が記された、駐日 NZ 大使館が作成したと考えられる、JAPANESE - KOREAN RELATIONSと題した6頁の文書がある17。上記の日韓間の対立激化に対応して作成されたのであろう。その(3)竹島問題(The Takeshima Question)の部分の全文訳は次の通りである。
韓国政府が、疑いもなく日本領である竹島への領土要求をしはじめてからすでに三年以上経過した。この間、日本政府は、韓国側から行われた竹島への侵入のような違法行為が発見されるたびに強く抗議してきた。また、竹島は歴史的また国際法的見地から明らかに日本の領土であることを韓国に示してきた。
韓国側は反駁の書簡を送り返した。しかし、それは日本政府の主張の正当性を揺るがすことのできるものを何ら持っていなかった。
昨年7(ママ)月に韓国政府は、実力によって竹島を支配し警備隊を島上に駐屯させるほど大胆になった。彼らは灯台を建設し電信用の柱を立てた。現地調査のために来島した日本の巡視船に発砲したのに加え、韓国政府はまた、竹島を絵柄にした切手を発行した。国内外に竹島に対する領有主張を宣伝するためであった。
日本政府はこのような不法で不正な行動に抜かりなく抗議してきた。しかし、紛争の平和的で最終的な解決のため、日本政府は竹島問題を国際司法裁判所に提起することを決定した。1954年9月25日、日本はこの提案を行い、韓国政府に合意を求めた。しかし、この提案は10月28日に拒否された。国際的な司法の場で自らの立場を明らかにして公正な判断を仰ぐこの機会を韓国政府が避けたことは、大変遺憾なことである。
それ以来、韓国政府は実力によって竹島を占拠するという態度を変えていない。もちろん、日本政府はこれに抗議するであろう。しかし、問題の平和的解決のためできることを最大限行うというのが日本の意図である。
日本の竹島領有主張の正当性を前提とした文章である。そして、竹島問題の平和的解決をめざす日本政府の方針を評価し、それを拒否する韓国政府を批判している。とりわけ、竹島の領有根拠を記した韓国政府見解について、「日本政府の主張の正当性を揺るがすことのできるものを何ら持っていなかった(It did not contain anything that could shake the validity of the Japanese Government’s assertion)」と、韓国の主張を全否定していることが注目される。
日韓両国政府間の見解の交換での重要な論点は、1905年の島根県の竹島編入前に朝鮮半島にあった政府が竹島を統治していた証拠があるか否かであった。竹島は日本の統治開始時に日本領であったという日本政府第一回見解の主張に反論するため、韓国政府は第一回見解と第二回見解18で1905年の島根県編入が侵略であったと強調した。その根拠は、(a)1906年の欝島郡主沈興澤の報告、(b)1904年に竹島の貸下げ願を政府に提出した中井養三郎が竹島を朝鮮領と思っていたこと、(c)樋畑雪湖「日本海における竹島の日鮮関係に就いて」(『歴史地理』55-6 日本歴史地理学会 1930年6月)の記述、(d)水路部編刊『朝鮮沿岸水路誌 第1巻』(1933年1月)では「朝鮮東岸」の項に竹島の説明があること、(e)同書にある鬱陵島民の竹島での活動の記録であった。
これらはすべて、朝鮮半島にあった政府が竹島を統治していた証拠ではなかった。日本政府は第二回見解で逐一反論し、1956年の第三回見解19で「韓国側では、竹島に対する韓国としての有効的経営の証拠を積極的に提示しえないため、日本側の文献を引用し、竹島が、島根県編入の前後において韓国領土の一部であったかの如くに主張しようとつとめているが、右はその直接的証拠とはなりえないのみならず、これらの文献の引用は、自己に都合よく恣意的解釈を下したもの、又は現在の竹島と欝陵島とを混同したものであって、なんら傍証とするにも値しない」と韓国政府の主張を全否定した。韓国政府の見解を読んだNZ 大使館の担当者も、同様の評価をしたに違いない。
なお、NZ 大使館の担当者が「疑いもなく日本領である竹島」と断定したのは、NZ政府外務省が1953年12月2日付で作成した調書「日韓関係特に竹島をめぐる紛争に関連して」(本サイトに2022年10月11日掲載の拙稿「平和条約と竹島‐英連邦諸国の対応を中心に‐」参照)が理由とも考えられる。同年12月7日付でNZ外務省が駐日大使館に送付したこの調書には、1951年7月に韓国政府が豪州政府に対して、竹島を韓国領とするよう平和条約草案を修正する要求への支持を求めたことが記録されている。しかし「韓国が望んだ意味での第2条a項の修正は行われることなく、平和条約は最終的に調印された」と、平和条約で竹島が日本領に残った事実を明確に記していた。
註16
外務部編刊『外務行政の十年』(1959年5月)513頁、國史編纂委員会編刊『大韓民國史年表 上』(1984年10月)295・303頁。
註17
Individual Countries - Japan - External Relations – Korea (ANZ, Item Code: R22230074)。この文書は日本国際問題研究所の出張依頼により調査を行ったニュージーランド国立公文書館で筆者(藤井)が発掘した。拙稿「竹島問題に関するニュージーランド政府外務省の調書について」(公益財団法人日本国際問題研究所のウェブページに2023年7月24日に掲載)参照。
註18
二つの見解は韓国政府外務部編『獨島關係資料集(Ⅰ)-往復外交文書(1952~76)-』(1977年7月)に収録されている。
註19
前掲註(18)の資料集に収録されている。
おわりに
以上検討した米、英、NZ三国の駐日各国大使館の竹島問題への認識はすべて、平和条約で竹島は日本領に残されたということであった。もちろん、在外公館から本国に宛てた報告はあくまでも報告であってそこに書かれていることは必ずしも本国政府の見解というべきものではない。また、シーボルドが「おそらく、これは総司令部や連合国と関係なしに、日韓間の交渉の議題とすることが適切だろう」と最後に述べているように、他国の領土問題への介入によって利益を得ることはないことは一般的なことであり、竹島が日本領であるという認識を持っていても、韓国の竹島不法占拠をやめさせる行動には必ずしもつながらない。
そうであっても、シーボルドは平和条約の文言から、英国とNZの大使館は日韓両国政府の主張を検討した上でそのような認識に至ったと考えられる。竹島問題について日韓両国以外から客観的な判断が下された点に、これらの文書の価値がある。