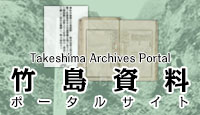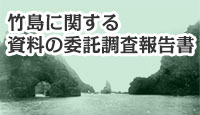本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
コラム 駐日各国大使館の竹島問題への認識
藤井 賢二 (島根県竹島問題研究顧問)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
はじめに
「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約、以下「平和条約」と略記)によって竹島の日本保持が決定したことは、塚本孝「論点解説 対日平和条約(サンフランシスコ平和条約)における竹島の扱い」(本サイトに2021年1月29日掲載)でも明らかである。にもかかわらず、韓国は竹島を不法占拠した。本稿では、この状況を駐日各国大使館がどのように認識していたかについて考察する。
1.シーボルド米国駐日政治顧問の本国宛報告
1952年1月18日、韓国政府は李承晩ライン宣言(正式名称は「隣接海洋に対する主権に関する宣言」)を発し、朝鮮半島をとりまく広い海域に漁業管轄権(漁業を沿岸国のみが管轄できる権利)と主権を持つと主張した。日本政府は同月28日にこの宣言に抗議し、この海域の東端に竹島があったため竹島問題が発生した。韓国政府は同年2月12日にこれに反論し、日本政府は同年4月25日に再反論した。
シーボルド(William Joseph Sebald, 1901~1980)米国駐日政治顧問(駐日米国大使にあたる。当時日本は独立を回復していないため駐日大使という職はない)が1月29日付で米国国務省に送った報告1がある。シーボルドは当時日本を統治していた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP、以下「総司令部」と略記)の外交局長を兼ねていた。
報告のPartⅠで彼は前日の日本政府の抗議文2を紹介し、PartⅣでは次のように述べた。
韓国が李承晩ラインに竹島を含めたことは、この島の領有問題を持ち出すことになった。日本はSCAPINによってこの島に対する政治上及び行政上の管轄権を奪われている。しかし、除外したことによって平和条約の文言は領有権を日本に残したように見える。おそらく、これは総司令部や連合国と関係なしに、日韓間の交渉の議題とすることが適切だろう。
SCAPINとは1946年1月29日に総司令部が出した指令、すなわちSCAPIN-677 3のことである。それは竹島を、済州島や鬱陵島とともに、日本の行政区域からはずすものだった。ただし、この指令が日本の領土の最終決定ではないことはSCAPIN-677自体に書かれていた。日本の領土を最終決定したのは、1951年9月8日署名の平和条約であった。
注意すべきは、「除外したことによって平和条約の文言は領有権を日本に残したように見える(by exclusion, terms of Peace Treaty appear reserve sovereignty to Japan)」という文言である。「除外」とは、SCAPIN-677の「鬱陵島、竹島、済州島」という「日本の範囲から除かれる地域」と、平和条約第2条a項「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」の「済州島、巨文島及び鬱陵島」を比べると、平和条約では竹島が抜け落ちているという意味であろう。
シーボルドは1949年11月に、米国国務省の平和条約草案では「済州島、巨文島、鬱陵島、竹島」が朝鮮に属すとされていたのを見て、竹島に対する「日本の領土主張は古く正当と思われる」と述べて米国国務省に修正を求めた4。彼の意見が受け入れられて、同年12月に作成された平和条約草案では竹島は日本が保持する島に修正された。その後、日本が保持する島を記した条項はなくなったものの、竹島を日本領に残すという米国の方針に変化はなかった。1951年8月に米国政府が竹島は日本領であるとして公文(「ラスク書簡」)で韓国政府の竹島要求を拒否した。こうした経緯を彼は知らなかったことがこの報告でわかる。にもかかわらず、竹島は平和条約で日本領に残されたと彼は考えていた。
韓国には、「日本の執拗なロビー活動により、アメリカ国務省は一時サンフランシスコ平和条約の草案に独島を日本の領土と記載したこともあった」(「独島は韓国領土」のⅢ章「戦後の連合国の措置から見た韓国の独島領有権」(東北アジア歴史財団ウェブページ掲載)5)などという非難がある。「ロビー活動」とは、日本政府が竹島問題についてシーボルドを利用して米国国務省に働きかけたということであろう。しかし、そうではない。米国国務省は、シーボルドの意見も参考にしたであろうが、自らの情報と判断によって平和条約で竹島を日本領に残すことを決定した。シーボルドの報告はこのような事実を浮かび上がらせる。
平和条約で竹島を韓国領とするよう、1951年7月に韓国政府が米国政府に要求した記録(17日に卞榮泰(ピョン・ヨンテ)韓国外務部長官からムチオ駐韓米国大使に対して、19日に梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使からダレス国務長官顧問に対して)6は、米国駐日政治顧問部にも送られていた。また、鳥取県立境高校の実習船「朝凪丸」の乗員の竹島上陸を非難する韓国の新聞報道をまとめた同年11月28日付駐韓米国大使の国務省への報告7も、米国駐日政治顧問部に送られていた。その報告には「トク島は対日平和条約第2条の島として特記されるよう韓国政府が求めた島の一つであったことを想起させる」とあった。これらの情報への言及がシーボルドの報告にはないことは、李承晩ライン宣言で竹島問題が浮上する以前の彼は竹島への関心は薄かったことを意味する。すなわち、竹島に関して彼が1949年の国務省への働きかけ以上の行動を行っていないこと、つまり、日本政府の「執拗なロビー活動」を担ったわけではないことを物語っている。
註1
1950-52: 322.2 Boundary Waters (NARA, RG84 Records of Office of the U. S. Political Advisor for Japan, Tokyo Box No.64 Folder No.8). 原資料は米国国立公文書館所蔵。国立国会図書館憲政資料室所蔵「在日米国大使館領事館・政治顧問部文書」請求記号FSP 0337。
註2
「1952年(昭和27年)1月の李承晩韓国大統領による隣接海洋に対する主権宣言に対して、同月28日付で日本国政府が行った韓国政府に対する抗議(口上書)」(「竹島資料ポータルサイト」 資料番号T1952012800101)。
註3
「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する件(SCAPIN-677)」(同前T1946012900101)。
註4
塚本孝「平和条約と竹島(再論)」(『レファレンス』518 国立国会図書館調査立法考査局1994 年 3 月)41~43頁。
註5
http://contents.nahf.or.kr/japanese/item/level.do?levelId=isdk.j_0001_0030_0020 「2008.7」と最初に記されている。2023年10月3日最終閲覧。
註6
1950-52: 320.2 Peace Treaty, June – July 1951 (NARA, RG84 Records of Office of the U. S. Political Advisor for Japan, Tokyo, Box No.62 Folder No.1). 原資料は米国国立公文書館所蔵。国立国会図書館憲政資料室所蔵「在日米国大使館領事館・政治顧問部文書」の請求記号FSP 3781。
註7
1950-52: 322 Territory (NARA, RG84 Records of Office of the U. S. Political Advisor for Japan, Tokyo, Box No.7 Folder No.10). 前掲註(6)の国立国会図書館憲政資料室所蔵「在日米国大使館領事館・政治顧問部文書」の請求記号FSP 0560。
2.駐日英国大使館の本国宛報告
1953年5月28日、島根県水産試験場試験船「島根丸」の乗員は竹島での韓国人の活動を確認した8。同年6月27日、島根県と海上保安庁は合同で竹島調査を行い、上陸していた韓国人に退去を勧告し、日本領の標識を設置した9。「獨島侵害事件」として日本の竹島調査に反発した韓国国会は、同年7月8日に日本に強硬姿勢で対処することを政府に建議した。同月12日、竹島で巡視船への銃撃事件がおきた10。翌13日、日本政府はこの事件に抗議するとともに、竹島問題に関する見解を付した口上書を韓国政府に送付した。同年8月には二回にわたる抗議の応酬があり、同年9月9日に韓国政府は日本政府見解への反論を付した口上書を日本政府に送付した 。
1953年7月1日付で駐日英国大使館が送った、竹島問題についての英国外務省宛報告11には、「我々は、公刊資料からはその島についての日本の歴史的根拠の詳細を発見できなかった。しかし、18世紀初めに鬱陵島に向かう日本人旅行者たちによってその途中で発見されたようだ」。「鬱陵島と竹島に付けられた名称にはいくらか混乱があるように見える。そして松島という名称はまた、竹島にも用いられる」とあった。文中の「18世紀」は「17世紀」の誤りであるように、英国大使館は江戸時代の竹島の利用をはじめとする日本の歴史的根拠や1905年の竹島の島根県編入時の島名の入れ替わりといった経緯を把握していなかった。ただし、英国大使館が竹島問題に関する情報収集を行っていたことはわかる。同月5日付『朝日新聞(島根版)』にも、島根県の「東京事務所では英国大使館から領土帰属について照会があり」という記事がある。
1953年7月15日付で駐日英国大使館が送った竹島問題についての英国外務省宛報告12は、同月12日の竹島での銃撃事件の説明から始まる。続いて事件に対する日本政府の抗議と日本政府の領有主張について説明している。その説明は、前々日の13日の日本政府見解13の次の主張と同様であった。
日本政府見解は、戦後の竹島の取扱いについて半分以上を割いていた。1952年2月12日付反論での韓国政府の領有根拠が、SCAPIN-677とSCAPIN-1033のみであったことによる。SCAPIN-103314とは、総司令部が日本漁船の操業限界線(いわゆるマッカーサーライン)を改訂し、竹島への日本人の接近や接触を禁じた1946年6月22日付の指令である。日本政府はSCAPIN-677とSCAPIN-1033について、これらの指令自体に日本領土の最終決定ではないと明記してあることを指摘し、竹島が日本領土であることを前提に米軍の爆撃訓練区域に指定されたと主張した。
英国大使館の7月15日付報告は、前日14日付『読売新聞』夕刊が竹島問題の平和的解決のため日本政府は米英両国に仲介を依頼する模様であると伝えた15ことを取り上げている。続けて、日本政府外務省からの要請はまだないが近い将来あることは確実なので、その時は速やかに知らせるとある。重要なのは報告最後の次の部分である。
5.一方、貴殿は、我々の態度がどうあるべきか検討していることを期待しておられるかもしれない。仮に、仲介が必要であるならば、我々は、もちろん、双方にそれぞれの立場の提示を求めるべきであろう。しかし、さしあたり考えるに、我々が共同署名国となっている平和条約第2条において、竹島は間違いなく日本の領土の一部を形成しているということである。
英国大使館の認識は、「さしあたり(preliminary)」としながらも、「竹島は間違いなく日本の領土の一部を形成している(Takeshima unmistakably forms part of Japanese territory)」であった。これも日本政府の見解を反映したものと思われる。
日本政府は同見解で、平和条約第2条a項「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」について、次のように主張した。竹島は「既に日韓併合以前において島根県の行政管轄下にあり、朝鮮総督府の管轄下におかれたことはなかった」。第2条a項にいう「独立した朝鮮」に日本領土であった竹島を割譲することはありえない。第2条a項で「済州島、巨文島及び鬱陵島」を列挙したのは「独立した朝鮮」にこれら3島が含まれることを「念のため」明らかにしたのであって、日本領土であった竹島がここに入らないのは当然のことである。
英国大使館の担当者は“it appears”, “it seems”, “the texts indicate”といったあいまいさを含む語句ではなく、“unmistakably”と強い表現を使用して日本の領有主張を支持した。韓国の領有根拠がSCAPIN-677とSCAPIN-1033しかなく、しかも、それが日本政府によって明確に否定されている状態では、それは妥当な評価であった。
註8
関連新聞記事として、1953年5月31日付『毎日新聞』(大阪)「「竹島」へ韓国人が上陸」(「竹島資料ポータルサイト」資料番号T1953053100102)、同年6月4日付『毎日新聞(島根版)』「『竹島の韓国漁船』は領海侵犯か 調査の上厳重抗議 小瀧外務次官語る」(同前T1953060400102)。
註9
「島根県・海上保安庁合同竹島調査「復命書」」(同前T1953062800103)。
註10
関連新聞記事として、1953年7月14日付『山陰新報』「竹島で巡視船發砲さる」(同前T1953071400202)。
註11
Japanese claim to Takeshima Island, also claimed by the Republic of Korea (TNA, FO371/105378, Code FJ file 1082). 原資料は英国国立公文書館所蔵。国立国会図書館憲政資料室所蔵「英国外務省 本省一般政務文書 日本ファイル 1952-1974」請求記号BFO-2。
註12
前掲註(11)に同じ。『平成29年度内閣官房委託調査 竹島に関する資料調査報告書』(株式会社ストリームグラフ 2018年3月)36~37頁。
註13
外務省情報文化局「記事資料」 島根県立図書館所蔵。
註14
「日本の漁業及び捕鯨業許可区域に関する件(SCAPIN-1033)」((「竹島資料ポータルサイト」資料番号T1946062200101)。
註15
前掲註(12)『平成29年度内閣官房委託調査 竹島に関する資料調査報告書』38頁。