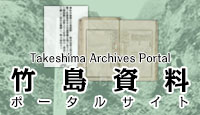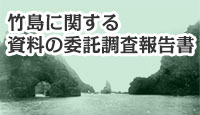本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
4.平和条約の領土条項とオーストラリア
1951年7月20日付の釜山のプリムソル(豪州の外交官で当時 UNCURK (国連朝鮮統一復興委員会)の豪州代表に任命されていた)から豪州外務省宛の電文No.3811には、「韓国外相は日本との平和条約草案への4点の修正について我々の支持を求めた」とあり、4点のうち(a)は、「第2条(a)の「含む」という語句の前に「および日本の韓国併合の前に朝鮮の一部であったすべての島々」を挿入する。また、とりわけドク島及びプラン島の名称を記す」であった。
韓国は、同年7月19日付の梁裕燦駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡で竹島を要求したが、同時期に同様の要請を豪州に対して行っていたことがわかる資料が発掘されたのである。
豪州外務省のプリモソルに対する1951年7月25日付電報No.3212では、「我々は、この種類の問題について貴殿を仲介者として用いる韓国政府の作法に疑問を感じるが、韓国外相に彼が示唆した日本との平和条約への修正に対する我々の仮の反応を全く非公式に伝えることぐらいは差し支えなかろう。我々は、韓国が提案した修正が現実的なものなのか確信が持てないが、原則、条約で自国の利益を守るための韓国政府の望みに共感するものであると貴殿は(韓国に‐藤井補注‐)言ってもよかろう」と述べて、豪州が韓国の要求の仲介者となることに消極的であった。
竹島問題については、豪州外務省は「貴殿の言う二つの島は、我々の持っているどんな朝鮮の地図でも探し出すことができない。」と述べた。これは、駐米韓国大使館の要求に応じて調査したが、米国務省の地理専門家である「ボッグズ氏が言うには「ワシントンにあるあらゆる資源に当った」が…ドク島とパラン島を特定でなかった」、同じく朝鮮担当官の「フレリンヒューセンの報告によれば、韓国大使館に聞いたところドク島は鬱陵島又は竹島の近くであろう、パラン島もそうかもしれないとのことであった」という米国の記録13とよく似ている。
ニュージーランド(以下「NZ」と略記)政府外務省作成の1953年12月2日付の資料 「日韓関係 特に竹島をめぐる紛争に関連して」の「竹島紛争」の項に、韓国から豪州への1951年7月21日付の電文に残された、韓国外務部長官の豪州への要請の記録がある14。そこには、韓国外務部長官は「ドク島」と「プラン島」を韓国領にするよう要求し、「これら二つの島は本土の南にある程度の距離にあり(these two islands were some distance to the south of the mainland)」と述べたとあった。韓国は「ドク島」と「パラン(プラン)島」の正確な位置すら示すことができなかった。米豪両国が韓国の求めに応じなかったのは当然であった。
平和条約草案への各国の意見およびそれを反映させるかについての米国の見解をまとめた1951年8月7日付米国務省文書 (Treaty Changes)15によれば、第2条(a)への「ドク島」と「パラン島」の追記を要求したのは、韓国だけだったことがわかる。「竹島を韓国領にするというのは韓国だけの意見であり、竹島領有権を決定するにおいていかなる効力ももちえない」が事実なのである。
註11
Amendments to Draft Japanese Peace Treaty 27th July, 1951 (NAA, Item ID: 140412, Japanese peace settlement)。「プラン島」=Prangdoは「パラン島」=Parangdo のことであろう。
註12
前掲註(11)
註13
Office Memorandum, To: Allison From: Fearey, Date: August. 3, 1951 (Comments on Korean Note Regarding U. S. Treaty Draft (NARA, RG59, Lot54 D423, JAPANESE PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea))※。
註14
JAPANESE - KOREAN RELATIONS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DISPUTE CONCERNIMG TAKAESHIMA ISLAND (ANZ, Post-war settlement - Japanese peace settlement – Territorial (Code:R20107058)) )p.9。
註15
Treaty Changes(NARA, RG59, Records of the Bureau of Public Affairs, Records Relating to the Japanese Peace Treaties, 1946-1952, Lot78 D173 Box2) ※。
おわりに
豪州外務省の1951年7月25日付電報No.32の最後に、「我々は、正しく朝鮮の一部と認められうる島々をできるだけ特記する草案にすることに反対はしない」とある。「日本と朝鮮の間にある島嶼が明確な表現で処遇されることが望ましい」という米英事務レベル協議での英国の方針を豪州が支持していたことを示している。
「日本近傍のいずれの島にも主権紛争を残さないようにすることを確保する必要性にかんがみ、英国草案第1条で提案されているように日本が保持すべき領土を経緯度によって正確に確定することが望ましいと考える」という、1951年6月1日付の米国文書に残る、NZ政府の米国草案に対する見解がある16。1947年の英連邦キャンベラ会議での英国の平和条約の領土条項に関する方針「どの島嶼も主権についての紛争が残ることにならないよう、この条項は非常に慎重な原案作りが必要である」をNZも共有していたことがわかる。
英国、そしてNZと豪州のこのような方針が、平和条約の領土条項作成において無視されたとは到底考えられない。平和条約第2条(a)の「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」について、米国と英連邦諸国の間で意見の相違はなく、竹島が日本の放棄する朝鮮に属する島に含まれないことは明らかである。
NZ外務省作成の「日韓関係 特に竹島をめぐる紛争に関連して」の「竹島紛争」には、「この韓国の不満の示唆にもかかわらず、韓国が望んだ意味での第2条a項の修正は行われることなく、平和条約は最終的に調印された(Despite this indication of Korean dissatisfaction, the Peace Treaty was finally signed without amendment of article 2(a) in the sense desired by Korea.)」とある。竹島が日本領に残ったことは、連合国の共通認識だったのである。
註16
JAPANESE PEACE TREATY, Working Draft and commentary, June 1, 1951 (NARA, RG59, Central Decimal File 1950-54 Box3009, 694.001/6-151)※。