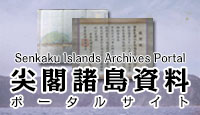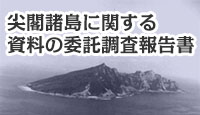本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
南シナ海・東シナ海
コラム 中国の南シナ海における十段線の狙い
坂元 茂樹(神戸大学名誉教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
1. はじめに
2023年8月28日、中国自然資源省が「2023年版標準地図」を公表した。この地図では、南シナ海の従来の「九段線」に加え、新たに台湾を囲った線を一本足した「十段線」が示された1。中国は、これにより、南シナ海海域に対する歴史的権利の主張とともに、島嶼帰属の線の役割を付け加えたように読める。この新たな線が、台湾は中国の領土であるという島嶼帰属を意図する線であることは明白である。なお、松野博一官房長官(当時)は、2023年9月5日の記者会見で、「2023年版標準地図」で尖閣諸島の魚釣島を中国が領有権を主張する「釣魚島」と表記したことに抗議した2。

出所:https://www.sankei.com/article/20230901-KKKY4I7NJVI3RKGFEFM7234BCQ/photo/BTHX2NNZXNIE3N4RZUNRWH7OYY/
九段線のルーツは、1947年12月1日に中華民国内政省地域局が作成し、国民政府が公布した「南海諸島新旧名称対照表」と「南海諸島位置図」に遡る。そこには、11段のU字線が描かれ、南沙諸島や西沙諸島らが取り込まれていた。1949年、中華人民共和国も公式地図としてこれを発行した。
1951年9月8日に署名された対日平和条約第2条(f)は、「日本国は新南群島[坂元注:南沙諸島]及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定したが、これに先立つ同年8月15日、周恩来首相(当時)は、「この草案は、日本が西鳥島及び西沙群島に対するいっさいの権利を放棄することを規定しているが、再び故意にこれらの島嶼についての主権の回復問題には言及していない。事実上、南沙群島、中沙群島及び東沙群島全部と、全く同じように、西沙群島及び西鳥島は、従来常に中国の領土であった3」と声明した。「南海諸島位置図」という地図の名称やその後のこうした中国政府の声明に鑑みれば、九段線の本質は、当初は、島嶼帰属の主張を示す線と考えられていたと解釈するのが妥当であろう。
1953年にトンキン湾のバイ・ロン・ウェイ島の領有権を中国からベトナムに移転した際、中国の地図では一一段線が九段線に書き換えられた。それ以降、九段線として知られるようになった。しかし、これからは、十段線と呼称されることになろう。いずれにしても、中国政府による十段線の公表が、台湾は中国の領土に属する島嶼であるとの強いメッセージであることはいうまでもない。
註1
「人民網日本語版」2023年8月29日(最終閲覧日:2024年1月4日)
註2
『朝日新聞』2023年9月6日朝刊14面。
註3
対日平和条約草案及びサンフランシスコ会議に関する周恩来声明、高野雄一『日本の領土』(東京大学出版会、1962年)339頁。
2. 台湾への圧力を強める中国
中国の習近平国家主席は、2023年12月31日、新年を迎えるにあたっての恒例のテレビ演説を行い、2024年1月13日に行われる台湾の総統選を念頭に、「祖国統一は歴史の必然であり、台湾海峡両岸の同胞は手を携え、心を合わせ、民族復興という偉大な栄光を分かち合わなければならない4」と述べて、台湾統一への決意を改めて表明した。しかし、2024年1月13日に投開票が行われた台湾の総統選挙では、台湾独立派と批判されてきた与党・民進党の頼清徳氏が当選し、中国の期待に反する結果になった5。
台湾をめぐって、米中は激しく対立している。2022年8月2日、ナンシー・ペロシ米国下院議長(当時)が、現役の下院議長としては25年ぶりに台湾を訪問し、蔡英文総統と会談した。中国はこれに激しく反発し、台湾周辺の海・空域において、8月2日夜から10日にかけて、統合封鎖、対海上・地上攻撃、制空作戦、空中偵察、対潜戦などの大規模な軍事演習を行った。日本の防衛省によれば、この軍事演習では、戦時における台湾の封鎖や対地・対艦攻撃、制海権・制空権の獲得、サイバー攻撃や「認知戦」などのグレーゾーン事態といった、対台湾侵攻作戦の一部が訓練された可能性があると考えられている6。中国が、自国と台湾が武力衝突する台湾有事を想定していることは明らかである。
実際、2022年10月16日から22日に開催された第20回中国共産党大会で、習近平国家主席は、台湾統一の方針を巡り、「決して武力行使の放棄を約束しない。必要なあらゆる措置をとる選択肢を持ち続ける7」と強調した。もっとも、それが直ちに台湾への武力侵攻に結びつくのか、台湾周辺の海上封鎖なのかは、台湾情勢をめぐる日米の対応を見極めた上で、中国が決断することになろう。異例の3期目に入った習氏が、台湾統一を、自らの任期中に達成できるかどうは別として、道筋をつけて自らのレガシー(政治的遺産)にしたいと考えていることは確かである8。
もっとも、2022年2月22日に開始されたロシアによる「特別軍事作戦」と称するウクライナ侵略は2年を経過しようとするが、未だに戦争が継続している。地続きであるウクライナでさえロシアが目的を達成できていない現状をみると、島嶼である台湾では中国の軍事力をもってしても制圧は簡単ではないことがわかる。さらに海上封鎖は、交戦当事者が国同士の国際的武力紛争でしか許容されない手段である。中国は、台湾は中国の領土の一部と主張するので、仮に中国と台湾の間で武力紛争が発生したとしても、当該紛争は非国際的武力紛争となる。中国が、台湾に出入りする第三国の船舶と航空機を周辺の排他的経済水域や公海で海上封鎖し、それを侵犯する船舶等に対して海上捕獲を行おうとしても、それはできない。もし仮にこれを強行すれば、国際法上は台湾を交戦団体として黙示的に承認したと解され、両者の間の武力紛争は非国際的武力紛争から国際的武力紛争に転換する。台湾の法的地位の承認につながる行為を避けたい中国としては、「海上封鎖」という概念や用語を用いた行動はとれないことになる9。習近平氏は「決して武力行使の放棄を約束しない」というが、実際の武力行使には軍事的にも国際法的にも様々な困難が伴う。
最近の報道によれば、先の大規模軍事演習の頃から、台湾周辺で主にフリゲート艦4隻が常時展開するようになったという。4隻は、沖縄県・与那国島周辺に1隻、与那国島とフィリピンの間に1隻、台湾の南西と北の海域にそれぞれ1隻ずつ配置されているという10。中国は、米海軍に対抗するため、「接近阻止/領域拒否(A2/AD)」能力の強化を図り、「第1列島線」の内側に米軍を侵入させない戦略をとっているが、常時展開する中国軍艦の位置はこれとほぼ重なっている。
註4
『産経新聞』2023年12月31日
(最終閲覧日:2024年1月29日)
註5
『朝日新聞』2024年1月13日
(最終閲覧日:2024年1月29日)
註6
「〈解説〉台湾をめぐる中国の軍事動向」『令和5年度防衛白書』
(最終閲覧日:2024年1月29日)
註7
『日本経済新聞』2022年10月16日
(最終閲覧日:2024年1月29日)
註8
「変る中国とのつきあい方」(垂秀夫前中国大使インタビュー)『朝日新聞』2024年1月27日朝刊9面。
註9
詳しくは、真山全「中国による対台湾海上交通妨害の国際法的検討」『交流』No.986(2023年)7-16頁参照。
註10
『読売新聞』2024年1月29日
(最終閲覧日:2024年1月29日)
3. 南シナ海で圧力を強める中国
2021年2月1日に施行された「中国海警法」は、海警が活動する海域として、「海警機構は、中華人民共和国の管轄水域(以下、「我が国管轄水域」という。)及びその上空において海上権益擁護の法執行業務を展開し、本法を適用する」(第3条)と規定し、南シナ海の九段線の海域で執行管轄権を行使している11。そのため、フィリピンなど南シナ海の周辺国との間で緊張が高まっている。
とりわけ中国に融和政策をとっていたドゥテルテ前政権に変り、2022年6月にフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領が就任し、「領域は1インチたりとも譲らない」と宣言し、2014年に締結された比米防衛協力強化協定(EDCA)を改定し、米軍が利用可能な基地を5カ所から9カ所に増やす措置をとったことで、中国がフィリピンに対し対抗措置を強めるようになった。
2023年9月26日、フィリピン沿岸警備隊は、中国海警局と海上民兵によって南シナ海のスカボロー礁に設置された全長300メートルの浮遊式の障害物を撤去した。フィリピンは、スカボロー礁やセカンド・トーマス礁、ウィットスン礁を含むスプラトリー諸島(南沙諸島)の領有権をめぐって中国と争っている。フィリピンは、スカボロー礁は「国家領土の不可欠の一部」であると主張している。
フィリピンは、1999年、アメリカ海軍から譲渡された老朽艦シエラマドレ号をセカンド・トーマス礁(フィリピン名:アユンギン礁、中国名:仁愛礁)に「難破」させ、海兵隊員らを常駐させ実効支配の拠点とした。中国海警船は、2023年2月6日、生活物資を届けるフィリピンの補給船に放水銃を浴びせ、警護するフィリピン巡視艇にレーザー照射する妨害行為に出た。同年4月28日には、フィリピン巡視船に中国海警の大型船が40メートルまで接近し、衝突寸前となる事件も発生した。
2023年10月22日、スプラトリー諸島(南沙諸島)の海域で、フィリピン軍の輸送船と中国海警局の船が衝突するとともに、軍の輸送船を警備していたフィリピン沿岸警備隊の巡視船と中国の海上民兵の船が接触する事故が発生した。同月25日、米国は、「フィリピンの公船、航空機、軍が南シナ海を含む太平洋で攻撃を受けた場合には、米国とフィリピン間の防衛協力強化協定が適用される」と述べて、米国に防衛義務が生じることを強調して中国をけん制した。これに対し、中国の毛寧報道官は、米国には「中国とフィリピンとの間の問題に介入する権利はない」と反発した12。
2023年12月3日、フィリピン沿岸警備隊は、フィリピンが自らの排他的経済水域と主張するスプラトリー諸島海域に135隻を超える中国民兵が乗り込んでいるとみられる中国船が停泊していると発表した。フィリピンは退去要請を行ったが中国は応じてはいない。中国によるフィリピンへの圧力は高まっている。
註11
坂元茂樹「機能拡大する中国海警―中国海警法の狙いを探る」坂元『日本の海洋政策と海洋法[第3版]』(信山社、2023年)32頁。
註12
「南シナ海での船舶衝突 フィリピンと中国互いに抗議 対立深まる」
(最終閲覧日:2024年1月29日)
4. 南シナ海仲裁判決を無視し続ける中国
フィリピンが南シナ海における中国による九段線の主張は国連海洋法条約に違反し無効であるとして中国を訴えた南シナ海仲裁事件で、裁判所は、2016年7月、「中国は、スカボロー礁における伝統的漁業活動に介入し、フィリピンの漁民が生計を立てるのを違法に妨げている」とし、「中国は、スカボロー礁近海で、フィリピン船舶に衝突する危険のある方法で法執行船舶を運用しており、国連海洋法条約上の義務に違反している」と述べるとともに、「中国は、セカンド・トーマス礁において、紛争を違法に悪化し拡大させている。(a)同礁水域と隣接水域でフィリピンの航行権に干渉している。(b)同礁のフィリピンの人員の交代・補給を阻害している。(c)同礁に駐留するフィリピン人の健康と安寧を危険にさらしている13」と判示した。それにもかかわらず、中国は、当該判決を無視してスプラトリー諸島の礁に対する実効的支配を続けている。
2019年12月12日付けのマレーシアの大陸棚延長に対する大陸棚限界委員会の申請に対して、中国は、自らの身勝手な主張を再び国連の場で述べた。2020年6月2日付けの国連事務総長宛ての口上書で、「中国は南シナ海において歴史的権利を有している。南沙諸島に対する中国の主権及び南シナ海における海洋権益は長い歴史的慣行の過程において確立され、国連憲章及び国連海洋法条約を含む国際法に合致している」(1項)と述べるとともに、「仲裁裁判所は、権限を踰越して管轄権を行使し、そして事実の確認及び法の適用において明らかに誤りを犯している。仲裁裁判所の行動とその判決は、…主権国家及び国連海洋法条約の締約国としての中国の正当な権利を重大に侵害しており、それゆえ不当かつ不法である。中国政府は、仲裁判決を受け入れないし、また承認もしないことを厳粛に宣言する。この立場は国際法に合致する14」(3項)とまで述べたのである。各国がこれに反発したのは当然である。
2020年5月26日付けのインドネシア国連代表部の国連事務総長宛ての口上書は、「歴史的権利の主張を含意する九段線の地図は明らかに国際法上の法的根拠を欠き、1982年の国連海洋法条約を無効にするに等しい15」と述べ、中国に反論した。ニュージーランドも、2021年8月3日付けの口上書において、「2016年の南シナ海仲裁判決で確認されたように、南シナ海の海域に関する『歴史的権利』を主張する国には法的根拠はない16」と反論した。各国が反発するように、間違っているのは南シナ海仲裁判決ではなくて、中国である。
註13
Award of the South China Sea Arbitration Case, July 12, 2016, pp.12-14, para.31 and pp.17-19, para.41.
註14
Note Verbale dated 2 June 2020 from the Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations addressed to the Secretary- General of the United Nations, CML/46/2020.
註15
Note Verbale dated 26 May 2020 from the Permanent Mission of Indonesia to the United Nations addressed to the Secretary- General of the United Nations, CML/46/2020.
註16
Note Verbale dated 3 August 2021 from the Permanent Mission of New Zealand to the United Nations addressed to the Secretary- General of the United Nations, Note Verbale No. 08/21/02.
5. おわりに
海洋強国中国の南シナ海における最近の行動は、その軍事力や海上警察機関を背景に、「力による現状変更」を求めている。尖閣諸島を台湾の附属島嶼と考える中国の立場を考えれば、台湾有事は尖閣有事につながりかねない。南シナ海で生じていることは東シナ海でも生じるのである。
2013年11月23日、中国は尖閣諸島を含む東シナ海上空に防空識別圏(ADIZ)を設定した。防空識別圏とは、領空侵犯を防ぐため、各国が自国の領空の外側に設定している空域で、侵入してくる航空機に領空侵犯の恐れがあるかどうかを識別し、戦闘機が緊急発進(スクランブル)する必要性を判断するためのものである。人民解放軍の部署が当初予定していた防空識別圏の範囲を、九州沖に寄せる形で修正したのは習近平政権だとされる17。最近の報道によれば、中国は、防空識別圏の境界線付近に、常時3隻以上の軍艦を展開させているという18。自衛隊関係者によれば、「台湾有事などの際には、自衛隊機や米軍機の進入を阻止する意図がある」とされるが、台湾有事は尖閣諸島有事でもあり、日本としては警戒を怠ることができない状況にあるといえる。