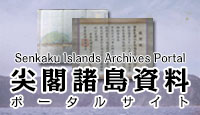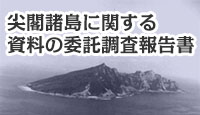本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
南シナ海・東シナ海
コラム 東シナ海における日中韓間の境界未画定海域と「自制義務」
西本 健太郎(東北大学大学院法学研究科教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
1.東シナ海における海洋境界画定と「自制義務」
(1)東シナ海における日中韓の海洋境界画定
東シナ海は日本と中国・韓国に囲まれた海域であるが、日本と中国・韓国の排他的経済水域(EEZ)と大陸棚の境界線は定まっていない。国際法上、海に面した国家(国際法の用語では「沿岸国」という)は200海里(約370キロメートル)までのEEZを設定することができ、また、少なくとも200海里の大陸棚を有することになっている。東シナ海のようにこの200海里の範囲が重複する場合には、合意により境界線を決める必要がある(この線引きのことを「境界画定」という)。しかし、日本と中国・韓国との間では、対馬海峡付近の大陸棚の境界線が1974年に締結された日韓大陸棚協定によって合意されているのを除いて1、EEZ・大陸棚の境界線について合意がない状態が続いている。
東シナ海における境界画定が困難であるのは、日中間では中国が日本の尖閣諸島に対する領有権を主張していることも影響しているが、境界画定の方法について日本と中国・韓国との間で主張が対立していることが主な理由である。海洋の国際的秩序について定めている国連海洋法条約は、EEZ・大陸棚の境界画定について「・・・衡平な解決を達成するために・・・国際法に基づいて合意により行う」(74条1項・83条1項)と規定している。日本は双方の海岸線からの中間線に基づいた境界画定が衡平な解決であり、国際判例にも整合的であるとの立場をとっている2。これに対して中国は、日本が主張する中間線による境界画定を認めずに、具体的な境界線の主張を示すことなく、自国の大陸棚は九州西方から琉球列島の北方に沿って延びている沖縄トラフと呼ばれる海底の窪みまで自然に延長しているとの立場を表明してきている3。韓国も同様に、自然の延長に依拠した主張を行っている。
「自然の延長」とは、陸上の領土が海底に向かって延長しているがゆえに沿岸国は大陸棚に対する権限を有するという考え方である。これは現在でも大陸棚制度の根拠となっている考え方ではあるものの、国連海洋法条約ではEEZと同じ200海里までは海底の地質的・地形的状況を問わずに沿岸国の大陸棚として認めている(76条)。そのため、距離に基づく大陸棚が重複している400海里未満の海域では海底地形に法的な意味はないというのが日本の立場である4。なお、中国・韓国の立場からは大陸棚については自然の延長に基づいた境界画定を行うとしても、距離に基づく制度であるEEZについてはどのように境界画定を行うのかが問題となるはずであるが、この点に関する具体的な主張はなされていない。
今日ではEEZ・大陸棚の両方に共通する単一の境界線を引くことが一般的であり、国際判例では①等距離・中間線によって暫定的な境界線を引き、②衡平な結果を達成するために暫定的な境界線の修正を必要とする事情(関連事情)の有無を検討し、必要に応じて修正した上で、③関連する海岸の長さと境界画定の結果としての双方の海域の面積との間に著しい不均衡が生じているという意味での不衡平な結果となっていないかを検証する、という「3段階アプローチ」が採用されるようになっている5。日本と中国・韓国の主張を比較した場合、等距離・中間線に基づいた境界画定を主張する日本の方が国際判例に整合的である。
(2)境界未画定海域としての東シナ海と「自制義務」
関係国の間でEEZ・大陸棚等の境界線が決まっていない海域は「境界未画定海域」と呼ばれる。東シナ海のように長期間に亘って境界線が未画定のままとなっている例は、国際的に見て必ずしも珍しくはない。EEZ・大陸棚の境界画定は、海洋資源の配分という各国の重要な関心事に関わっており、また、200海里の基点となる領土に対する主張が関係している場合などもあり、妥協による解決が容易ではないためである。しかし、境界線が未画定のまま関係国がそれぞれ自国の主張する境界線に基づいて一方的に活動や規制を行うことは紛争の発生・悪化に繋がりかねない。このことに鑑みて、国連海洋法条約は、海洋境界に関する合意が得られるまでの過渡的期間に適用される義務を定めている。それは、関係国は「・・・・・・合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及び最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う」というものである(74条3項・83条3項)。
このうち暫定的な取極の締結については、東シナ海では日韓大陸棚協定(南部協定)の下での鉱物資源の共同開発6や、日中漁業協定7および日韓漁業協定8の下での漁業資源に関する取り決めの形で行われてきている。これに対して「最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う」義務については、一定の行為を差し控えることが求められていると解釈できるものの(そこで以下、この義務を便宜上「自制義務」と呼ぶ)、その表現は必ずしも具体的ではない。そのため、どのような行為が違反となるのかが議論されてきた。東シナ海では、中間線の中国側で中国が一方的な鉱物資源の開発行為を行っており、日本が遺憾の意を表明してきているという経緯もある9。自制義務の具体的な内容がどのようなものであるかは、このような一方的行為が国際法上違法なものとして評価されるかに直結する問題であるが、この点については最近の国際判例で一定の理解の収斂が得られつつある。以下ではその内容をさらに紹介するとともに、国際裁判所を通じた東シナ海における紛争の解決の可能性について説明する。
註1
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の北部の境界画定に関する協定(1974年1月30日署名、1978年6月22日発効)
註2
註3
Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "China's Oil and Gas Development in the East China Sea is Justified and Legitimate."
註4
外務省(註2)2(2)項。
註5
Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, pp. 101-103 (paras. 115-122).
註6
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定(1974年1月30日署名、1978年6月22日発効)
註7
漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(1997年11月11日署名、2000年6月1日発効)
註8
漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(1998年11月28日署名、1999年1月22日発効)
註9
2. 国際判例における自制義務
境界未画定海域に適用される自制義務は、一方的な活動を完全に禁止する趣旨ではないと理解されてきた。この理解は国連海洋法条約の起草過程からも確認できる。国連海洋法条約の交渉過程では、境界画定合意に至るまで境界未画定海域での自国の権利の行使を制限する提案は支持されず、代わりに最終的な境界画定合意への到達を阻害する行為に着目する現在の規定が採用されたのである10。そこで、自制義務の内容をめぐっては、関係国間の暫定的な取極に基づかずに境界未画定海域で一方的に行われる行為のうち、どのようなものが違反となるのかが問題となってきた。
(1) ガイアナ・スリナム事件(国連海洋法条約附属書VII仲裁裁判所・2007年判断)
ガイアナ・スリナム事件は南米のガイアナとスリナムの間で発生していた領海、EEZおよび大陸棚の境界画定に関する紛争が、2004年に国連海洋法条約附属書VIIに基づく仲裁裁判所に付託されたものである。両国がそれぞれ主張する境界線に挟まれた係争海域ではガイアナが民間企業に対して石油探査の許可を付与しており、これに基づいて活動を行っていた掘削船に対してスリナム海軍が退去を命じるという事件も発生していた11。スリナムはガイアナが係争海域で石油探査を許可したことが自制義務に違反すると主張したのに対して、ガイアナは試掘船に対するスリナム海軍の行為が自制義務に違反すると主張した。
仲裁裁判所は、暫定取極に基づかない一方的活動であっても、最終的な合意への到達を危うくし又は妨げるものでなければ自制義務の違反にはならないとの判断を示した12。そしてより具体的に、海洋環境に対して恒久的な物理的変更をもたらす活動が暫定取極なしに行われた場合には合意への到達を危うくし又は妨げることになるが、そうではない活動は一般的には許されるとした13。仲裁裁判所はこの基準を適用して、ガイアナによる試掘の許可は自制義務に違反するが、音波を用いた地震探査の実施は本件の状況の下では違反に当たらないと結論づけた14。
(2) ガーナ・コートジボワール事件(国際海洋法裁判所特別裁判部・2017年判決)
ガーナ・コートジボワール事件は西アフリカのガーナとコートジボワールの間の領海、EEZおよび大陸棚の境界画定に関する紛争が、2014年に国際海洋法裁判所(ITLOS)の特別裁判部に付託されたものである。ガーナは両国間のEEZ・大陸棚の境界線は双方の海岸線の等距離線であることが黙示的に合意されていたとの立場をとり、そのガーナ側の海域で石油開発を行っていた15。これに対して、コートジボワールは等距離線よりもガーナ寄りの境界線を主張し、ガーナによる石油開発が自国の大陸棚の主権的権利を侵害し、自制義務にも違反すると主張した16。
ITLOS特別裁判部は、2つの理由を挙げて自制義務の違反に関するコートジボワールの主張を認めなかった17。第1の理由は、ガーナが裁判所による仮保全措置に従って最終的には係争海域における活動を中止したという事情である。第2の理由は、「コートジボワールの海域」における自制義務の違反が主張されていたところ、判決はガーナの主張に沿って等距離線に基づく境界画定を行ったので、等距離線のガーナ側における活動は「コートジボワールの海域」における自制義務の違反にはあたらないというものである。
コートジボワールが境界画定前の係争海域全域を対象に自制義務の違反を主張しなかった理由は不明であるが、このことにより判決は自制義務の内容について詳細な検討を行わなかった。ただし、ガイアナ・スリナム事件で示された基準が踏襲されていれば、係争海域における掘削は直ちに自制義務の違反となり、その後中止したという事情は違反を否定する理由にはならないはずである。そのため、本判決はガイアナ・スリナム事件とは異なる理解を採用するものと考えられる。また、本判決には自制義務を「結果指向的な概念」と捉えるべきであり、ガイアナ・スリナム事件のような一般的・抽象的な基準によってではなく、活動の種類、性質、場所、時期および態様等を考慮し、関係国間の関係に照らして判断すべきであるとする個別意見も付されている18。
(3) ソマリア・ケニア事件(国際司法裁判所・2021年判決)
ソマリア・ケニア事件は東アフリカのソマリアとケニアとの間の領海、EEZおよび大陸棚の境界画定に関する紛争が、2014年に国際司法裁判所(ICJ)に付託されたものである。ソマリアは、係争海域におけるケニアの活動が自国の領海に対する主権とEEZ・大陸棚に対する主権的権利・管轄権の侵害であるとともに、自制義務の違反にも当たることを主張した。自制義務の違反に当たるとして主張されたのは、石油鉱区に対する権益の民間事業者への付与や、これに基づく地震探査や掘削の実施である。
ICJ は明示的にガイアナ・スリナム事件における仲裁判断を引用しつつ、鉱区権益の付与や地震探査の実施は海洋環境に対する恒久的な物理的変更を伴う種類の活動ではなく、かつ、海洋境界画定の最終的な合意へ到達することを危うくし又は妨げる効果を有するものであったとも立証されていないとして、自制義務の違反を否定した19。また、掘削の実施に関するソマリアの主張については、恒久的な物理的変更が生じうるものであることを前提としつつ、係争海域において行われたという事実が立証されていないとして主張を退けた20。
(4) 国際判例から得られる理解と残された問題
国際裁判所において自制義務の内容が初めて詳細に検討されたガイアナ・スリナム事件の仲裁判断では、海洋環境の恒久的な物理的変更を伴う活動の実施は自制義務の違反となるという明確な基準が示された。その後はガーナ・コートジボワール事件判決まで同種の事件がなく、また同事件では異なる判断がなされたために、ガイアナ・スリナム事件で示された「海洋環境の恒久的な物理的変更」の有無という基準を一般的に通用するものとして捉えてよいのかについては、議論があった。しかし、ソマリア・ケニア事件においてICJがガイアナ・スリナム事件の基準を踏襲したことで、少なくとも掘削を伴う一方的な活動については自制義務の違反に当たるとの判断が今後定着していく可能性が高い。
ただし、これまで自制義務が問題となった3つの事件はいずれも石油・天然ガス開発に関係するものであり、かつ、確立しつつあるのは「海洋環境の恒久的な物理的変更」があれば自制義務の違反になるという点のみであることには注意が必要である。漁業活動や海洋科学調査の実施などの他の種類の活動にも同じ基準が当てはまるかは、必ずしも明らかではない。また、ガイアナ・スリナム事件の仲裁判断とICJのソマリア・ケニア事件判決は、「海洋環境の恒久的な物理的変更」がなければ自制義務違反にはならないとは述べておらず、このような場合にも個別具体的な事情に鑑みて違反が認定される余地が示唆されている。その意味で、自制義務の違反となる一方的な活動の範囲については、国際判例上なお不明瞭な点が残されている。
さらに、3つの事件ではいずれも隣接国間でそれぞれの主張する境界線が明確に示されており、その2つの線の間の海域が自制義務の適用される係争海域として理解されていた。これに対して、東シナ海では中国は具体的な境界線を示すことなく自然の延長論に基づく主張をしており、日本も中間線に基づく境界画定が衡平な解決であるとの立場をとりつつ、それ以遠に対する権原の主張を放棄しているわけではない21。このように双方が積極的に争っている範囲が明確ではない場合には、両国間の境界未画定海域のうち地理的にどの範囲に自制義務が適用されるのかという問題がある22。この点についても国際判例から明確な回答は得られるわけではない。
註10
境界画定合意までは等距離線を超えて権利を行使してはならないとする条文提案の例として、UN Doc. A/CONF.62/C.2/L.14 (1974), Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume III, pp. 190-919 (Netherlands); UN Doc. A/CONF.62/C.2/L.31/Rev.1 (1974), ibid., p. 211 (Japan).
註11
Award in the Arbitration Regarding the Delimitation of the Maritime Boundary Between Guyana and Suriname, Award of 17 September 2007, Reports of International Arbitral Awards, Vol. XXX (2012), p. 36 (paras. 150-151).
註12
Ibid., p. 132 (para. 466).
註13
Ibid. (para. 467).
註14
Ibid., p. 137 (paras. 479-481).
註15
Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), Judgment, ITLOS Reports 2017, pp. 39-40 (para. 102), pp. 43-52 (paras. 113-145).
註16
Ibid., p. 32 (para. 63).
註17
Ibid., pp. 167-169 (paras. 629-634).
註18
Separate Opinion of Judge Paik, ibid., pp. 178-184.
註19
Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Judgment, ICJ Reports 2021, p. 282 (para. 207).
註20
Ibid., pp. 282-283 (paras. 208-209).
註21
日本の法的立場について外務省ウェブサイト(註2)は、日本が中間線まで「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を適用していることについて、「・・・中間線以遠の権原を放棄したということでは全くなく、あくまでも境界が画定されるまでの間はとりあえず中間線までの水域で主権的権利及び管轄権を国際法に従って行使するということである」と説明している。
註22
この論点について検討しているものとして、British Institute of International and Comparative Law (BIICL), Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83 (3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas (BIICL, 2016), pp. 29-31.
3.国際裁判による解決の可能性
自制義務が問題となった3つの事件は、国際裁判所が海洋境界画定を行うとともに、それ以前の双方の活動についても判断を下したものである。東シナ海の海洋境界画定紛争についても、このような国際裁判所による紛争解決はありうるのであろうか。国際紛争は双方の合意がなければ国際裁判所に付託することができないのが原則であるが、国連海洋法条約には同条約に関する紛争を最終的に裁判によって解決することを義務づける紛争解決手続が設けられている。南シナ海における中国の海洋主張をめぐって2014年にフィリピンが中国を訴えた事件は国際的な注目を集めたが、当該事件もこの手続を利用したものである23。国際裁判所の判断は、これを執行する手段が存在しないという限界はあるものの、自国の主張の正当性を示し、国際世論を動かすことによって外交的圧力をかける手段にはなる。
もっとも、国連海洋法条約は義務的な紛争解決手続を設けているものの、一定の紛争については受け入れないことを宣言することを認めている(298条)。そして、その1つに「海洋の境界画定に関する第15条、第74条及び第83条の規定の解釈若しくは適用に関する紛争」が挙げられている(同1項(a))。日本はこの宣言を行っていないが、中国と韓国はこの宣言を行っている24。そのため、両国との間のEEZ・大陸棚の境界画定を求めて一方的に国際裁判所に提訴することはできない。しかし、相手方が抗議にもかかわらず境界未画定海域における一方的な開発活動をやめない場合など、自制義務の違反のみを取り上げて紛争を付託することができないかについては、議論の余地がないわけではない。国連海洋法条約74条3項・83条3項に規定されている自制義務に関する紛争は「第74条及び第83条の規定の解釈若しくは適用に関する紛争」には該当しそうであるものの、「海洋境界画定(そのもの)に関する」紛争ではないとの主張が成り立つ余地がないとはいえないためである。ただ、このような主張が試みられた例はなく、具体的に検討した国際判例は存在しない25。
なお、義務的な紛争解決手続の適用を除外する宣言が存在する場合でも、境界画定紛争に関する紛争が生じ、当事者間の交渉によって合理的な期間内に合意が得られない場合にはいずれかの当事者が一方的に調停に付することができることになっている。しかし、この調停には法的拘束力がなく、実効的な解決は期待しにくいことから、今まで活用された例はオーストラリアと東ティモールの間のティモール海をめぐる紛争の1件にとどまっている26。
註23
この事件については、西本健太郎「南シナ海仲裁判断の意義―国際法の観点から」『東北ローレビュー』4号(2017年)15-52頁参照。
註24
China – Declaration under Article 298, 25 August 2006, Law of the Sea Bulletin, No. 62 (2006), p. 14; Republic of Korea - Declaration pursuant to Article 298, 18 April 2006, Law of the Sea Bulletin, No. 61 (2006), p. 14.
註25
ただし、後述のティモール海調停において、298条1項(a)で除外された紛争を扱う調停委員会が過渡的期間における取極に関する問題を自らの権限内であると判断した例がある。Timor Sea Conciliation (Timor-Leste v. Australia), Decision on Australia’s Objections to Competence (19 September 2016), paras. 93–97.