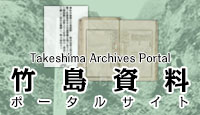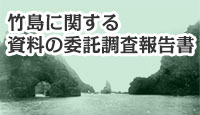本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
他国の主張分析
韓国の社会科教育課程の変化
2018年改訂社会科教育課程の科目に変化はないが、中学「歴史」と高校「韓国史」の竹島問題の記述は簡略化され、現代史部分の記述はなくなるという内容の変化が見られた。2022年改訂社会科教育課程では、中学「歴史」で竹島問題を扱わなくなり、中学「社会」〈地理領域〉の竹島問題の記述はさらに簡略化した。高校「韓国史2」の竹島問題に関する記述は現代史部分のみになった。2015年改訂社会科教育課程の「独島については領有権問題ではなく歴史問題として接近しなければならず」という方針と矛盾するが、理由は不明である。
小学校「社会」での竹島問題の記述は、2015年改訂社会科教育課程の「⑻統一韓国の未来とグローバル社会の平和」の単元から、2022年改訂社会科教育課程の「⑴我が国国土旅行」という韓国の自然環境を説明する単元に戻された。この単元の学習目標は実務的な色彩が強く、2015年改訂社会科教育課程の、竹島問題を素材に朝鮮半島の未来を考えさせる色彩は薄い。2015年改訂社会科教育課程では6回も使われた「固有の領土」という語句が、2022年改訂社会科教育課程では消えたことも、変化を物語っている。「固有の領土」とは、「一度も他の国の領土になったことがない領土」という意味である(2017年告示の小学校学習指導要領解説)が、「だんぜん自国の領土だ」と強調する時にも用いられる。これは韓国でも同様であろう。
2022年改訂社会科教育課程の高校「韓国地理探求」には、「領土教育の目標は、我が領域に対する正確な理解と国土愛の涵養であり、学習の結果が周辺国に対する嫌悪、あるいは漠然とした反日、反中感情に帰結しないようにする」という指導方針がある。これも、実務的な内容を重視する小学校「社会」の扱いの変化に通じるものがある。
おわりに
次は、韓国の社会科教育課程で竹島問題を扱った科目の一覧である。
| 1997年改訂 | 中学「国史」、高校「韓国近現代史」 |
| 2007年改訂 | 中学「社会」〈地理領域〉、高校「韓国地理」 |
| 2010年改訂 | 中学「社会」〈地理領域〉、中学「歴史」、高校「韓国地理」、高校「韓国史」 |
| 2011年改訂 | 小学校「社会」、中学「社会」〈地理領域〉・〈一般社会領域〉、中学「歴史」、高校「韓国史」、高校「東アジア史」 |
| 2015年改訂 | 小学校「社会」、中学「社会」〈地理領域〉、中学「歴史」、高校「韓国史」、高校「東アジア史」、高校「韓国地理」 |
| 2018年改訂 | 小学校「社会」、中学「社会」〈地理領域〉、中学「歴史」、高校「韓国史」、高校「東アジア史」、高校「韓国地理」 |
| 2022年改訂 | 小学校「社会」、中学「社会」〈地理領域〉、高校「韓国史2」、高校「韓国地理探求」 |
日本の学習指導要領およびその解説で竹島問題の記述が増加したことに対応したと思われるが、韓国の2010・2011年の改訂社会科教育課程で竹島問題を扱う科目と記述は増加し、2015年改訂社会科教育課程でそれは最大になった。ところが、2018・2022年改訂社会科教育課程では、竹島問題の記述の簡略化と扱う科目の減少が見られた。
この変化を見ると、韓国の「独島教育」に一貫した戦略は感じられない。一方で能動的な学習態度を求める方針に変化はない。2022年改訂社会科教育課程の小学校「社会」にも、「独島をカバーするさまざまな情報を探索するために独島に関連する機関のウェブページを活用できる」とある。日本はこの方針に対応して多言語の主張発信を強化し、韓国の児童・生徒へのその浸透を図るべきである。
日本の主張発信の柱は、17世紀の幕府公認の下での竹島の利用、1905年の島根県編入とその後の継続的な行政権の行使、それらをふまえてサンフランシスコ平和条約で竹島が日本領であることに変化はなかったという、三つの根拠である。韓国にこれらに優越する根拠はない。とりわけ、サンフランシスコ平和条約は重要であり、学習指導要領解説での説明は不可欠である。