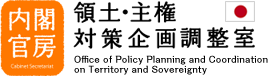本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
他国の主張分析
コラム 現代国際社会における外交上の抗議と国際裁判への付託提案がもたらす法的効果 韓国による『不法占拠』の長期化は国際法上いかなる法的効果も生じない
中野 徹也 (関西大学法学部教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
「不法占拠」が続けば「有効支配」に転換することはあるのか?
竹島が韓国に不法占拠されてから60年以上の月日が流れている。この間、日本は、1954年、1962年及び2012年に、韓国に竹島問題を国際司法裁判所に付託することを提案した。 また、再三再四文書または口頭により抗議を行ってきているが、韓国は、反発を強め、不法占拠を既成事実化する行動に出るばかりであり、いずれも功を奏していない。
膠着状態が続くなか、日本の対応の効果を疑問視するむきもある。すなわち、日本による措置は、外交上の抗議のみであり、強制力を伴っていないため、いわば「ペーパープロテスト」に終わっているのではないかという疑問である。このような外交上の意思表示程度の消極的措置のみでは、第三国から見れば、日本は韓国による竹島領有を黙認したとみなしかねない。 その結果、本来は、日本が竹島に対して主権を行使するに足る根拠(=領域権原)を有しており、韓国による占拠は「権原なき占拠」(=不法占拠)だが、不法占拠が長期化する一方で、日本がこのような状況を実際に変更するための措置をとれなければ、領域権原が移転し、「権原にもとづく占有」(=有効支配)になってしまうことが懸念されているのである。
領域権原としての「時効」
確かに、国際法上、他国による継続的な占有によって領域権原が他国に移転することが認められた事例がまったくないわけではない。たとえば、伝統的な領域権原の一つである時効は、その根拠になりうる。 時効は、国家が他の国家の領域を、①主権者として、②平穏かつ中断することなく、③公然と、④一定期間占有することによって成立するとされる占有は、「主権者として」、つまり国家機能の表示を伴う行為により行われなければなければならない。私人による活動だけでは足りない。 また、占有は、「平穏かつ中断することなく」、つまり他の国から抗議されることなく、継続して行われなければならない。かかる占有は、必然的に「公然と」行われることになる。期間については、「50年」と定めた条約(1897年の英・ヴェネズエラ条約)もあるが、一般には①~③の要件がみたされたとき、④の要件が満たされると解されている。したがって、各事案の事実関係により、期間は異なる。このように、国内法上の時効制度とは異なり、一般に適用可能な期間が設定されていないこと、それが国際法上の時効制度の特徴である。
時効は、「他の国家の領域」を対象としていることから、「無主地」を対象とする先占とは区別される。行為の瑕疵(かし)が、権原保有国の同意により治癒され、それにより国際秩序と国際関係の安定性が維持される。多くの論者は、ここに領域権原として時効が存在する意義を見出してきた。
「時効」の中断事由―国際裁判への付託「提案」の効果」
上記のように、「平穏」とは、他の国からの抗議が一定期間なされていない状態をさす。抗議をしていないことによって、権原保有国は、無権原で占有を行っている国が権原を有することに同意したものとみなされる。 その結果、第三国に対しても有効な絶対的な権原となる。したがって、他の国の猛反対にあいながら、実力により占有が維持されているような場合には、「平穏」とはみなされない。
同意の推定を覆す、すなわち時効を中断させるには、外交経路を通じた抗議を行うだけで足りるといえるだろうか。現代国際社会においては、国際連合への付託や国際司法裁判所に訴えるといった国際紛争の解決手段が存在するので、外交経路を通じた抗議だけでは不十分であり、あらゆる手段を尽くさなければ時効は中断しない、という見方と対比しながら、この点を検討してみよう。
まず、時効の中断事由について検討した20世紀初頭の古い国際裁判例を見てみよう。
エル・チャミザルと呼ばれる土地の帰属をめぐって、アメリカとメキシコとの間で発生した紛争で、両当事国の合意により紛争の解決を付託された国際国境委員会は、次のように述べている。 「国内私法上、時効の中断は訴訟の提起によりもたらされる。しかし、国家間の関係においては、かかる目的のために、国際裁判所が設立されない限り、不可能である」。 また、メキシコが実力で係争地域を占拠しようとしなかったことについて、「そのようなことを試みれば、凶行を引きおこしていただろう。外交文書により抗議を行うという控えめな形式に依拠したからといって、メキシコに責めを負わせることはできない」とも言う。 こうして、メキシコは抗議により、しかるべきことをすべて行っており、また国際国境委員会が活動を開始してから、妥当な期間内に請求を提起していることから、時効は成立しないとされた。本裁定は、1911年に下されているが、当時、武力行使禁止原則は確立しておらず、征服は有効な権原と考えられていた。 それでも、上記のような「何がしかの強制的な抵抗行動をとる必要」を認めなかったことは注目に値する。当時でさえ、「凶行を引きおこさせない」ために、実力を行使せず、抗議にとどめておいた場合でも、時効が中断しうると考えられていたのである。
もっとも、常設国際司法裁判所の設立以降、少なくとも同規程当事国については、「訴訟の提起」が、非当事国については第三者機関への付託が時効の中断事由となり、抗議を繰り返すだけでは時効の成立を妨げることはできないと解しうる裁定とも言える。 「訴訟の提起」を時効の中断事由とすることは、国家間関係では「不可能」であるとしつつ、「国際裁判所が設立されない限り」との条件が付けられていることや、国際国境委員会という紛争解決機関への請求提起を時効が成立しない根拠の一つとしてあげているからである。
いずれにしろ、少なくとも第三者機関への付託が時効の中断事由になるという点では、学説・先例は一致している。しかし、これを時効中断の不可欠の要件とすることには、躊躇いを禁じ得ない。時効を中断させるには、同意が推定されなければ足りるのであるから、外交経路を通じた抗議により、その旨を知らしめれば足りる。 仮に、時効を中断させるには、「必ず」常設国際司法裁判所や国際司法裁判所などの国際裁判所へ紛争を付託しなければならないとすれば、他方の当事国が合意しなければ、裁判が開かれる可能性がないにもかかわらず、常に単独提訴を強いられることになる。 領域紛争の場合、自国領を不法に占拠された国は、相手国からの同意を得ることができない又は近い将来得られる見込みがない状況で、訴状を作成しなければならなくなる。これでは、一方の当事国にのみ、過大な負担を課すことになってしまう。これは、国際司法裁判所でさえ義務的管轄権が十分に確立していない国際社会の現状をまったく無視した見解であり、妥当でない。 百歩譲っても、時効の中断のためには、国際裁判への付託の「提案」で足りる。他方当事国への権原移転に同意していないことが明らかになるからである。