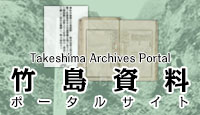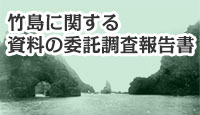本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
総合的論点
4 米英共同草案の作成
英国は、米国とは別に対日平和条約草案を作成していた。英国の草案では地図上に日本の領土的範囲を示す線を引き、1951年2月草案は竹島をその中に入れていたが、同年3月の第二次草案及び4月7日付けの暫定草案(Provisional Draft of Japanese Peace Treaty)10 では竹島を線の外に置いた(第1条)。また、当該4月7日付け英国草案は、第2条で朝鮮の放棄を規定していた11。
1951年4月から5月にかけて、ワシントンで米国務省と英外務省の協議が行われ、5月3日付けで米英共同草案(Joint United States-United Kingdom Draft of Peace Treaty)12 が作成された。米英共同草案においては第2条で、「日本国は、朝鮮(済州島、巨文島及び欝陵島を含む。)、〔台湾及び澎湖諸島〕に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。(以下、委任統治…)」とされた。米英協議において、米国は、日本の周りに連続した線を巡らすと日本を檻の中に囲い込むように見えるという心理的不利益を指摘し、英国は(上記英国案第1条の)提案の取り下げに同意した13。また、米英協議では、日本が主権を放棄する領土だけを挙げることが好ましい旨双方が合意し、この関係において(in this connection)米国案第3条に済州島、巨文島及び欝陵島の3島の挿入が必要である、ということになった14。斯くして、米英共同草案においても、竹島が日本領であるとの認識が維持された。
1951年6月のダレス訪英による調整を経て6月14日付けで改訂米英草案(Revised United States-United Kingdom Draft of a Japanese Peace Treaty)15 が作成された。朝鮮放棄条項は、「第2条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」となった。
註10
2月草案:英国国立公文書館TNA, PRO: 外務省記録FO371/92532, FJ1022/97, p.58-; 3月草案:TNA, PRO: FO371/92535, FJ1022/171, p.70-; 4月草案:TNA, PRO: FO371/92538, FJ1022/222, p.14-.
註11
「日本国は、ここに、朝鮮に対する主権主張並びに朝鮮におけるすべての権利、権原及び利益を放棄し、かつ、朝鮮の主権及び独立に関して国際連合がとり又はその後援でとられるすべての措置を承認し尊重することを約する。」
註12
Foreign Relations of the United States 1951, Vol.6, p.1024-.
註13
Japanese Peace Treaty: Working Draft and Commentary Prepared in the Department of State (June 1, 1951) 中5月3日草案第2条に関するニュージーランドの意見への国務省コメント,Foreign Relations of the United States 1951, Vol.6, p.1061.
註14
Anglo-American Meetings of Japanese Peace Treaty, Summary Record of Seventh Meeting held at 10.30 a.m. on the 2nd May, in Washington 中、米国案第Ⅲ章、TNA, PRO: FO371/92547, FJ1022/376, p.66.
註15
Foreign Relations of the United States 1951, Vol.6, p.1119-.
5 韓国政府の修正要請と米国による否定
1951年7月19日、梁裕燦(You Chan Yang)駐米韓国大使がダレスを訪ね、政府の訓令により、改訂米英草案の修正要請に係るアチソン(Dean G. Acheson)国務長官あて文書を手交した。 第2条(a)に対する修正要請は、“放棄する”を“朝鮮並びに済州島、巨文島、欝陵島、ドク島(Dokdo)及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する”に改めるというものであった16。
これに対し、米国のラスク(Dean Rusk)国務次官補は国務長官に代わり、同年8月10日付け文書で次のとおり述べて韓国の要請を退けた。曰く、「合衆国政府は、遺憾ながら当該提案に係る修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。ドク島または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年ころから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」17
改訂米英草案の規定は、そのまま条約第2条(a)となり、大戦後も竹島の日本領土としての地位に変動のないことが確定した。
註16
NARA, RG59, Lot54 D423, Japanese Peace Treaty Files of John Foster Dulles, Box 8, Korea. また、Foreign Relations of the United States 1951, Vol.6, p.1206.
註17
NARA, RG59, Lot54 D423同上。また、Foreign Relations of the United States 1951, Vol.6, p.1203, f.n.3.
6 現今の韓国の主張とその当否
以上のことは史実であり、本来“反論”の対象とはなり得ないところであるが、韓国においては今日次のような主張が行われている18 。
連合国総司令部は、日本占領期間中、独島を鬱陵島とともに日本の統治対象から除外される地域と規定した連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677号(1946.1.29)を適用した。総司令部が独島を日本の領域から分離して取り扱ったのは、日本が「暴力と貪欲によって略奪した」領土を放棄することを明示したカイロ宣言(1943年)およびポツダム宣言(1945年)等によって確立された連合国の戦後処理政策に従ったものである。すなわち、独島は、日本が露日戦争中に暴力と貪欲によって奪ったものとして日本が放棄すべき韓国の領土であったのである。
1951年9月に締結されたサンフランシスコ講和条約も、このような連合国の措置を継承した。したがって、講和条約に独島が直接的に明示されはしなかったが、日本から分離される韓国の領土に独島は当然含まれていると見なければならない。独島よりもっと大きい無数の韓国の島々も一つひとつ摘示されることはなかった。韓国のすべての島を条約で挙名することはできなかったからである。
また、日本が独島領有権の根拠として掲げる「ラスク書簡」は、連合国全体ではない米国だけの意見で、独島領有権を決定することにいかなる効力も有しない。
この主張は、事実関係からも法的観点からも成り立たない。まず、1946年1月の総司令部覚書SCAPIN-677は竹島を占領下日本政府の施政範囲から除いたが、それは占領統治の目的上の措置であり領土の処分ではなかった。SCAPIN-677自体が「この指令中の条項はいずれもポツダム宣言第8項にある諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない(第6項)」と断っていた。領土の処分は平和条約で行われた。そもそも竹島は、韓国の領土であったことがない――韓国においては今日、韓国の古文献・古地図に登場する「于山(島)」が竹島であり歴史的に韓国領であった等の主張が行われるが根拠薄弱である19。韓国が竹島を実効的に占有した証拠も提示されていない。日本が奪ったという主張は前提(韓国領であったこと)を欠く20。
次に、条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従って解釈される(条約法に関するウィーン条約31条参照)。この方法で得られた意味を確認するため又はこの方法による解釈では意味が曖昧若しくは不明瞭である等の場合に意味を決定するため、解釈の補助的手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる(同32条参照)。対日平和条約第2条(a)にいう朝鮮の“文脈・趣旨に従った通常の意味”は、1910年に日本に併合された朝鮮ということであり、竹島を含まない。この用語の意味は、なお必要であれば、前記2から5でみた“準備作業”により確認され、決定される。「独島より大きい無数の韓国の島々」は“朝鮮”の語に含まれるので元々列挙されることはないし、「ラスク書簡」は、(米国だけの意見でないことに加え)条約の準備作業として大いに意義を有するのである。
註18
東北アジア歴史財団編『日本の虚偽主張 独島の真実(일본의 거짓 주장 독도의 진실)』2019.9, 20-21頁(最終アクセス2020.2.5)。
註19
詳細は、塚本孝「竹島領有権をめぐる韓国政府の主張について」『東海法学』52 (2016.9) 62-86頁参照。
註20
なお、初期の国務省草案や英国草案の竹島除外には、SCAPIN-677が影響した可能性がある。そのSCAPIN-677には“マッカーサーライン”の前身である1945年9月27日付け米国第5艦隊司令官覚書80号(川上健三『戦後の国際漁業制度』大日本水産会, 1972, 54-55頁に原文収録)が影響したと考えられる。覚書は、9月26日の日本政府の要請に応え一定水域内での漁船の操業を包括的に許可したものであるが、日本海の水域設定に際し対馬の北端と日本海中央北緯40度東経135度の地点を直線で結んだ結果、竹島が線に掛かった。回答が申請の翌日であることから機械的に線を引いたことが分かる。SCAPIN-677の竹島除外は、竹島を日本が略取した地域であると連合国が判断した結果ではない。