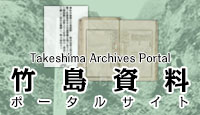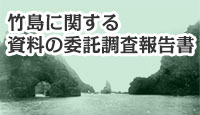本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
他国の主張分析
コラム 韓国における「独島」の研究と教育─その史的な前提
永島 広紀 (九州大学教授)
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。インストールされていない場合は、こちらよりダウンロードしてください。
はじめに
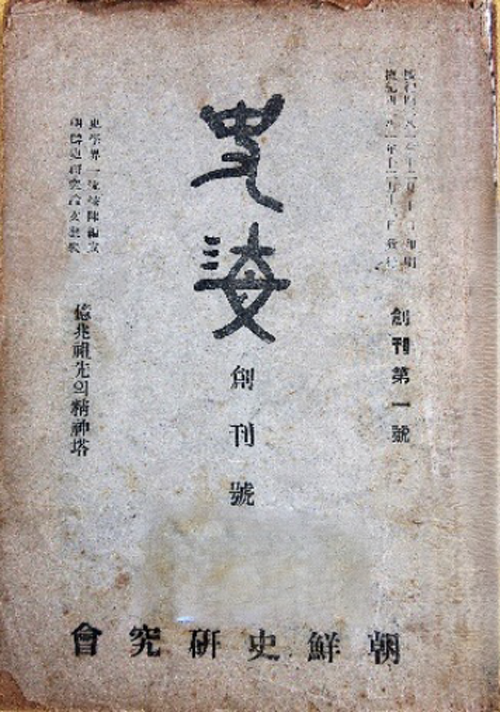
韓国における「独島」に関する初の本格的な学術研究としてしばしば言及、ないしは引用されるものに申奭鎬(シン・ソッコ、1904-1981)による「獨島所屬에對하여(独島の所属について)」という論文がある。この論文は「朝鮮史研究会」を名乗る韓国史研究者の集まりが学術誌として1948年12月に刊行した『史海』誌の創刊号に掲載されていたものである。
同誌は第2号までの発刊で終わってしまったとされるが、くだんの「朝鮮史研究会」の「主幹」には李丙燾(イ・ビョンド、1896-1989)なる、当時の韓国における歴史学会の重鎮の名が掲げられているところから、これに先立つ米軍政下において軍政庁から歴史教科書の編纂を委嘱されていた「震檀学会」(1934年5月設立)の、言わば歴史学系の別働組織と言って差し支えない。
さて、この申奭鎬によって書かれた論文は、「独島」の領有に関して、まずは「李朝実録(朝鮮王朝実録)」をはじめとする官製の「編年記録」(ただし実録は各代国王の薨去後に編纂されるものであり、リアルタイムの記録ではなく、常に潤色・改変される可能性がある)に依拠しつつ、いかに韓国が古来より独島を領有していたかを証明しようとする、手法としてはきわめてオーソドックスなものであった。また、引用している学術論文やデータ類はほぼ日本側のものが利用されているところからも、まさに「1945年」以前の学術的成果を下敷きにしたものであった。
すなわち、日本統治下の朝鮮においては、まず初代総督である寺内正毅のイニシアティブの下、広範囲・高精度の「旧慣調査」と「古蹟調査」が実施された。その結果、旧王朝時代に作成され、地方各地の「史庫」に分散されて保管されていた各王代の「実録」をはじめとする大量の公的記録物が京城(ソウル)に集められた。そして、旧王宮である景福宮内の「参事官分室」での整理を経て、やがて京城帝国大学附属図書館の特殊コレクションとしての「奎章閣」に収められた。今日、韓国側が「独島(竹島)」領有における有力な根拠史料の一つとする「世宗実録地理志」は、第4代国王である世宗(位:1418-1450)の薨去後に編纂された実録の、さらにその付録物となる。なお、1930年から32年にかけて京城帝国大学法文学部のスタッフが中心となって、第25代国王までの実録を「李朝実録」として影印して848冊×30セットの複製版を作成し、各大学等に頒布したことから、以降、李朝時代に関する学術研究が飛躍的に精緻なものとなった。
後述する通り、京城帝大史学科の卒業生(1930年3月)であり、卒業直後から朝鮮総督府の修史スタッフを長く務めた申奭鎬は、こうした歴史資料に直にアクセスすることができる立場にあった。よって『史海』誌の論文においても、歴代国王の実録以外にも「日省録」「承政院日記」「新増東国輿地勝覧」「同文彙考」といった、現在でも学術研究の場で用いられている奎章閣(現:ソウル大学校奎章閣韓国学研究院)所蔵の基礎史料が掲げられるとともに、「恩師」たる田保橋潔教授の論文をはじめとする日本側の研究や地誌を多く引用している。彼の『史海』論文におけるその立論は、まさに1945年以前の諸成果を土台としたものであった。
1. 朝鮮総督府学務局の「朝鮮史」教育
通常は、特に何らの根拠も示されないまま、日本統治期の朝鮮においては「朝鮮の歴史」は抹消され、なんら教育も行われなかったかのようなイメージや言説が先行しがちであるが、それは完全に誤りである。むしろ、史料に基づく綿密な編年作業を踏まえた上で、時代区分を施し、あるいは政治史・経済史・文化史といったテーマ毎の「朝鮮通史」を描き、教科書を通じてこれを普及していこうとする試みは、やはり朝鮮総督府によって主導されたのは、紛れもない事実である。
その中心にあったのは、小田省吾(1871~1953)という学務官僚である。小田はまだ「帝国大学」が一つしかなかった時代にその「文科大学・史学科」にてドイツ流の実証史学を学んだ世代である。そして、第一高等学校教授の身分を持ったままで当時の大韓帝国に派遣され、主として教科書の作成に携わっていた人物である。
韓国併合(1910年8月)後も、引き続き朝鮮総督府に学務局編輯課長として勤務する傍ら、官員や教師による学術組織を作ることに腐心し、特に1920年代に入ってからは「朝鮮史学会」の名の下にまずは月刊の『朝鮮史講座』(1~15号、1923.09~1924.11)を刊行し、朝鮮各地の学校教員に対して「朝鮮史」教育の指針を示していた。
そして、小田は1924年度に開設される「京城帝国大学」の予科部長を兼務し、次なる段階での朝鮮史教育の在り方を模索していくことになるが、その一つの結晶が、予科開設から2年後の1926年度から開講される大学本科における「法文学部史学科」、さらにその専攻の一つとして置かれた「朝鮮史学」であった。
2. 京城帝国大学法文学部史学科・朝鮮史学専攻
新設された京城帝大においては法文学部内に2講座分の「朝鮮史学講座」が確保され、開設時の第一講座には小田省吾、第二講座には古代史を専門とする今西龍がそれぞれ教授として配置された。ただし、小田はまもなく1931年度には停年を迎え、翌1932年に今西龍が在職中に逝去したことを承け、第一講座は末松保和、第二講座担当は考古学・古代史を専門とする藤田亮策という体制に移行し、そのまま1945年8月に至っている。
一方、京城帝大においては、朝鮮史学講座の教員以外にも、「朝鮮研究」を手掛ける者が多く、それは法文学部の文科系講座のみならず、法科にも波及し、さらには医学部の一部教員(例えば、戦後日本の「竹島」地図研究にも足跡を残した中村拓は医学部教授〔医化学講座〕であった)すら巻き込むものであった。
特に、国史学第一講座教授の田保橋潔(1897~1945)は、幕末維新期の対外関係史を専門とする日本史研究者であったが、朝鮮のみならず欧米の外交史料を用いた近代の日韓関係史にその研究的な関心を拡げていた。さらには、後述する「朝鮮史編修会」が手掛けていた『朝鮮史』編纂も、その事業の後半(すなわち近代史の領域)に入ると事実上、田保橋が主宰する形となっていた。そして、「竹島」にまつわる名称変遷に関して東西の史料を博捜しての実証的な論文(『青丘学叢』3号・4号、1931年)を最初に執筆したのは、まさに田保橋潔であり、申奭鎬の既出論文もこの田保橋の論考をベースとする内容である。
3. 朝鮮史編修会から国史編纂委員会へ
さて、朝鮮史編修会についてである。当初は大韓帝国末期に実施されていた不動産法調査・法典調査の流れから、この業務を継承した朝鮮総督府「取調局」および「参事官室」によって旧王朝の各種記録類が京城(ソウル)に集約され、図書番号を付して目録化を行う「図書整理」が「旧慣制度調査」の一環として時期的に先行して実施されていた。
この参事官室はまもなく廃止され、1915年5月には「中枢院」(元来は朝鮮人側の有力者で組織された朝鮮総督府の諮問機関)へ旧慣制度調査にまつわる事業は移管されることになった。この際、中枢院の事業として「朝鮮半島史」の編纂が開始(1915.01)されていたのであるが、この編纂事業は法務官僚が担当していたこともあり、同じく参事官室から別途に「古蹟調査事業」を継承していた学務局側との間で「修史」をめぐる主導権争いが惹起されるなか、最終的には中断してしまっていた。
これが、「三・一独立運動」(1919年)の後、いわゆる「文化政治」の開始とともにあらためて朝鮮史編纂委員会が組織され(1922.12)、さらにこの事業を推進するために官制化されたのが「朝鮮史編修会」(1926.06)であった。
そして、この朝鮮史編修会の主要業務として位置づけられる『朝鮮史』の編纂と刊行が1932年から1938年にかけて実施され、また関連史料の収集と整理も併行して行われていた。これはすなわち、明治期の「大日本編年史」編纂に端を発する『大日本史料』に範をとった編年史料集としての『朝鮮史』を編纂したものであった。
さて、こうした史料編纂の実務を担ったのは「修史官」「修史官補」「書記」「嘱託」といった職階にあった専門官吏たちであった。当初は内藤湖南の薫陶を受けた満鮮史研究の稲葉岩吉(君山)が中心となり、さらに東京帝大「国史学科」出身の藤田亮策・中村栄孝・末松保和が登用されていた。やがて卒業者を出していくことになる京城帝大史学科朝鮮史学専攻の出身者(申奭鎬・田川孝三ら)が順次に採用されていった。また、短期間ではあるが、早稲田大学出身の李丙燾も修史官補として勤務しており(1925.08~1927.05)、退官後も嘱託として修史事業そのものには従事しつづけていた。
なお、『朝鮮史』編纂の終了と前後して稲葉は満洲・建国大学教授に転出(1937年)、また末松保和はすでに京城帝大助教授へ(1935年)、中村栄孝は朝鮮総督府学務局の編修官(国定教科書の編纂業務)にそれぞれ異動しており、申奭鎬こそが戦時下の朝鮮史編修会においては先任の修史官として会務を切り盛りする立場にあったのである。
おわりに
「解放」後、朝鮮史編修会は米軍政下で「国史館」として再出発することになるが、その中心となったのが、他ならぬ申奭鎬である。そして、この国史館は1949年7月に文教部傘下の「国史編纂委員会」に改編され現在に至っている。
韓国では1947年より1973年まで「検定」(一部の科目は国定も併存)「歴史(国史)」教科書が使用されていたが、1974年より「国定」に移行していた。さらに、1982年夏に発生したいわゆる「教科書問題」の前から燻っていた「検定」制への再移行問題が紛糾する中、国史編纂委員会に置かれる「1種図書開発委員会」の名義によって「検定」教科書が発行されはじめることとなった。ただし、各科教科書は中高ともに「1種のみ」であり、これは実質的な国定教科書であった。異なるのは執筆を行うのが文教部の編修官ではなく、国史編纂委員会の委嘱を受けた現場の大学教員や中高教員であったところであった。
かくして、韓国における歴史教科書編纂とは「国家としての正統な歴史」、すなわち「国史」が叙述される場そのものとなっていったのである。そして、その淵源を少し辿りさえすれば、すぐに日本統治期の朝鮮における修史事業と歴史教育との関係に行きつくのである。