 |
日時:2025年1月20日(月)
13時30分-16時30分
会場:ダイワロイネットホテル和歌山
定員:200名
主催:内閣官房国土強靱化推進室
共催:和歌山県、和歌山市、毎日新聞社
協力:紀伊民報
https://www.youtube.com/watch?v=B5B2lcY0O9U


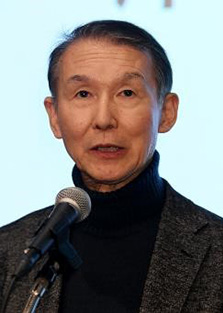

事前の防災対策が復旧・復興を早める

明らかになった半島地域の脆弱性

「津波犠牲者ゼロ」への挑戦

<モデレーター>








|
中林
|
まずは能登半島地震から何が学べるかを話し合えればと思います。 |
|
茶谷
|
能登半島地震では、半島特有の地理状況によって復旧復興が困難を極めました。土砂崩れなどにより、道路が寸断され、多くの集落が孤立しました。珠洲市などでは地震による隆起で使えなくなった港も多かったのですが、七尾港は使用することができました。また能登には空港もあります。これらのインフラを活用できていれば、さまざまな支援が可能だったのではないかと感じています。これは和歌山県にも通じる課題ではないでしょうか。 |
|
富田
|
和歌山県の沿岸部には三方を山に囲まれた地形に港とともに数多くの漁村集落が形成されています。また、役場などの社会資本も集中しています。南海トラフ巨大地震が発生した場合、20メートルを超える津波が押し寄せるとされていますが、沿岸部には壊滅的な被害が及ぶことが想定されます。過疎と高齢化が進む状況を考えれば、支援や復興は容易ではありません。東日本大震災や能登半島地震の教訓を踏まえれば、被災後の混乱期にスタートする復興ではなく、発災から復興事業の各段階のスケジュール感を持った「事前復興」計画を準備しておくことが重要ではないかと考えています。 |
|
中林
|
事前復興というのは、平時から被災後の復興まちづくりを考えておくことです。平成7年の阪神淡路大震災をきっかけにクローズアップされてきた考え方であり、国土強靱化を考える上での重要なキーワードです。和歌山県田辺市でも事前復興の取り組みがなされていますね。 |
|
真砂
|
田辺市では東日本大震災をきっかけに事前復興計画を策定しました。災害に見舞われた際、市を三つの地域に分けて復興する、という計画です。多くの歴史文化資源を有する中部地域では、現地再建を目指します。西部、東部地域では高台への移転をベースに新市街地を整備していきます。被災後の混乱の中で復興計画を作ることは困難です。あらかじめ住民の理解を得ながら計画を作っておけば、復興のスピードは格段に速まると考えられます。 |
|
富田
|
私は東日本大震災後の漁村復興まちづくりに携わってきましたが、復興達成状況についての満足度が高い地域は、住民参加の度合いが高いように思います。事前復興の計画を作る際にも、住民との対話のプロセスを積み重ねていくことがポイントですね。 |
|
真砂
|
田辺市でも計画をまとめる上で、住民説明会を実施しました。事前の復興計画がほかの計画と違うのは、計画ができて終わりではないということです。まちづくりとともに変わっていくので、常に計画のブラッシュアップが必要です。 |
|
茶谷
|
被害を最小限に抑え復興に迅速に取り組むためにも事前復興は大変有意義ですね。 |
|
中林
|
能登半島地震は超高齢社会での災害でしたが、どんな課題が浮かび上がったでしょうか。 |
|
茶谷
|
超高齢社会という側面が被害を大きくしたように感じています。行政としては住民の皆さんに耐震化を呼びかけていたのですが、「子どもや孫がここに住むことはない」と考える人が多くいました。このことが家屋被害を拡大させたように思います。また、避難所でも高齢者ばかりだと共助の力が発揮できないという課題もありました。 |
|
神元
|
能登半島地震では、仮設住宅に移った高齢者の方が取り残されている状況が多く見受けられました。どこに買い物に行っていいか分からないし、その手段もない。支給された家電の使い方も分からず、2日間、真っ暗な部屋で過ごしていたお年寄りもいました。こうした方々には災害支援を行うNPOがきめ細やかに対応しました。 |
|
中林
|
超高齢社会では、地域の共助の力が低下するということですね。DX(デジタルトランスフォーメーション)の技術を活用することはできないでしょうか。 |
|
園田
|
私たちは全国40以上の自治体を支援し、防災を含むさまざまなDX推進に取り組んでいます。これまでに、避難所の人数把握や避難者のアレルギー情報管理の仕組み、津波シミュレーションデータを活用したデジタル避難訓練などの実証を行い、その可能性を模索してきました。データを活用して平時から備えておくことで、効率的な防災につなげられると考えています。 |
|
丹羽
|
日本に住んでいる以上、いつでもどこでも災害に備えなければいけません。国や自治体、民間の皆さんの力を合わせて防災対策を進めていく必要があります。 |
|
田中
|
皆さんのお話を聞きながら、大きな地震が来た時、自分がどう行動すればいいかを想像しました。一方で行政や民間団体、企業が連携している地域は心強いと感じています。 |
|
中林
|
まとめに移ります。国土強靱化とは、防災・減災対策であり、復旧・復興を早めるための取り組みです。今日のパネルディスカッションでは、被災後の迅速な復興には、事前復興という考え方がポイントになるという指摘がありました。また、超高齢社会においては、どう共助を実現していくかという課題も浮かび上がりました。こうした課題sに対しては、国という「官」、自治体という「公」、市民の「民」と民間事業者の「民」による「官・公・民・民の連携と連帯」が鍵になります。みんなでつながることで災害に強い日本を作り、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震に立ち向かっていきましょう。 |
 |
|