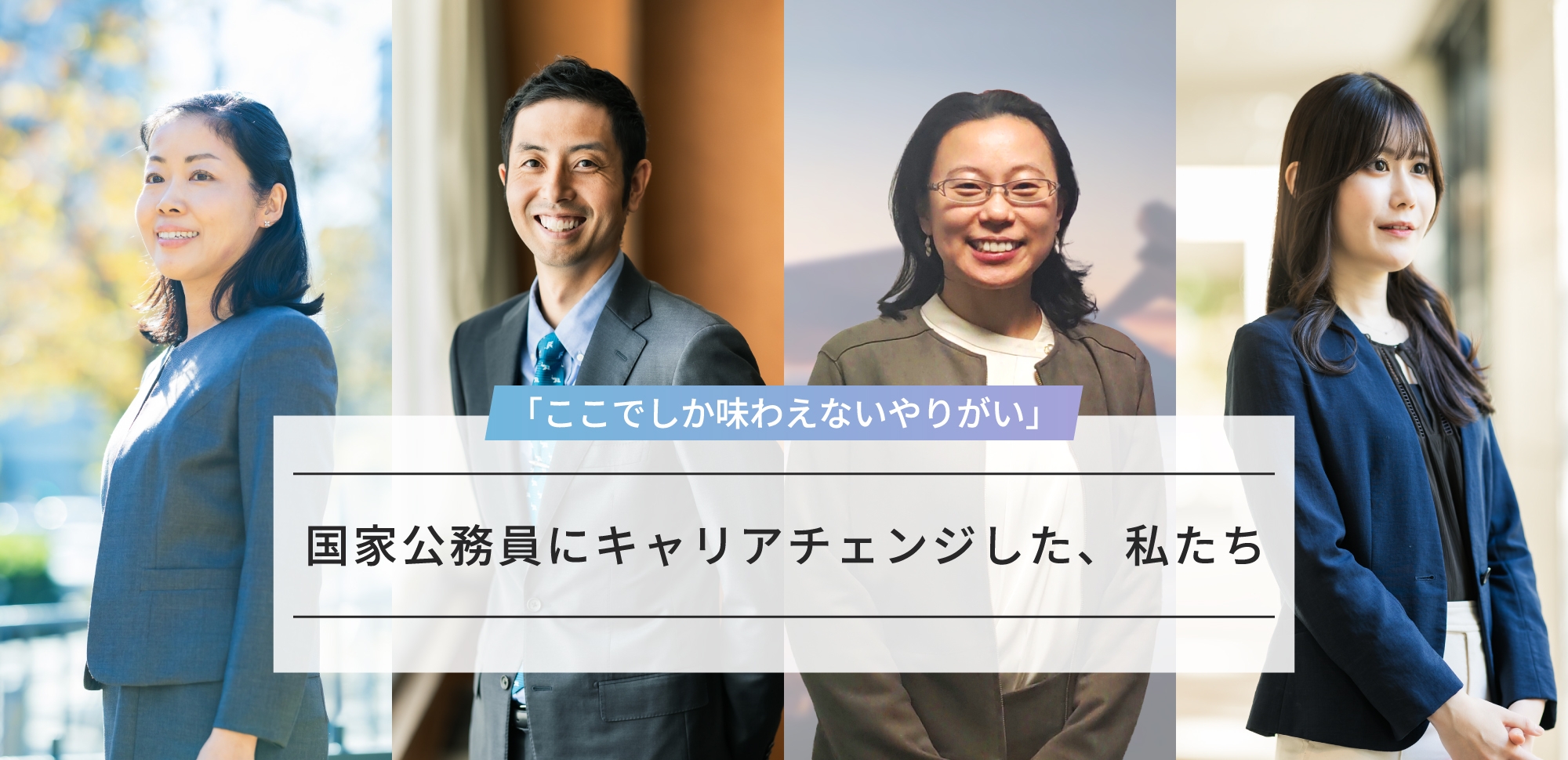


外務省
門 愛子
Aiko Kado

農林水産省
山田 大樹
Daiki Yamada

防衛省
小川 修子
Shuko Ogawa

内閣府
片山 啓
Kei Katayama
※各職員の所属は2025年3月時点
CASE:01
外務省
門 愛子
Aiko Kado
国際機関→外務省
Question01
前職ではどのような仕事に携わっていたか教えてください

門
私は、国際連合開発計画(UNDP)にて、3年間ジュニアプロフェッショナルオフィサー(JPO)を務めた後、欧州復興開発銀行(EBRD)のAgribusiness チームにて、Technical Cooperation Managerとして、技術協力プロジェクトの立ち上げ及び管理を担当しました。UNDPでは、紛争の傷跡の残るコソボで北部ミトロヴィツアにおける民族融和プロジェクトの実施に関わった後、ニューヨーク本部に異動し、当時最大のドナーであった日本による対アフガニスタン支援の実施及び管理を担当し、3年目には国連に設立された信託基金の管理に携わる機会を得ました。EBRDでは、同行の中心的な業務である投融資プロジェクトに付随して組成される技術協力案件を、食糧安全イニシアティヴ(Food Security Initiative)の一環として、セルビアやウクライナ等で実施しました。

Question02
国家公務員を志望したきっかけや理由を教えてください
また、経験者採用試験の受験に向けてどのような準備をしましたか

門
私は、子供の頃から国際問題に興味があり、国際情勢に関わる仕事がしたいと漠然と考えていました。外務省の業務には大学在籍中から興味があり、フランス留学後にEU代表部でインターンをし、大学院在籍中には、専門調査員として在外公館で勤務する機会を得ました。その後、自分のやりたいことを更に模索したいと考え、民間企業に勤めた他、国際機関における勤務にも挑戦しました。外務省の中途採用試験を受けたのは、こういった様々な経験を通じて、日本の外交政策に携わり、日本の国益に資する仕事がしたい、という強い気持ちに、私自身が漸く気が付くことができたということがあると思います。
また、経験者採用試験の受験に向けての準備は、当時英国在住であったため、国家公務員試験の準備のためのテキストを日本から取り寄せ、朝いつもより早く起きたり、通勤時間やお昼休みの時間を使ったりして勉強しました。国際的な課題に対する日本の政策について、必ずしも日常的に接する環境にいなかったため、日本の新聞を読む等して情報収集をし、意識して日本の政策に対する自分の見解を考えました。今回が最後のチャンスという覚悟で、今真剣に勉強しなかったら一生後悔する、と自分に言い聞かせ、3~4か月の準備期間だったと思いますが、集中して真剣に取り組んだ記憶があります。

Question03
今携わっている業務について教えてください

門
私は2024年1月から国際法局経済条約課に勤務し、国際約束の締結業務に取り組んでいます。一例を挙げると、国際約束の締結に際し、日本の外交政策を適切に実現し、かつ、先方政府との交渉の結果を適切な文言に落とし込む業務や、締結済みの国際約束で必ずしも想定していない事態が起こったときに、その解決策を検討する業務等を行っています。また、新たな協定を作る際に法制局審査に臨み、訳文の作成という、ある種「職人芸」的な、私にとって新しい世界にも携わっています。条約その他の国際約束の締結並びにそれら国際法規の解釈及び実施を行う権限は、外務省が一元的に有しています。国際法の原則を理解し、それに沿った助言をすることは、時に重圧を伴いますが、それ故にこそ、先例等を読んだり、考えたり、教えてもらったりして、この一年は、毎日が未知の事案に取り組む勉強の日々でした。そのような中で、多様な考え方や各国の特殊事情に可能な限り寄り添いながら解決策を探ろうとする向き合い方は、在外勤務や地域課での勤務を通じて獲得したもので、適切な助言を模索する上で大きなアセットになっていると思っています。
Question04
国家公務員になって良かったことや国家公務員の魅力を教えてください

門
国家公務員になって良かった、と思うのは、志を同じくする上司、同僚、後輩たちとともに課題に取り組み、助け合い、どんな小さな一歩でも、日本の国益の推進に繋がっていると感じることができるからです。民間や国際機関とは異なる面も多いほか、強いプレッシャーの下に置かれたり、徹夜の交渉等、精神的にも肉体的にしんどい状況も経験したり、苦しいときもありました。しかし、外交の現場では、専門性や語学力のみならず、人間性が試される場面が多くあり、最後は人間同士の信頼関係が重要な役割を果たす局面があります。国境や文化を超えて共鳴し、人と人のつながりによって問題解決の糸口を見いだす現場に立ち会うことができるのも、この仕事の大きな魅力だと思います。私にとって国家公務員という職業は、中途採用ならではの多様なバックグラウンドを活かし、人としての総合力をもって、全身全霊で自らの使命に取り組むことのできる、「生き方」そのものと言えるのではないかと思っています。
CASE:02
農林水産省
山田 大樹
Daiki Yamada
総合商社、コンサルティング会社→農林水産省
Question01
前職ではどのような仕事に携わっていたか教えてください

山田
日本の食文化を世界に広めたいという思いから新卒で総合商社に入社しました。はじめに人事部で新卒採用や人材育成に3年間携わった後、営業部門に異動して果物のトレーディング、事業会社管理、食料市場開拓等に従事しました。中でも、タイの現地法人に赴任した際、世界中の果物や飼料、穀物、脱脂粉乳、畜産品等様々な商材の営業を担当し、新規案件の構築に携われたことは貴重な経験となりました。帰国後、コーポレート部門と営業部門を繋ぐ部署に異動し、与信管理、決裁管理、DX推進、脱炭素ビジネスの構築などに携わりましたが、自身の更なるスキルアップを目指し、スタートアップのコンサルティング会社に転職し、中途採用や人事企画を担当しました。

Question02
国家公務員を志望したきっかけや理由を教えてください
また、公募に応募するに当たってどのような準備をしましたか

山田
「食」の輸出を通して稼げる農林水産業を構築し、日本の生産者を支援したいと考え農林水産省を志望しました。海外で商談する度に日本産の「食」の人気の高さに驚かされる一方、物量やコストの問題から日本産品の輸出の難しさも実感し、もどかしい思いをしました。国内に目を向けると、人口減少や地方の過疎化等の諸課題が農家の生産量減少・所得水準の低下に繋がっています。これを解決するには、人口が増加している海外市場向けに輸出展開し、販売量を増やしていく必要があり、私のこれまでの海外営業での経験を活かせると考えました。
応募に当たって、農林水産省のHP上で現在の政策や今後の方針を確認したうえで、自分の考えや意見を整理するよう努めました。書類選考の小論文については、家族や友人に見せ、文章の構成から言い回し等細部に至るまで助言をもらい、作成しました。

Question03
今携わっている業務について教えてください

山田
私が所属する国際地域課では、東アジア、東南アジア、中東、大洋州、欧州との二国間交渉や二国間対話等を所掌し、各国の大臣や政務に対し、日本の農林水産物の輸出促進や規制緩和交渉、博覧会や展示会への招聘、農業や食料分野での相互協力の働きかけ等を行っています。私自身は欧州チームで、イタリア、フランス、スイス、デンマーク、フィンランド等のヨーロッパ諸国を担当しており、当該国に対し優先的に協議すべき案件などを省内の関係各所と調整し、農林水産省としての方針を取りまとめています。その他、二国間会談の成果文書や協力覚書の推敲にも携わったりしています。最近では、イタリアシチリア島のシラクーザという都市で開催されたG7イタリア農業大臣会合に随行し、合間で開催されたイタリアとの二国間会談に参加しました。その際、両国の農業大臣間によって「農業及び食料分野における協力覚書」へ署名されましたが、この協力覚書の内容も、私が推敲し、省内の関係部局や関係省庁と調整し、作り上げました。
Question04
国家公務員になって良かったことや国家公務員の魅力を教えてください

山田
民間企業での意思決定においては、獲得利益や発生コストがベースにあり、その中から実行可能性を模索していきますが、日本が抱える課題に対して真正面から向き合い、あるべき論から判断することができるのは国家公務員の魅力だと思います。
農林水産省には、畜産局、農産局、水産庁、林野庁、新事業・食品産業部など品目ごとに産業振興を行う組織と、そうした様々な品目を横断的に取扱い輸出促進、国際交渉、規制緩和、防疫等の政策を打ち出す組織が存在しますが、どの組織でどの業務を担うことになっても、入省当初に抱いていた思いでもある「稼げる農林水産業の構築」に向け、真正面から課題解決していくことができるため、今もなお心が躍るとともに、ワクワクが止まりません。
CASE:03
防衛省
小川 修子
Shuko Ogawa
防衛庁(当時)→米国企業→防衛省
Question01
前職ではどのような仕事に携わっていたか教えてください

小川
前職では、米防衛企業の日本支社において、今後の日本の防衛力整備・防衛政策の方向性を見据えた経営戦略の立案や事業開発を担っていました。それまで公務員しか経験のなかった私にとって、民間さらに外資企業での勤務は、新たな発見の連続でした。米国流の仕事のやり方(例:根回し等の過程よりも結果重視)や日米間の様々なギャップ(語学の問題にとどまらない日本人と米国人の間のコミュニケーションの課題)を目の当たりにし、文化や国を跨いだ効果的な仕事の進め方を学べたのは自分のキャリアにとって非常に有意義でした。公務員時代とはまた違った立場から、日米間の架け橋となり、日本の防衛や日米関係の強化に貢献できる仕事はやりがいもありました。

Question02
一度離職したものの、再度国家公務員を志したきっかけや理由を教えてください

小川
米防衛企業での勤務により、米政府・企業側の防衛装備品にかかる諸制度や取り組みに関する知見を得ることができたのは、他では得難い収穫でした。日本側から見た米企業との防衛装備協力にあたっての諸課題は、日米間の制度のミスマッチにも起因していることに気づかされ、日米双方の立場を経験した身として、より良い日米間のみならず日本と海外企業間の協力に貢献できるのではないかとの思いを新たにしました。同様に、民間企業で勤務したからこそ、よりその実情を踏まえた防衛産業政策の企画・立案にも貢献できると考え、再度防衛省を志しました。

Question03
今携わっている業務について教えてください

小川
我が国は、イギリス及びイタリアと次期戦闘機GCAP(Global Combat Air Programme)の共同開発に取り組んでいます。これまで主に米国と防衛装備協力を重ねてきた我が国にとって、欧州のしかも3カ国での共同事業は初の試みです。戦闘機の共同開発は、各国の優れた技術を結集し、コスト等を分担できるメリットがありますが、当然参加国政府・企業の意見を調整して事業を進める必要があります。事業の進め方を始め、予算や制度上の仕組みの相違などに直面しながら、担当間で真剣な議論を重ねて一つずつ課題をクリアしていき、事業の確実な推進に取り組んでいます。戦闘機の共同開発に共に携わるということは、今後何世代にもわたるイギリス及びイタリアとの幅広い協力の礎となることであり、その責任の重みを感じつつ日々業務に邁進しています。
Question04
国家公務員になって良かったことや国家公務員の魅力を教えてください

小川
昨今はよく「パーパス」の重要性が強調されますが、何のために働くのかという視点において、国家公務員は国のためという民間ではなかなか再現できない「パーパス」があります。もちろん民間も公務員も一長一短あり、個々人それぞれ向き不向きはあるでしょうが、両方の世界を経験した者が、それぞれの世界の長所を育み、必ずしも効率的でない短所を改善していくことができれば、より良い方向に進めるのではないでしょうか。
CASE:04
内閣府
片山 啓
Kei Katayama
地方公共団体→内閣府
Question01
前職ではどのような仕事に携わっていたか教えてください

片山
新卒就職の際、自分の生まれ育った地の様々な課題の解決や地域活性化に携わりたいと考え、地元の県庁に就職しました。当時は、震災や大雨等による被害があった際の緊急参集や注意報等の発令、防災アプリの開発や普及等に従事していました。大雨による被害のあった自治体への派遣業務等を通じ、人の命を守ることの重要さを実感しました。特に、防災アプリの開発、普及においては、どのような機能を持たせれば被害が少なくなるのか、頭を悩ませながらの業務でしたが、思い出深い経験です。

Question02
国家公務員を志望したきっかけや理由を教えてください
また、経験者採用試験の受験に向けてどのような準備をしましたか

片山
様々な施策について頭を悩ます内に、こうした行政課題は一地方自治体だけが抱える課題ではなく、法律や制度を所管する国全体としての立場からのアプローチが必要なのではないかと考えるようになりました。実際に法律の改正や基本計画の改訂等により、現場が大きく変わった瞬間を見たことも影響を与え、国家公務員を志望するようになりました。
試験に向けては、基礎能力試験は参考書を利用し演習を繰り返しました。面接は、自身のキャリアや強みを整理し、焦らず説明ができるよう整理を行いました。

Question03
今携わっている業務について教えてください

片山
現在は、就職氷河期世代の支援に関する業務に従事しています。就職氷河期世代の中には、希望する就職ができず、不本意ながら不安定な仕事についている方など、様々な問題に直面してきた方が多く含まれています。こうした方々への支援に向け、政府全体としての方針をとりまとめています。非正規雇用者を正規雇用化した企業に対する助成や、ひきこもり状態の方々への相談対応、リ・スキリング支援等を通じ、一人でも多くの氷河期世代の方に支援施策が行きわたるよう、日々様々な検討を行っています。
Question04
国家公務員になって良かったことや国家公務員の魅力を教えてください

片山
社会のダイナミズムの中で日々社会課題は変化していますが、そうした課題に国としてどのように対応していくのか、そうした大きな政策方針の決定に携われることが国家公務員としての仕事の面白さだと思います。自分が携わっていることが国としての方針となり、今後の世の中にどのような変化をもたらすのかを形づくっていくことができます。このように社会課題に正面から向き合うことができるというのは、他にはない仕事だと思います。
同じように地方公共団体からの転職を悩まれている方もいるかもしれませんが、省庁の中には、地方公共団体からの転職者で活躍されている方も多くいます。是非、門戸を叩いていただければと思います!