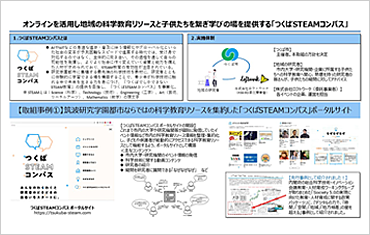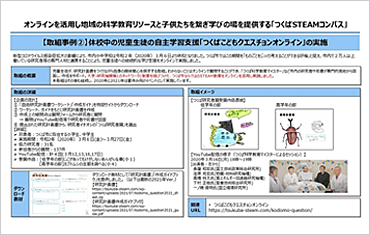Digi田甲子園の事例を中心に、
デジタルを活用した地域の
課題解決や魅力向上の優れた
取組をご紹介します。
オンラインを活用し地域の科学教育リソースと子供たちを繋ぎ学びの場を提供する「つくばSTEAMコンパス」
茨城県つくば市教育・子育て
実施に至る経緯・動機
- つくばの強み(科学技術)を活かし、子育て世代の移住定住ニーズの高い「学力・知力の向上ができる教育環境」を提供し、特に東京圏からの子育て世代の転入を加速させるとともに、次の世代の子どもたちもつくば市で育てたいと思える「まち」をつくることで、持続的な人口の維持・増加を目指したもの。
- コロナ禍による学校の休校、科学教育イベント自粛等により、従来子どもたちが経験・体験することができた学びの場を継続するための環境づくりが急務であった。
解決する課題の具体的内容
- 情報化、グローバル化といった社会変革が予測困難なスピードで進展していく将来世代にとって、科学技術を正しく理解し活用する力、課題を主体的に発見し解決する力等を養うのにSTEAM教育が有効である中、十分な取組ができていなかった。
- また、コロナ禍による休校など、学習の継続が困難になった子どもたちに対してオンラインを活用した学習支援の場を提供することで、休校期間を「自分の興味・関心を探求する時間」という前向きな位置づけに転換することが可能となった。
参考:つくばこどもクエスチョンオンライン https://tsukuba-steam.com/kodomo-question/ - 市内には約150にも及ぶ官民の研究機関等、1万人以上の研究者が集積しており、科学教育を推進していく上で、最適な人的資源と学習素材としての科学技術リソースが揃っているが、それらが「見える化」されておらず、活かされていなかった。
- これらのリソース情報を「つくばSTEAMコンパス」ポータルサイトに集約化するとともに、子どもたちへの科学教育へ協力いただける地域の研究者ネットワークを構築したことで、有益な情報発信、魅力的な科学教育オンラインコンテンツの配信が可能となり、全国の子育て世代に対して「つくばのSTEAM教育」を発信することが可能となった。
参考:つくばSTEAMコンパス https://tsukuba-steam.com/
デジタルを活用した取組による成果
つくばクエスチョンオンライン(2020年3月実施)
- 開催1週間(2020/3/4~2020/3/10)のセッション数:11,215セッション
- アクセス地域:75%が市外、地域順では第1位の市内に続き、第2位:大阪(6.7%)、第3位:横浜(5.64%)と遠隔地からもアクセスを獲得
取組全体
- つくばSTEAMコンパス開催イベントの延べ参加者数:798名
- 本取組で研究者からオンライン指導を受けた参加者が「第18回小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」(主催:日本損害保険協会)まちのぼうさいキッズ賞(日本ユネスコ国内委員会会長賞)、「第62回自然科学観察コンクール(主催:毎日新聞社、自然科学観察研究会)健闘賞を受賞
- 内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)教育・人材育成ワーキンググループ「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ(案)」に『1.(4)「時間」「空間」「地域」「地方格差」の壁を越えるデジタルの力」』の事例として掲載
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kyouikujinzai/saishu_print.pdf
本取組の特徴的な点やデジタルの活用において工夫した点
- つくばは研究学園都市ではあるものの、「次世代人材への科学教育に熱意を持っている研究者」と「科学技術に興味関心を持つ子ども」が、個別に繋がることは難しかった。本取組は、オンラインを活用することで、「なぜ?」と思った疑問を「相談したい子ども」×「応えたい研究者」双方のニーズをマッチングするとともに、地域の魅力的な科学教育コンテンツとして発信を可能とした先進的な取組である。
- オンラインの活用により、「時間」「空間」「地域」を超えて、つくばの科学技術リソースへアクセスすることが可能となった。
- また、オンラインを活用することで、「ものづくり」「農業」など、地域の特徴的な地場リソースと教育を掛け合わせることで、他地域でも本取組と同種の教育環境を子どもたちへ提供することが期待できる。
- 学校でのSTEAM教育に関して、GIGA端末に導入されたMicrosoft Teamsを活用し、授業以外でも児童・生徒と研究者がチャットベースでコミュニケーションを取れることで、子供たちの探究活動を継続的に支援する仕組みを構築した。
成果をあげるためのポイント
教育事業という観点から、市長部局である当課が単独で事業を企画し運営するのではなく、教育長部局である教育局と連携することで、現在の教育方針、学校の現状を踏まえた事業として、部局を超えた協力関係を構築できたことが大きかった。
デジタル化を実施するにあたり、苦労した点と対応方法
実際の学校現場でオンラインによるSTEAM授業を展開する際に、ネットワーク環境、校務PCのスペック、電子黒板の数といったインフラの問題が都度発生し、事前確認→問題への対処に相応の時間を要した。また、学校側で使用しているMicrosoft Teamsのアカウント権限の問題で、当課でTeamsを直接管理できず、チャンネル作成、招待といった管理業務が学校側の負担になるという課題が生じた。
いずれについても、学校の管理部門である教育局と連携し、IT支援員を派遣する等、学校現場に解決を委ねず、管理部門である我々が間に入ることで1つ1つ対処した。
今後DX化に取り組む自治体等へのアドバイス
オンラインを活用することで、つくばの科学技術リソースを活用したSTEAM教育は他地域でも実施可能である。また、「ものづくり」「農業」など、地域の特徴的な地場リソースと教育を掛け合わせることで、本取組と同種の教育環境を子どもたちへ提供することが期待できる。参考にしていただければ幸いである。
- 連携団体
- 市内大学・研究機関・企業に所属する研究者、株式会社ロフトワーク(委託事業者)
- 問い合わせ
-
- 部署
- つくば市政策イノベーション部科学技術戦略課 科学の街推進係
- 電話
- 029-883-1111
- メールアドレス
- sts01@city.tsukuba.lg.jp