地方創生2.0 政策の5本柱
地方創生2.0では、その目指す姿である「新しい日本・楽しい日本」をつくり出していくため、次の5本の柱に沿った政策を力強く展開していきます。
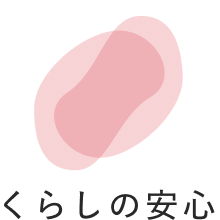
安心して働き、暮らせる
地方の生活環境の創生

稼ぐ力を高め、付加価値創出型の
新しい地方経済の創生
~地
方イノベーション創生構想~

人や企業の地方分散
~産官学
の地方移転、
都市と地方の交流等による創生~
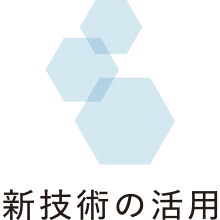
新時代のインフラ整備とAI・
デジタルなどの新技術の徹底
活用
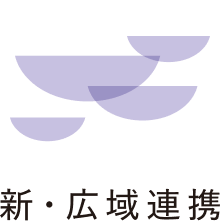
広域リージョン連携
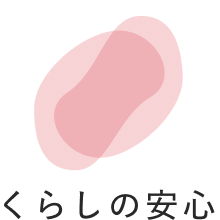


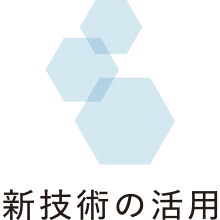
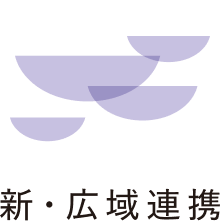
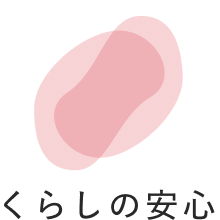
安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
民主導でハード整備からソフト運営まで担う新しいタイプの企業城下町、人を惹き付ける質の高いまちづくりの推進
本年6月中に総理をトップとする会議を新地方創生本部の下に創設
意欲と能力のある「民」の力を活かす観点から、地方創生に民間の資金とエネルギーを投じ、新たなまちづくりに取り組む企業経営者をロールモデルとして、全国各地でこうした取組を普遍化させていく。このため、新地方創生本部の下に、内閣総理大臣をトップとする会議体を立ち上げ、民主導の地方創生の取組を進めるために必要となる行政の対応(規制制度改革や支援)の在り方や、企業経営者のネットワークの形成などについて検討を行う。
地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革
68自治体で先行実施
公募した取組意欲ある68の自治体(24県、44市町村)と各府省横断のサポートメンバーで「地域働き方・職場改革ネットワーク」を形成し、「若者や女性にも選ばれる地方」に向けた地域働き方・職場改革の取組を始動する。今後3~5年程度、これらの先行自治体の成果・成功体験の蓄積を進め、全国的な波及を目指す(アンコンシャス・バイアス等の意識変革)。
地域くらしサービス拠点構想、ドローンや自動配送ロボットを活用した生活必需品の物流、 「地域協同プラットフォーム」の構築
暮らし続けるために必要なサービスを1か所で複数提供する拠点を整備
- 各省庁・地方公共団体の連携の下、民間事業者の知見や資本も活用しつつ、民間施設(スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア等)への行政機能の併設等、1か所で複数のサービスを提供する総合的な「地域くらしサービス拠点」を整備する。これらにオンライン、ドローン等のデジタル技術の活用による遠隔地へのサービス提供を組み合わせる。
- 人口・生産年齢人口の減少等により事業継続が難しい地域において、社会生活に不可欠なサービスの提供を可能とする共助型事業体を「地域協同プラットフォーム」と位置づけ、省力化・デジタル化・協同化によって、事業継続に取り組む事業体への支援の枠組みを新たに設ける。
全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開
3年後に、全国で100か所小規模・地域共生ホーム型CCRCの展開を目指す
年齢や障害の有無を問わず多様な人々が集い、持つ能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らす小規模・地域共生ホーム型CCRCの推進を中心として、「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開に向け、省庁横断的な「「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0検討チーム」を設置し、制度・運用の見直し等を行う。

稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生~地方イノベーション創生構想~
スタートアップを生み出すエコシステムの形成、地方公共団体によるスタートアップからの調達促進
スタートアップ・エコシステム拠点都市を8都市から13都市へと拡大
- ディープテック分野をはじめとしたスタートアップを一層生み出していく環境を整備するため、スタートアップ・エコシステム拠点都市において、地域の産業や大学等の研究特性を活かした分野・領域の重点化、アントレプレナーシップ教育の充実、オープンイノベーションや公共調達の促進、核となる組織・人材の育成・確保等の取組を強化し、スタートアップの創出から創業後の成長までの一貫した支援を推進する。
- 自治体ニーズとのマッチング・案件組成の支援、トライアル発注や随意契約の促進など契約の工夫、地域間の共同調達の円滑化に関するガイドの作成、知的財産の保護、インセンティブ措置の深掘り等、地方公共団体によるスタートアップからの調達を促進する多面的な取組を新たに実施する。
産官学共創に向けた拠点の形成
地方における先端研究設備等の利用機会を3倍以上増加させることを目指す
地方におけるオープンイノベーションの促進のため、地方大学や国立研究開発法人等の産官学の連携拠点・地方創生型共創拠点(例:現状地域大学関連26か所、産総研関連3か所)を強化するとともに、地方大学、大学共同利用機関等に AI for Science に資する自動化・自律化・遠隔化等の機能や世界に先駆けた新たな計測・分析機能を備えた先端研究設備等の共用拠点を整備しネットワークを構築する。
地域を支える企業の輸出・海外展開支援を通じた高付加価値化
新規輸出1万者
中堅・中小企業等の輸出額・現地法人売上高35.5兆円を目指し、商社やメーカー出身の専門家による販路開拓支援や越境EC等を活用した輸出先の多角化など、全都道府県に支援拠点を持つ独立行政法人日本貿易振興機構をはじめとする関係機関が連携し、「新規輸出1万者支援プログラム」を更に充実させる。
観光・インバウンドの地方誘客の促進を通じた高付加価値化
2030年訪日外国人旅行者数6,000万人・消費額15兆円
2030年訪日外国人旅行者数6,000万人・消費額15兆円を目指し、インバウンドの地方誘客を促進するため、「多様な地域資源」を生かした観光コンテンツ造成や観光客向けの移動手段などの受入環境整備等に取り組む地域等を支援し、観光地の高付加価値化を進める。
農林水産業の未来を創るスマート技術の開発・普及促進
2030年までにスマート農業技術を活用した面積を50%にすることを目指す
農林水産業の飛躍的な生産性向上や環境負荷低減を実現するため、農地の大区画化、共同利用施設の再編・集約化、多収性・高温耐性等を備えた品種の開発・導入に加え、AIやデジタル、衛星情報等の宇宙技術など先端技術を利用した高度な管理や出荷手法等の導入、生産者の労働負担を軽減するリモート監視やリモート操作を活用した労働力の外部化・無人化等により、徹底的な効率化・省力化に向けたスマート農林水産業技術の開発・普及を加速化する。将来的には、農業者の指示でAIを搭載したロボット農機が様々な作業を行う姿を実現する。
中堅・中小企業に対する地域の支援体制の構築
中堅企業の付加価値増加率 実質 4%/年(経済成長目標の4倍)以上を目指す
- 「中堅企業成長ビジョン」等で掲げた目標の達成に向け、累計6,000億円(令和5年度補正及び令和6年度補正)の大規模成長投資補助金など、設備投資や海外展開、M&A等に対する措置を通じて、地域経済を牽引する中堅・中小企業の成長投資を促進する。
- 高度化する経営課題への対応として、地方9ブロックごとの広域的な支援の枠組みである「地域円卓会議」を通じて、地産外商に積極的に取り組み地域貢献度の高い企業を重点支援企業として選定し、各省庁の地方支分部局や民間支援機関による省庁横断的なプッシュ型の伴走支援を行うなど、地方での企業支援体制を強化する。
文化・スポーツを活かした高付加価値化の取組の強化
2026年までにスポーツツーリズム関連消費額3,800億円
- 各地の文化資源をいかし、インバウンドの呼び込み等を更に進めていくため、NEXT日本博(仮称)を創設し、人材育成を含む一体的な伴走による、地域に根ざした文化観光コンテンツの創出に重点化するとともに、マンガ、アニメ、ゲーム、映画等のコンテンツが有する複合的な地方創生の力の発揮に向け、アニメツーリズムやロケ誘致、博物館・美術館等の拠点化等を推進する。
- スポーツコンプレックスの推進などをはじめ、地域に応じた伴走支援や、大規模なスポーツ大会の開催などスポーツを活用したまちづくり・観光との連携の充実等により、スポーツが持つ地方創生への高いポテンシャルを最大限発揮させ、地域に楽しみや交流拡大、経済活性化をもたらす。
豊かな自然環境・自然景観を活用した地域づくり
早期に自然共生サイトを500以上認定することを目指す
- 自然共生サイトや里海づくり、環境と調和した農林水産業、グリーンインフラの活用促進等を通じて、地域の自然資源の豊かさと地域の価値を相互に高め合う「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を進める。
- 国立公園等の利用拠点において、滞在体験の魅力向上に資するソフト・ハード両面の取組を総合的に実施し、世界遺産やジオパーク等の地域資源とも連携しながら、「保護と利用の好循環」を創出する。
循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行
先進技術の実装等の高度な資源循環事業を3年で100件以上認定
廃棄物等を地域資源として活用し付加価値創出等を進めるため、先進技術の実装支援等により広域的な廃棄物等の回収や再生材の安定供給を行う新たな資源循環ネットワーク・拠点を構築する。また、「資源循環自治体フォーラム」を活用した資源循環ビジネスの創出の支援、農山漁村のバイオマス資源や里山広葉樹材の活用、資源を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備等も進め、関係省庁の施策を統合したパッケージにより、地域の資源循環の実現を総合的に推進する。
再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進
2030年度までに脱炭素先行地域を少なくとも100地域で実現し、先行的な取組を普遍化
脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等を通じて得られたノウハウの発信等により先行モデルを普遍化するとともに、熱の脱炭素化や水素・ペロブスカイト太陽電池等の新技術を地域に実装する「地域GXイノベーションモデル」の構築の検討や、適切な営農を確保しつつ農業者の所得向上にも資する営農型太陽光発電やカーボン・クレジットの創出等を推進する。
地域経済の更なる成長に向けた地域金融力の強化
2026年通常国会へ関連法案の提出を目指す
地域経済の更なる成長に向け、地域金融が地域の多様なステークホルダーと連携しつつ、融資にとどまらない多様な金融仲介機能を発揮することが重要であり、今後、地方創生2.0に向けた地域金融力を強化するため、地域の事業者に対する経営改善・事業再生等の支援や事業性融資の推進を含めた地域金融機関による地方創生の取組の後押しとともに地域金融機関自身の経営基盤強化(資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保策を含む資本参加制度や資金交付制度の延長・拡充等の検討)を柱とする地域金融力強化プランを策定し、推進する。
「新結合」を全国各地で生み出す取組
本年7月に関係省庁による「新結合」の支援体制を立ち上げ
官民プラットフォーム等を通じた地域の地方公共団体、民間事業者や大学・高専、研究機関等の連携・マッチング支援など、新結合を面的に広げる取組を進めるほか、本年7月に、意欲ある自治体が行う高付加価値化などの取組を関係省庁が連携してアイデア段階から支援する体制を立ち上げる。また、地方の関係者に使いやすい、効果的な施策展開に向け、地方イノベーション創生構想関連施策を取りまとめ、分かりやすく一覧化する。

人や企業の地方分散~産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生~
政府関係機関の地方移転
移転の類型を提示し、地方からの提案を募集する。国でも主体的に検討し、順次結論を出す
DXの進展、リダンダンシーの確保の必要性などこの10年間の変化等を踏まえ、政府関係機関の地方移転に向けた取組を着実に進める。機関の全面的な移転だけでなく、業務形態及び地域の実情に応じ、サテライト方式や部局単位での移転など様々な類型を提示した上で、地方からの提案を募集し、国においても主体的に検討を進め、順次結論を出す。
本社機能の地方分散
2027年度までの3年間で本社機能の移転・拡充に伴う従業員増加数を約1万人とすることを目指す
地方での雇用や、地方への新たな人や資金の流れを創出するため、域外からの本社機能の移転・拡充を促す地方拠点強化税制について、制度の活用促進などによる環境整備や、制度を補完する地方公共団体等支援の好事例の公表とあわせ、活用実績等の分析を踏まえた制度の見直しを検討する。
「ふるさと住民登録制度」の創設
関係人口を可視化。関係施策と連携し、今後10年間で実人数1,000万人、延べ人数1億人を目指す
住所地以外の地域に継続的に関わる者を登録することで関係人口の規模や地域との関係性などを可視化し、地域の担い手確保や地域経済の活性化等につなげる仕組みを創設する。誰もがスマホのアプリで簡単・簡便に登録でき、各地域との関わりを深められるよう、関係府省庁が連携してプラットフォームとなるシステム構築を進める。
都市部人材の地方での活用促進
2027年度までの3年間でレビキャリの大企業人材の登録を1万人、プロ人事業等における副業・兼業による専門人材の活用を1万人とすることを目指す
大企業への働きかけを強化することで、REVICareer(レビキャリ)の人材登録を増やす。また、プロフェッショナル人材事業(プロ人事業)等における地域企業に対する補助制度などを通じて、都市部の経営人材や輸出の専門人材等と地域企業とのマッチング支援を強化するとともに、地方の副業・兼業による専門人材の活用を促す。
地方移住の更なる促進 ・二地域居住の促進
若者や、農林水産業、エッセンシャルワーカーへの支援を強化
地方創生移住支援事業について、若者への支援強化に加え、現行の中小企業等への就職だけでなく、地域社会を下支えするために必要となる人材を確保するため、支援の対象業種に地域の基軸産業である農林水産業をはじめ、自営業、医療・福祉等のエッセンシャルワーカーを位置付ける。その上で、農林水産省や厚生労働省等の関係省庁が実施する施策と連携するなど支援の相乗効果を高める。また、関係人口の中でも特に地域への関与が強い類型である二地域居住を促進する。
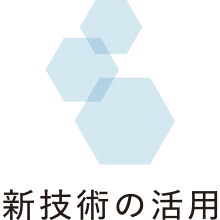
新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
ワット・ビット連携等の推進
日本全国47都道府県で地域のニーズに即したDX化と地域に最適なAIサービスを享受できるよう、2030年代までにオール光ネットワークの全国的実装を進める
電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)の下、オール光ネットワーク技術の実装を進めつつ、脱炭素電力が豊富な地域など電力インフラから見て望ましい地域や、大規模災害時のデジタルサービスの維持に資する地域へのデータセンターの誘導の観点も含め、光ファイバや5Gの全国展開とともに、電力と通信基盤を整合的・計画的に整備する。
GX産業立地の推進
大規模なデータセンターの適地やGXに不可欠な企業等を呼び込むための地域を5か所以上創出することを目指す
GX経済移行債による設備投資等の支援と国家戦略特区制度等を活用した規制・制度改革を一体で進め、「新技術の社会実装のための拠点形成」と「脱炭素型の産業団地の整備」による新たな産業集積(GX戦略地域(仮称))を目指す。
GX・DX分野における大規模投資の促進や人材の育成・確保
AI・半導体分野において今後10年間で50兆円を超える官民投資、GX分野では2032年度までの10年間に150兆円の官民投資を目指す
GX・DXを進める基盤である半導体・蓄電池等の分野は、関連産業の裾野も広く、既に九州地域では、製造業の設備投資が倍増近くまで拡大・継続するなど、広域的なエリアで大きな経済効果等を生んでいる。経済安全保障等の観点も踏まえ、こうした大規模投資を更に促進するとともに、既存産業の高付加価値化や関連産業を含めた新たな産業集積の形成を支えるため、地域の産官学が広域的に連携して行う関連人材育成・確保に向けたコンソーシアムの創設やイノベーション拠点整備、人材育成拠点の形成等を推進する。
産業用地・産業インフラの確保
2033年までに工業用地の1万ha程度の増加を目指す
地域の産業用地・産業インフラを円滑に確保することを通じて、地方に効果的な投資が行われるよう、全国の産業用地情報を活用した産業用地マッチング事業を新たに創設し、既存の産業用地の利活用を促進するとともに、産業用地の計画的な整備を促進するため、関係法令の改正を含めた検討を行い、必要な措置を講じる。また、GX・DXも踏まえた産業インフラへの支援を行う。
デジタルライフラインの整備
ドローン航路:全国の国管理の一級河川(1万km)、送電網上空(4万km)での整備を目指す
自動運転サービス支援道:物流ニーズ等を踏まえ、東北から九州までをつなぐ幹線網の形成を図る 等
地方における生活必需サービスの維持・継続に向け、地方において自動運転やドローン等のデジタル技術を活用したサービス展開が可能となるよう、自動運転サービス支援道、ドローン航路、インフラ管理DX等の早期実施プロジェクトの成果も踏まえ、ハード・ソフト・ルールの3つの側面からデジタルライフラインの全国展開を加速する。
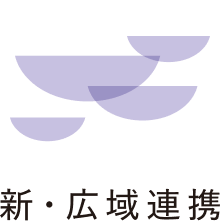
広域リージョン連携
都道府県域を超える「広域リージョン連携」の枠組みの創設
先行して3か所の広域リージョンにおいてプロジェクトを開始し、全国展開を目指す
複数都道府県の区域における地方公共団体と経済団体や企業、大学、研究機関等の多様な主体が、半導体関連産業の支援、公設試験研究機関等による共同研究・開発プロジェクトの促進、周遊型観光の促進などの複数のプロジェクトに連携して取り組むことを宣言する新たな広域リージョンの枠組みを創設する。広域リージョンとして実施するプロジェクトに対しては、省庁横断的に支援を行い、成長やイノベーション創出のための取組を面的かつ分野横断的に広げる。
広域地方計画等に基づく「シームレスな拠点連結型国土」の実現
広域地方計画:全国8つの広域圏で2025年度末頃の策定を目指す
- 地元経済界などの民間主体と行政が有機的に連携し、各地域が有する文化・産業等の地域資源の強みを最大限活かす「シームレスな拠点連結型国土」の実現のため、広域リージョン連携の枠組みとも結合しながら、都道府県域を超える広域圏内外の交流・連携を図るため広域地方計画の策定を進める。
- 「地域生活圏」を中心とした全国各地の地域課題の解決を図る新たな枠組みとも連動しつつ、こうした広域地方計画等※に基づく、既存の圏域を超える広域的なプロジェクトをハード・ソフト両面からの新たな枠組みで一括支援する。
※北海道総合開発計画及び沖縄振興開発計画を含む。
広域連携でのインフラ管理等の推進
広域連携によるインフラ管理を全国の自治体に拡大する
- 能登半島地震や埼玉県八潮市での道路陥没事故の被害等を踏まえ、業務共通化や情報整備・管理の標準化の推進等により、地方公共団体間の広域的な連携による効率的なインフラの維持管理・経営等(浄化槽の適切な利活用も含む)を目指す。
- 生活や経済等を支えるインフラを技術者が不足している地方においても持続可能にするため、複数自治体のインフラを「群」として広域に捉え、官民連携手法も活用して管理する地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)を普及させるとともに、地域の将来像を踏まえて必要なインフラを広域的観点から判断し、集約再編等の「インフラの再構築」を進める。


